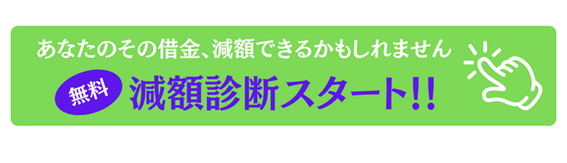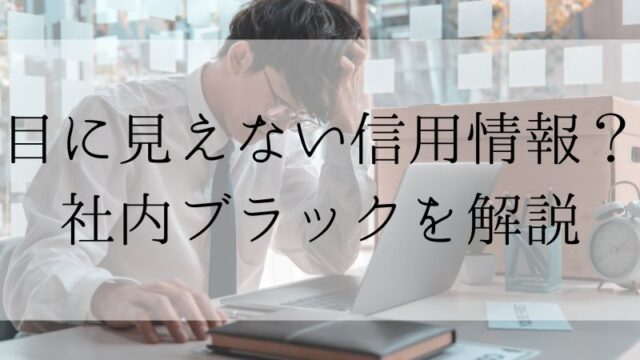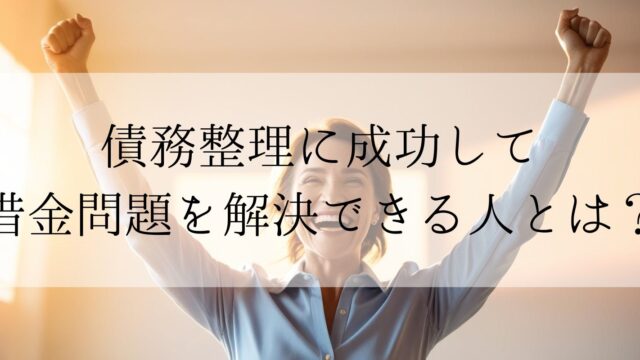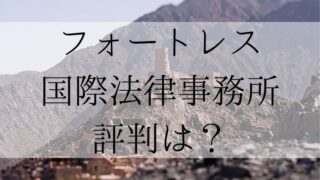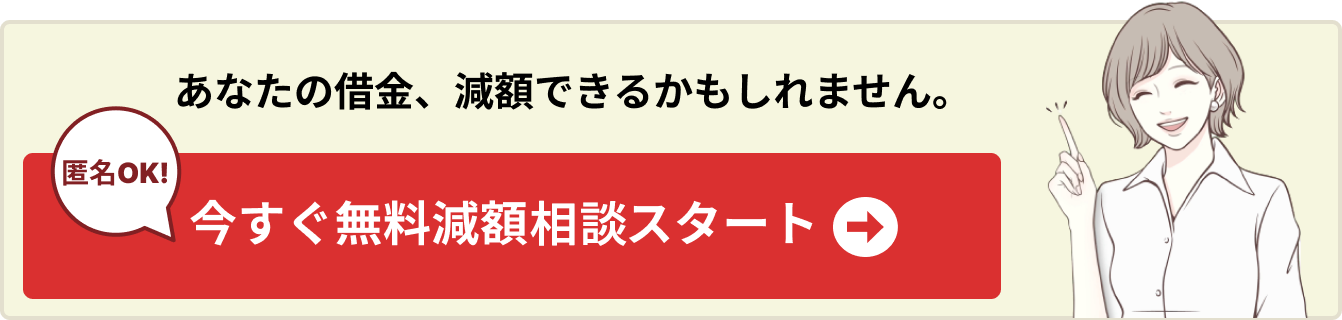借金の返済ができなくなり、裁判所から書類が届いたら、多くの方はパニックに陥ってしまうことでしょう。「どうしていいか分からない」「もう人生終わりだ」と絶望的な気持ちになるかもしれません。しかし、まだ打つ手はあります。
この記事では、借金で裁判を起こされた時に、どのように対処すべきかを専門家が解説します。冷静に正しい知識をもって対応すれば、状況を打開する道は必ず開けます。
目次
借金で裁判をされてしまうケース
支払いを長期に滞納してしまった時
貸金業者からの借金返済を長期にわたって滞納すると、裁判を起こされる可能性が高まります。もちろん、最初は電話やメールで連絡が来ますが、それを無視していると、次に督促状や催告状という書面が届きます。一般的に、滞納が2〜3ヶ月続くと、書面での督促が始まると言われています。
督促状を無視し続けると、「この人は返済する意思がない」と判断され、債権者との信頼関係が完全に失われてしまうのです。
しかし、債務整理の専門家である弁護士は、「督促状が届いたらすぐに連絡してください」と強くアドバイスしています。たとえば、病気や失業などで返済が困難になった場合、正直に事情を説明することで、月々の返済額を減らしたり、返済計画を見直してもらえたりするケースがあります。つまり、多くの貸金業者は、返済の意思さえあれば、柔軟な対応を検討してくれる傾向にあるのです。
逆に、連絡を絶ってしまうと、債権者は債権回収の手段として、裁判という法的措置を取らざるを得なくなってしまうのです。
債務整理中で弁護士費用の積み立てが長引き、和解できない時
債務整理を進める場合、まずは弁護士に支払う費用を積み立てることが一般的です。この費用がまだ用意できていない状態では、弁護士は債権者との和解交渉を正式に始めることができません。多くの債権者は、債務者が債務整理に取り組んでいることを知れば、交渉が始まるまで返済を待ってくれることが多いです。
しかし、この費用の積立期間が不必要に長くなると、状況は一変します。
特にありがちなのが、依頼者が費用や必要な書類を提出しないケースです。もし、積立期間中に、債務者が弁護士からの連絡を無視したり、積立を全く行わない状況が続いたりすると、債権者からすれば、「いつまで待てばいいのか分からない」「本当に債務整理を進めるつもりがあるのか」と不安になるのは当然です。
そこで、債権者は「このままではいつまでも返済されない」と判断し、債務整理の交渉を待たずに裁判を起こす可能性があるのです。
特に、債務整理は借金問題の解決策として多くの人に選ばれていますが、手続きが長引くと、かえって事態を悪化させるリスクがあることを知っておくべきでしょう。
借金の裁判にはどんな種類がある?
借金の返済を滞納し続けると、債権者は法的な手段で債権を回収しようとします。その際に利用される手続きは、主に「支払督促」と「訴訟」の二種類です。これらは全く異なる手続きであり、どちらの手続きで訴えられたかによって、その後の対処法も変わってきます。ここでは、それぞれの特徴を分かりやすく解説します。
支払督促とは?訴訟との違い
支払督促と訴訟は、どちらも債権回収のための法的な手続きですが、その内容や流れには明確な違いがあります。
| 支払督促 | 通常訴訟 | |
| 開始方法 | 簡易裁判所に申立て | 地方裁判所などに訴状を提出 |
| 手続きの概要 | 書類審査のみ | 口頭弁論・証拠調べなど |
| 裁判官の関与 | 書記官が書面を審査 | 裁判官が審理を担当 |
| 債務者の対応 | 2週間以内に異議を申立て | 裁判期日に出頭し反論 |
| 確定までの期間 | 異議申立てがなければ確定 | 長期間にわたることも |
支払督促は、債権者が裁判所に申し立てることで、裁判所の書記官が債務者へ支払いを命じる書面を送付するものです。(民事訴訟法第382条)
つまり、支払督促は、債権者が返済を促すために利用する、簡易的な手続きと言えます。証拠の提出は不要で、書面審査のみで進められるため、迅速に手続きを終えられるのが特徴です。
ですが、簡易的な手続きとは言え、支払督促も法的手続きであることから、支払督促は,確定判決と同一の効力を有するものとされます。(民事訴訟法第396条)
つまり、債務者側がこの書面を放置し、2週間以内に異議を申し立てなければ、支払督促は確定し、強制執行(給料や財産の差押え)が可能となってしまうということです。
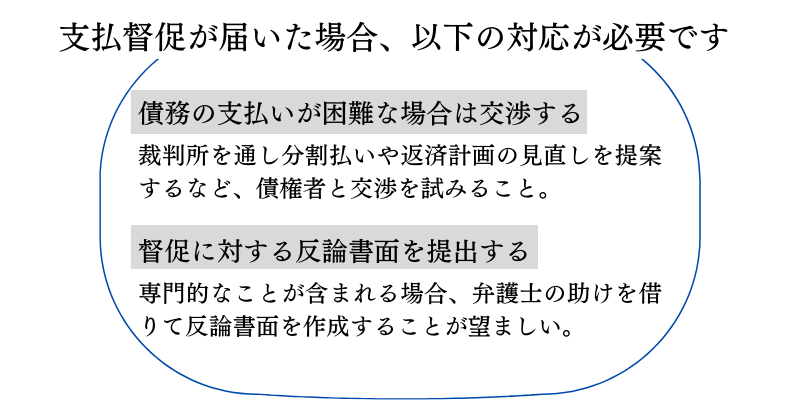
通常訴訟とは?
一方、通常訴訟は、法廷で当事者同士が口頭で主張し合い、証拠に基づいて裁判官が判決を下す正式な手続きです。支払督促と異なり、債権者は訴状とともに借金の証拠を提出する必要があります。
通常訴訟の手続きは、「訴状」という書類を裁判所に提出することから始まります。訴状には、誰が誰に対し、どのような理由で、いくらの支払いを求めるかといった詳細が記載されています。(民事訴訟法第134条)
訴訟の最大の特徴は、双方の主張と証拠に基づいて審理される点です。裁判が始まると、何度か口頭弁論という期日が設けられます。口頭弁論では、当事者や弁護士が法廷に出席し、互いの主張を述べ、証拠を提出します。(民事訴訟法第87条)
裁判官は、これらの情報をもとに、事実関係を明らかにし、法律に基づいて判断を下します。
どちらの手続きでも、裁判所から書類が届いた時点で放置しないことが最も重要です。もし、心当たりのない請求や、詐欺の疑いがある場合は、速やかに弁護士に相談し、適切な対応をとることが必要です。
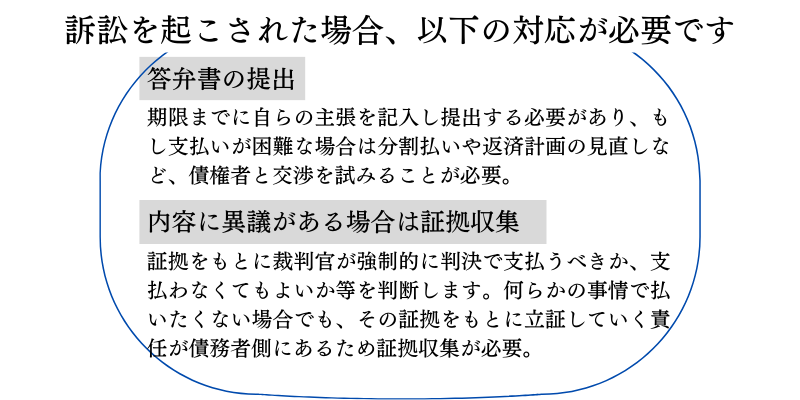
裁判所から書類が届いたらどうする?専門家に依頼するべき理由
裁判所から書類が届くと、誰もが驚き、頭が真っ白になってしまうかもしれません。
しかし、この段階で冷静に対応できるかどうかが、その後の人生を大きく左右するといっても過言ではありません。
ここでは、専門家に依頼すべき理由とともに、正しい対処法を解説します。
書類を無視するのはリスクが大きすぎる
「どうせ払えないから」と裁判所からの書類を無視することは絶対に避けてください。なぜなら、書類には必ず対応期限が定められているからです。特に、支払督促の場合は、2週間以内に異議を申し立てなければ、相手の主張がそのまま認められてしまいます。
期限を過ぎると、裁判所が債務者の財産を差し押さえることを許可する「強制執行」へと進んでしまいます。一度、差し押さえが始まると、給料や銀行預金が強制的に差し引かれるため、生活に深刻な影響が出るだけでなく、差し押さえを取り下げるには、借金を一括で返済するか、自己破産などの手続きに進むしかありません。
つまり、多くの人が書類を放置した結果、財産を失ってしまうのです。このようなリスクを避けるためには、弁護士や司法書士に依頼をして、債務整理手続を行うことがベストだと言えるでしょう。

時効の可能性があるなら専門家に相談を
もし、「届いた書類に書かれている借金に心当たりがない」あるいは「かなり昔の借金では?」と感じるなら、その借金は時効を迎えている可能性があります。特に、借金の回収を仕事とする債権回収会社へ回収を委託されている場合は、時効の援用が出来るケースも少なくありません。
借金の時効は、最後の返済日から5年と決まっています。しかし、時効期間が過ぎたからといって、借金が自動的になくなるわけではありません。債務者本人が「時効が成立している」と主張すること(時効の援用)で、初めて債権者の請求権が消滅するのです。
ただし、時効援用が使えるケースと使えないケースも存在します。裁判になると時効の完成猶予を受けている可能性もあり、この場合も時効の主張はできません。
そのため、時効を迎えている可能性がある借金で訴えられた場合は、専門家である弁護士や司法書士に相談をしてみましょう。そして、時効の成立を適切に主張し、借金問題を解決できる可能性を探るべきでしょう。
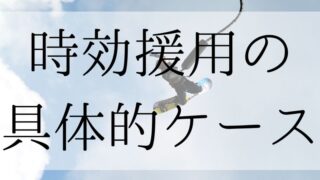

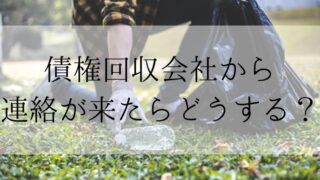
支払いができないなら債務整理を検討するべき
裁判に直面した場合、自分で対応しようと考える人もいるかもしれません。しかし、裁判は多くの専門用語や複雑な手続きを伴い、一般の方が一人で対応するのは非常に困難です。
弁護士に相談すれば、最適な解決策を提案してくれます。借金問題に詳しい弁護士は、あなたの状況に合わせて、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)などの手続きを進めてくれます。特に、借金の支払いが全くできない状況であれば、自己破産も選択肢の一つとなります。
自己破産は、裁判所の手続きを経て借金の返済義務を免除してもらうもので、経済的に行き詰まってしまった人が、人生を再スタートするための有効な手段です。
裁判中であっても債務整理は可能です。ただし、一刻を争う状況なので、できるだけ早く弁護士に相談し、今後の対応を検討することが大切です。弁護士に依頼することで、書類作成や裁判期日への出頭など、煩雑な手続きをすべて任せることができ、精神的な負担も軽減されます。