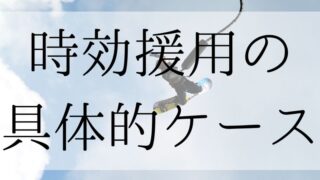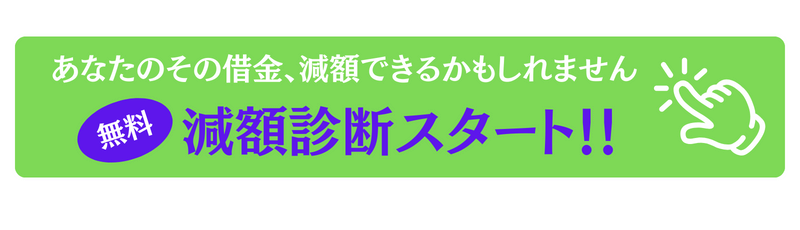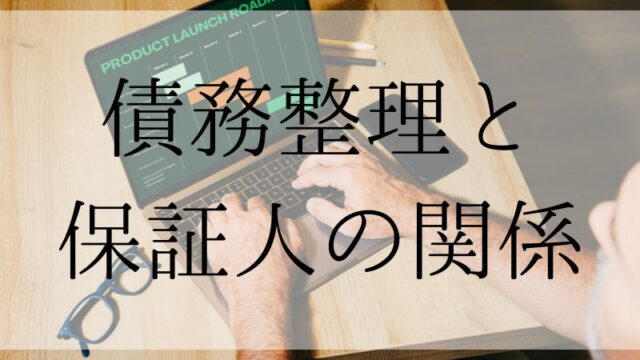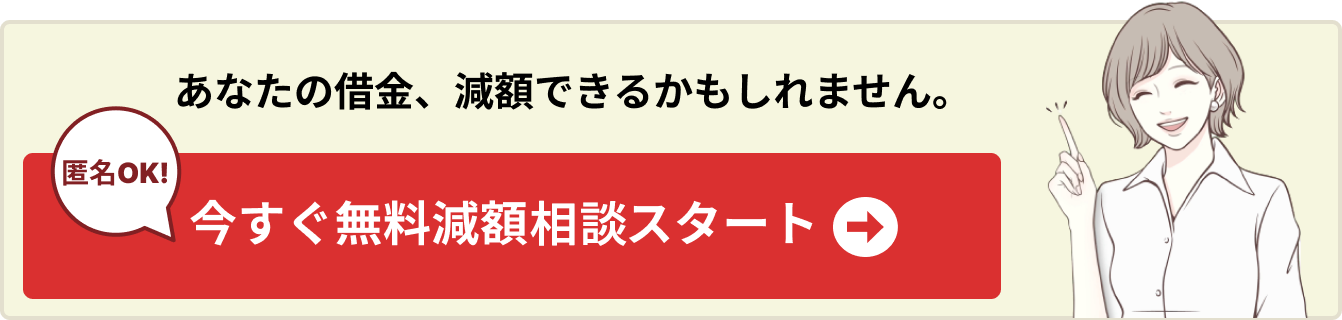借金の返済を長い間していないと、「もう時効だから大丈夫」と思っていませんか?確かに、借金にも消滅時効という制度があり、一定期間が経過すると債務が消滅する可能性があります。
しかし、時効が成立するには厳密な条件があり、時効の援用という手続きを踏まなければなりません。また、うっかり債務を認めてしまうと、時効の利益を受けられなくなってしまうこともあるのです。
時効援用にはメリットもありますが、リスクも伴います。専門家に相談しながら、慎重に対応することが大切です。この記事では、消滅時効の条件などを詳しく解説します。借金問題でお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
借金にも時効がある?「消滅時効」とは?
「消滅時効」とは?
「時効」と聞くと、刑事事件で時間が経っても解決せず、迷宮入りして自動的に無効になるようなイメージがありますかもしれません。
実は借金にも「時効」があるのです。
では、そもそも、借金の時効とは、どのようなものなのでしょうか?
「消滅時効」とは、一定の期間、債権者が債務者に対し、借金回収の権利を行使せず経過した場合に、その回収権利を消滅させるものです。(債権等の消滅時効 民法第166条)また、時効の効力は、その起算日にさかのぼると定められており、借金を借りたという効力が、借りた当初にさかのぼって消滅することとなります。((時効の効力)民法第144条)
時効援用のメリット
時効援用の最も大きなメリットは、借金の返済義務がなくなることです。
時効が成立すると、借金の返済義務が消失し、それに伴い債権者からの取り立ても完全に停止します。これにより、毎日のように続いていた支払いのプレッシャーから解放されることができます。
また、時効援用は、自己破産など他の債務整理とは異なり、財産を失うことなく手続きを進めることができます。
自己破産の場合は財産を処分する必要がありますが、時効援用は単に時効の成立を主張するだけの手続きなので、自宅や貯金など自分の財産をそのまま保持できます。この点が、時効援用の大きな魅力となっています。
時効援用の手続きは非常にシンプルで、債権者に対して内容証明郵便を送るだけで完了することも多いです。そのため、自己破産や個人再生のような他の債務整理に比べて、手間も費用も大幅に少なく済み、手続きが家族や勤務先に知られるリスクが少ない点も大きな利点です。
最後に最も重要なポイントとして、信用情報機関に登録されていた事故情報(延滞情報など)が、抹消されることが期待できます。これにより、今後のクレジットカード利用やローン申請の際に、以前の借金の影響が薄れる可能性があります。信用情報機関の一つであるJICCでは、「「時効の援用」については、お客さまが債権者である登録会社に対し「時効の援用」をし、登録会社と認識に相違がない場合に、時効の起算日に遡って完済として登録されます(その時点で登録期間経過により登録情報は抹消されます)。」としており、契約当初にさかのぼって借金の記録を抹消するとしています。(参照:「JICCに登録されている信用情報は、どのくらいの期間登録されるのですか?」)
これにより、信用情報に載っている事故情報が抹消されるケースがあることは、早期の信用情報の回復に資することと言えるでしょう。

時効援用のデメリット
上記のようなメリットがある一方で、時効援用に失敗する場合があることには注意をするべきでしょう。
時効援用に失敗してしまうと、様々なリスクが伴います。最も大きな問題は、借金の返済義務が残ってしまうことです。そして、長期間返済を行っていないため、未払いに対する利息や手数料である遅延損害金が加算され、請求額が増加することもあり得ます。元金が数十万円だったものが、数百万円にまで膨れ上がることもあるのです。このような状況に陥ると、返済が困難になってしまうでしょう。
また、時効援用を試みたことで、債権者に自分の居場所が知られてしまうリスクもあります。もし債権者が居場所を特定し、訴訟を起こした場合、時効が更新されて再度消滅時効の期間を経過するまで、借金の返済義務が延長されるする恐れがあるのです。
さらに、時効援用を行うと過払い金請求ができなくなるケースもあります。過払い金請求は、過去に払い過ぎた利息を取り戻す手続きですが、時効援用と同時に進めることはできません。
もし借金が残っている状態で過払い金請求をすると、借金を「認めた」とみなされ、時効が更新されてしまうのです。反対に、時効を援用してしまった場合、過払金を請求できなくなるため、返ってくるはずのお金を取り戻し損ねるということが生じる場合もあり得ます。
以上のように、時効援用にはリスクが伴うことがあります。したがって、時効援用を行う前に、自分にとってどの手続きが最も有利であるか、慎重に判断することが大切です。
借金の消滅時効の条件
では、「消滅時効」が成立するにはどのような条件があるのでしょうか?
民法では、2つの条件が明文で規定されています。
さらに、時効の完成猶予及び更新がされていないこと(民法第147条以下)も条件となります。
条件①債権の消滅時効の期間が経過している
時効援用を成立させるためには、まず借金の消滅時効期間が経過している必要があります。消滅時効期間は、借入れの時期によって変わってきます。
令和2年3月31日以前に銀行やサラ金などの金融業者から借りたお金の時効期間は5年、信用金庫・個人間の貸借奨学金などの場合は10年と定められていました。
一方、民法の改正により、令和2年4月1日以降の借入れについては、債権者に関係なく、「権利を行使できる時から10年間」または「権利を行使できることを知った時から5年間」のどちらか早い方となりました。
金融業者からの借金は通常、返済期日が決まっています。この返済期日は、債権者が権利を行使できることを知った時に当たります。つまり、金融業者からの借金の消滅時効期間は、返済期日の翌日から5年間ということになるのです。
したがって、時効援用を成立させるには、「返済の期日」もしくは「最終返済日」から5年または10年が経過している必要があります。
ここで、「5年」と「10年」の違いについて説明しましょう。これは、2020年4月の民法改正が関係しているのです。民法の改正によって、時効の考え方である起算点と期間が変更されました。
つまり、民法改正後に発生した借金は、以下のいずれかのうち、早いタイミングの時効期間を適用します。
- 主観的起算点➡債権者が借金の請求権を「行使できることを知った」とき
- 客観的起算点➡債権者が借金の請求権を「行使できる」とき
改正前は、消費者金融や銀行等からの借金の消滅時効期間は一律5年でした。しかし、改正後は、主観的起算点(債権者が借金の請求権を「行使できることを知った」とき)から5年、または客観的起算点(債権者が借金の請求権を「行使できる」とき)から10年のいずれか早い方となったのです。
つまり、民法改正後に発生した借金については、主観的起算点と客観的起算点のどちらか早いタイミングの時効期間が適用されるようになりました。
| 借入先の種類 | 消滅時効の期間 | |
| 改正前(2020年3月31日まで) | 改正後(2020年4月1日以降) | |
| 消費者金融・銀行等 | 5年 | 主観的起算点から5年または客観的起算点から10年 |
| 信用金庫・個人間の貸借奨学金など | 10年 | |
(参考:法務省「民法(債権法)改正」)
条件②「時効援用」の手続きをする
借金の時効は時効期間が過ぎただけでは成立しません。
民法第145条では、「当事者等が時効の援用の意思表示をしないと、裁判所はこれによって裁判をすることができない」とされています。反対に言えば、時効の主張を出来るのは、時効の援用の意思表示を事前にしている場合だということです。つまり、時効援用を成立させるためには、「時効援用の手続き」が必要不可欠であり、時効の意思表示を行うことで初めて債務が消滅するのです。
では時効援用とはなんでしょうか?
時効援用とは、「時効の利益を受けます」という意思を、当事者が債権者に伝えることを指します。民法第97条では、「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」と定めています。通知と言うと書面で行うイメージがありますが、民法上、口頭でも通知とされています。時効援用の方法に特別な規定はなく、書面ではなく口頭で時効援用を主張することもできるのです。
ただし、口頭だと証拠が残りづらい関係上、一般的には「時効援用通知書」などの書類を内容証明郵便で債権者に送付します。手続きにはある程度の費用がかかりますが、弁護士事務所や司法書士事務所に代行を依頼することもできます。
なぜ、時効の援用が必要なのか?
ここで疑問に思うのは、なぜこのような面倒な手続きが必要なのかということです。これは、時効の利益を受けるかどうかを当事者に委ねるという趣旨によるものです。
世の中には、
時効になっていようが、時効の利益は受けません!
借金は何年経ってでもお返しします!
という潔い方もおられるでしょう。世の中には、時効になっていても時効の利益は受けず、何年経っても借金を返済したいと考える人もいるでしょう。そのような人にまで時効の効果を押し付けるのは適切ではありません。
したがって、当事者の意思を尊重するために、時効の援用が必要とされているのです。
条件③時効の完成猶予及び更新がされていないこと
時効の援用を成立させる3つ目の条件は、時効の完成猶予及び更新がされていないことが挙げられます。
時効の更新とは、民法第147条以下に定められた一定の更新事由が発生した場合に、その時から新たな時効期間の進行が開始されることです。
上記更新理由があることにより、時効期間の進行が阻止され歓声が猶予されたり、進行していた時効期間のカウントがゼロから再開される効果があります。
具体的に時効援用が出来るかどうかは以下の記事を参照してください。