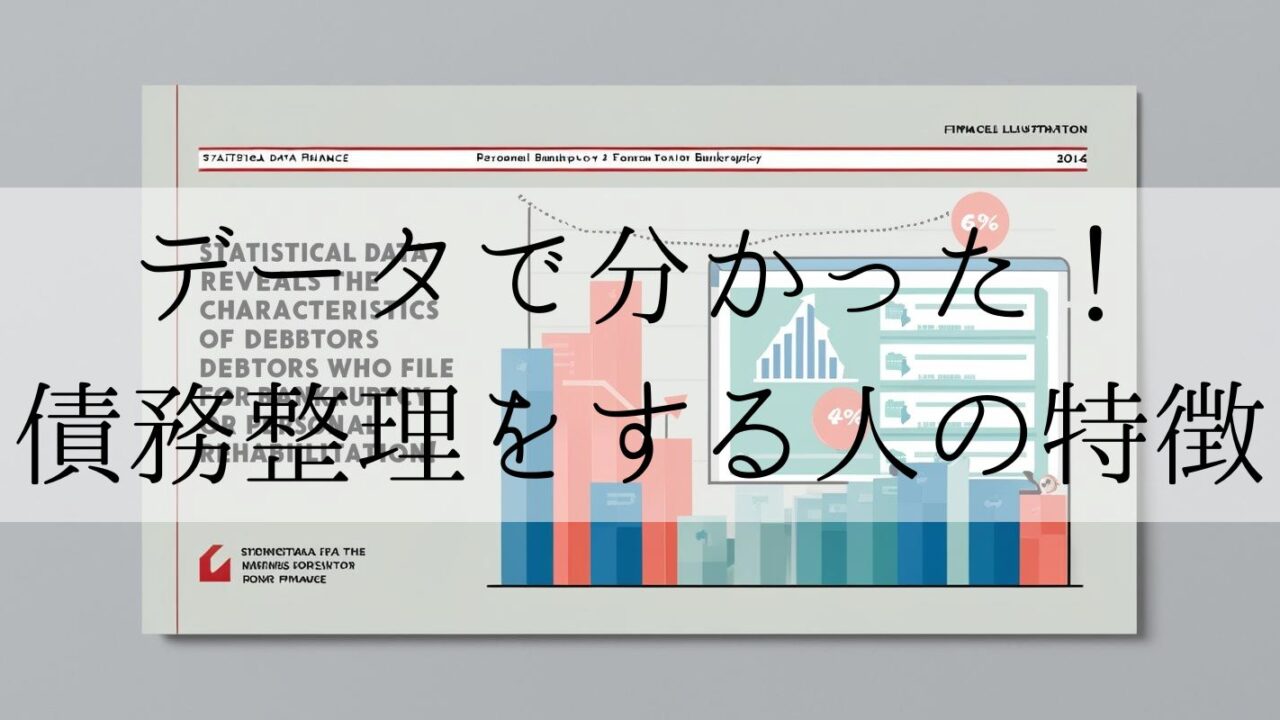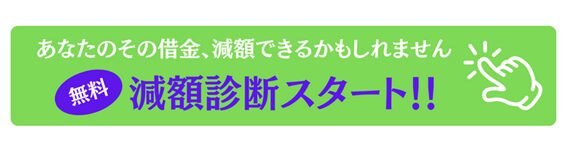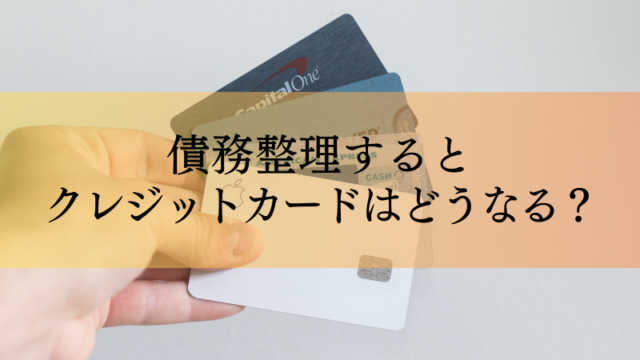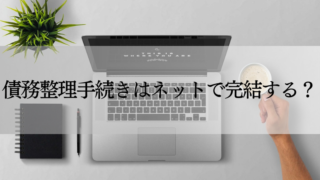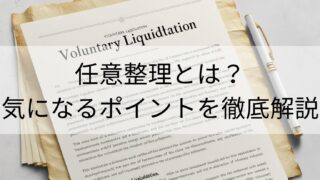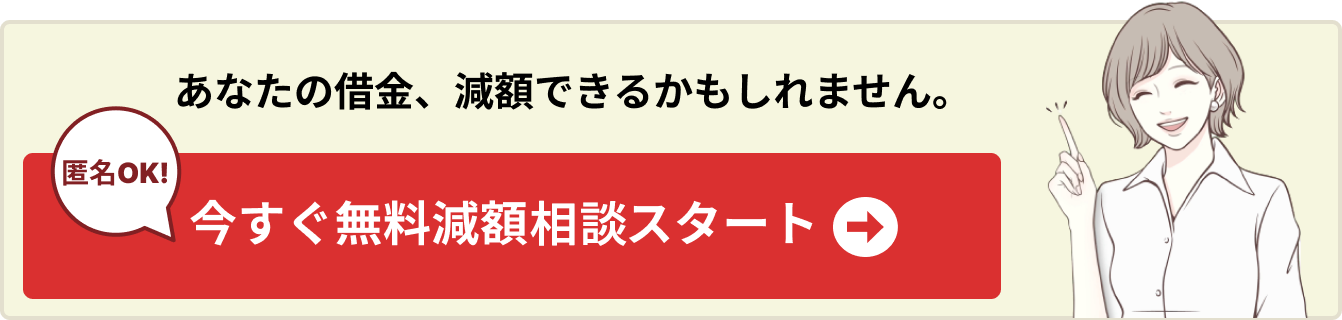個人再生と破産は、債務整理を目的とした法的手続きですが、申立者の特徴には違いがあります。
年齢層、性別、収入、負債額、職業、住居形態など、様々な観点から両者の共通点と相違点を見ていきましょう。統計データを基に、それぞれの手続きを選択する債務者の属性を詳しく解説します。
なお、本記事では、日本弁護士連合会「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査【報告編】」を参照しています。
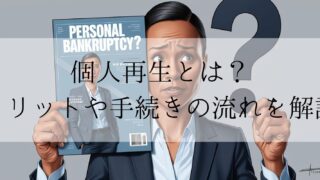
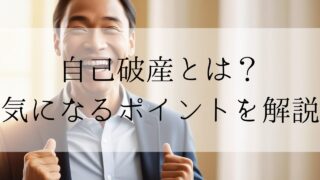
年齢・性別
個人再生申立債務者の年齢・性別
個人再生を申立てた債務者の年齢層では、近年、「50歳代」や「60歳代」の割合が再び増加傾向にあります。特に、50歳代の申立て者は、これまでより増加しており、22.41%から25.30%にまで上昇しました。また、60歳代も4.85%から6.02%に増加しています。一方で、70歳代以上の割合は減少しました。これは、個人再生を選ぶ年齢層がやや若年層にシフトしていることを示唆しています。
性別では、個人再生を申立てる男性が圧倒的に多いのが特徴です。調査によると、男性が申立てる割合は約8割を占め、過去の調査と比較して男性の割合が増加しています。これは、経済的な困難や仕事のストレスにより、男性が負担を感じるケースが多いためと考えられます。女性の割合は一貫して少なく、特に昨今では17%程度に留まっています。
この性別の差は、社会的な役割や経済的な事情に起因しているといえるでしょう。
破産債務者の年齢・性別
破産を申立てた債務者の年齢層は、年々変動が見られますが、特に「70歳代以上」の割合が増加しています。これは、1997年調査以降、徐々に増加し、今回の調査では過去最高の9.35%に達しました。これは高齢者の生活苦や医療費の増加が原因で、破産に至るケースが多くなっているためと考えられます。
さらに、20歳代の破産者も増加しており、9.92%に達しました。これは若年層の借金の増加や、消費者金融の利用拡大が影響していると考えられます。
性別では、破産債務者においても男性が若干多い傾向が続いています。男性は55.65%、女性は44.11%で、男性がわずかに多いものの、女性もほぼ半数に近い割合を占めています。
国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」によりますと、男性に比べて、女性は平均年収が低い傾向にあり、女性の平均年収が低い要因の一つとして、正社員と正社員以外の割合の男女差が考えられます。女性は全体の5割以上が正社員以外で働いているという実態から、給与が上がりづらく、年収が低く抑えられており、その結果、低収入を補うために借り入れを行い、破産に至るケースが多いのかもしれません。
債務者の年齢・性別の共通点・相違点
債務者の年齢や性別について、個人再生申立者と破産債務者には共通点と相違点がいくつか見受けられます。
共通点
- 年齢層の幅広さ
どちらのケースでも、債務者は様々な年齢層にわたります。20代から70代以上の年齢層まで、幅広い年代の債務者が存在しています。特に、年齢が上がるにつれて、借金返済が困難になる傾向があり、50歳代や60歳代の債務者も増加しています。このように、どの年齢層にも債務整理を必要とする人々がいる点は共通しています。 - 男性が多い
性別についても、個人再生申立者、破産債務者ともに男性が多い傾向があります。特に個人再生申立者では、男性が80%を超える割合を占めており、破産債務者でも男性の割合がやや高いです。これは、男性が家庭や仕事の経済的な責任を多く背負っていることが影響していると考えられます。
相違点
- 年齢層の特徴
個人再生申立者は、特に50代以上の年齢層に多く見られます。50歳代や60歳代の債務者が増加しており、これは中高年層が今後の生活を維持するために選ぶ手続きであるためです。一方、破産債務者では、20代や30代の若年層の割合が増加しており、特に20代の破産者は増加傾向にあります。このように、破産債務者はより若い世代が多い傾向があります。 - 女性の割合
個人再生申立者においては、女性の割合が比較的低く、約17%程度です。しかし、破産債務者の場合、女性の割合は44%に達しており、女性が多く見られる傾向があります。これは、家庭や育児などの生活費に関連する経済的な困難が、女性の場合にはより深刻化しやすいことが影響している可能性があります。 - 年齢層の偏り
個人再生申立者は、中高年層(50代、60代)の割合が増加していますが、破産債務者は逆に、20代や30代の割合が目立ちます。これは、個人再生が生活の再建を目指す手続きであるため、仕事を持つ中高年層が利用しやすいのに対し、破産は収入が不安定な若年層に選ばれる傾向があるためです。
このように、債務者の年齢・性別には共通点もあれば、個人再生と破産それぞれで顕著な相違点もあります。
収入
個人再生申立者の収入
個人再生を申立てた債務者は、破産債務者と比較して平均月収が高い傾向があります。
2017年の調査によると、個人再生申立者の平均月収は26万1,323円で、破産債務者の14万2,021円よりも大幅に高いことがわかります。これは、個人再生が「継続的な収入」が前提となるため、一定以上の収入が必要だからです。再生債務者は、弁済計画を履行するために収入を安定的に得ている必要があります。そのため、収入が低すぎると再生手続きが適用されない場合もあります。
月収帯を見ると、個人再生申立者は、20万円以上30万円未満の層に多く見られ、特に25万円以上30万円未満の割合が高いです。また、30万円以上の層にも一定数が含まれており、収入層の幅が広いことが特徴です。こうした高い収入を持つ債務者は、生活再建を目指し、個人再生を選択するケースが増えています。男女別に見ると、男性の割合が圧倒的に多いことが確認されており、収入を得る立場として男性が主に再生申立てを行うことがうかがえます。
破産債務者の収入
破産を申立てた債務者の平均月収は14万2,021円で、個人再生申立者に比べて低い水準です。これは、破産手続きが借金の免除を目的としており、収入の多寡に関わらず、すべての借金を清算するための手続きであるためです。収入が低くても、生活が困窮している状態であれば破産を選ぶことが一般的です。
収入帯で見ると、月収15万円未満の債務者が非常に多く、特に女性の割合が顕著に高いことが特徴です。女性の収入は男性に比べて低い傾向があり、収入層が低いことで破産を選択するケースが増えることがわかります。
特に、月収10万円未満の債務者の割合が高く、これらの債務者は生活費や日常的な支出に困り、破産を申立てることが多いです。収入が安定しない、または低収入で生活が困難になっている状況が影響しています。
債務者の収入の共通点・相違点
個人再生申立者は収入層が比較的高く、月収が20万円以上の層が多いのに対して、破産債務者は月収15万円未満の層が圧倒的に多いです。個人再生は「弁済計画の履行可能性」が求められるため、破産債務者よりも高い収入を得ている債務者が多い点が大きな違いです。
特に破産債務者では、収入が少ないことが直接的な原因となり、破産を選択する債務者が多く見受けられます。また、女性の収入が低く、破産を申立てる女性が多いことも特徴的です。
このように、個人再生と破産では収入の差が顕著であり、それぞれの手続きにおいて、収入の安定性や額が債務者の選択に大きな影響を与えています。
負債額
個人再生申立者の負債額
個人再生を申立てた債務者の負債額は、破産債務者に比べて低いことが特徴です。負債額が100万円未満の債務者も一定数いますが、200万円以上の負債を抱えている債務者が多い傾向にあります。特に、1000万円未満の負債額帯に多くの債務者が集中しており、この層が個人再生を選ぶ場合が多いです。負債額帯別で見ると、1000万円以上の負債を抱えている人は少なく、再生手続きが選ばれる要因として、収入が安定していることと、比較的低い負債額が影響しています。
また、再生債務者は、住宅ローンを含んだ負債も多く見られます。住宅ローンが含まれている場合、住宅の維持を希望するために個人再生を選択することが多いです。負債額帯としては、100万円未満や100万円から200万円未満の層が少数派ですが、200万円以上の負債を抱えているケースは多く、弁済計画を立てて一定の負債の減額を図りながら、生活再建を目指します。
破産債務者の負債額
破産債務者の負債額は、個人再生債務者と比較してかなり高額です。
2020年の調査によると、破産債務者の平均負債額は1,449万9,580円で、前回調査から減少傾向にありますが、それでも依然として高額な負債を抱えています。
ただし、負債額帯を見ると、1000万円未満の層が最も多く、その割合は74.36%に達しています。そのため、25%ほどの高額な負債を負った方が、平均を釣り上げているという点には注意が必要です。
負債額で注目するべきポイントとしては、負債額が100万円未満の層が増加していることです。これにより、少額の借金を抱えて破産申立てを行う債務者が増加しており、破産債務者の負債額の幅広さが顕著です。
破産債務者は、基本的に生活が困窮している場合が多く、収入が不安定であることも少なくありません。そのため、少額でも高い利息や延滞によって負債が膨らみ、最終的に破産申立てを行うことが一般的です。また、負債額が数百万円以上に達している債務者が多く、これが原因で破産を選択せざるを得ない状況が続いています。
債務者の負債額の共通点・相違点
相違点としては、個人再生申立者は、一般的に負債額が低めであることが多いです。特に、1000万円未満の負債層が多く、住宅ローンが含まれる場合もあります。
一方、破産債務者は負債額が高額であり、1000万円以上の負債を抱えている債務者が多数を占めます。破産申立ては、収入が不安定であったり、負債の返済が不可能になった場合に選ばれるケースが多く、支払いが一切できなくなった債務者が多いため、負債額も大きくなる傾向があります。
職業
個人再生申立者の職業
個人再生を申立てた債務者の職業において特徴的なのは、高い割合で給与生活者が占めている点です。調査によると、正社員として働いている債務者は83.00%に達し、給与生活者全体の92.64%が安定した収入を得ていることがわかります。
この点は、個人再生が弁済計画を履行しながら負債整理を進めるため、安定的な収入が不可欠であることを反映しています。
正社員以外の給与生活者も9.64%を占めており、パートやアルバイト、契約社員などの非正規雇用も少なからず見受けられます。
また、少数派ではありますが、自営業や自由業に従事している債務者も一定数おり、5.49%の割合を占めています。これらの債務者は、収入の安定性が低いことが多いため、負債額が増加して再生手続きに至るケースが多いです。一方で、会社役員や主婦・内職、年金生活者といった他の職業層は比較的少数派となっています。
全体的に見ると、個人再生申立者は安定した収入源を持っている場合が多いことが特徴です。
破産債務者の職業
破産申立てを行う債務者も、給与生活者として働いており、特に正社員および正社員以外の給与生活者の割合は増えています。正社員の割合は32.02%、正社員以外は27.50%となっており、合計すると約60%が給与生活者です。
しかし、無職の割合が高いのも特徴であり、13.23%の債務者が無職と報告されています。この点は、破産申立てを行う理由が収入不安定であったり、働くことが難しい状況にあることを示しています。
また、生活保護を受給している債務者も13.23%に達しており、生活が困窮しているために破産を選択したケースが見られます。年金生活者も一定数おり、7.26%が年金収入のみで生活している状況です。自営業や自由業の割合は4.44%と比較的低いですが、仕事の不安定さが経済的困窮につながり、最終的に破産に至る債務者も少なくありません。
破産債務者の職業は、安定した収入源を持つ者よりも、無職や生活保護を受けるなど、経済的に不安定な状況の人が多いことが特徴です。

債務者の職業の共通点・相違点
個人再生申立者と破産債務者の職業には共通点も多くありますが、重要な相違点も見られます。共通点としては、どちらも給与生活者が多い点です。
個人再生申立者は、特に正社員として安定した収入を得ている割合が高いのに対し、破産債務者は正社員および非正社員の給与生活者を含めても、全体の約60%を占めるにとどまります。
さらに、両者ともに自営業や自由業の割合は比較的少なく、この職業層においても安定した収入が確保できない場合が多いことがうかがえます。
相違点としては、破産債務者の無職や生活保護受給者の割合が高いことが挙げられます。
特に、破産債務者の13.23%が無職であることに対し、個人再生申立者の無職の割合はほとんどありません。
無職や生活保護を受ける債務者は、収入がなく支払いが不可能な状況に陥っているため、破産手続きを選ぶ傾向が強いです。一方、個人再生申立者は、主に給与所得が安定している層が多く、再生手続きに必要な弁済計画の履行が可能であることが大きな特徴となります。
住居形態
個人再生申立者の住居形態
個人再生申立者の住居形態については、本人所有の住宅を持つ割合が高いことが特徴です。最新の調査によると、37.88%の申立者が自己所有の住宅に住んでおり、これが破産債務者の3.47%と比較して圧倒的に高い割合です。個人再生は、住宅ローンを減額することが可能な手続きであるため、住宅を所有している債務者が多く利用していると考えられます。また、家族所有の住宅に住んでいる人も12.99%を占めており、合計すると、ほぼ半数近くの申立者が何らかの形で所有している住居に住んでいることになります。
しかし、2011年以降、本人所有の住宅割合は減少傾向にあり、住宅を所有する債務者の数が減っていることも見逃せません。一方で、持ち家でない割合は43.11%に達しており、これらの債務者は賃貸住宅に住んでいることがわかります。

破産者の住居形態
破産債務者の住居形態は、個人再生申立者と比べると、圧倒的に「持ち家でない」割合が高いことが特徴です。
最新の調査によると、破産者の74.25%が自己所有の住宅を持たず、賃貸住宅に住んでいることがわかります。これは、自己破産をする場合は、原則として持ち家を売却しなければならないため、住宅を保有している方が選べないという理由からこうなっているのかもしれません。
本人所有の住宅に住んでいる破産債務者は3.67%と非常に低い割合で、家族所有の住宅に住んでいる人は22.08%と比較的多いですが、それでも全体の半数以上が持ち家ではないことがわかります。
破産手続きは、住宅ローンの支払いが滞ることが多く、最終的に住居を失う可能性が高いため、このような住居形態が反映されているのでしょう。破産手続きの中では、住居が手放されることもあり、持ち家を維持することは難しいといえます。
債務者の住居形態の共通点・相違点
個人再生申立者と破産債務者の住居形態には、いくつかの共通点と相違点があります。共通点としては、両者ともに「家族所有」に住む割合が比較的高い点が挙げられます。個人再生申立者の12.99%が家族所有の住宅に住んでいる一方、破産債務者は22.08%とさらに多く、家族との同居や親からの支援を受けている債務者が多いことがわかります。
相違点としては、最も顕著なのは「本人所有」の住宅を持つ割合です。個人再生申立者の約37.88%が自己所有の住宅に住んでいるのに対し、破産債務者の3.67%と、両者の間に大きな差があります。この差は、破産申立てを行った債務者が住宅ローンの支払いや生活の困窮から住宅を手放している可能性が高いことを示唆しています。さらに、個人再生では、住宅を保持しながらの負債整理が可能なため、自己所有の住宅に住んでいる申立者が多いという特徴がありますが、破産では住宅を保持しづらく、賃貸住宅に住む債務者が多いという点が大きな相違点です。
同一家計の家族人数
個人再生申立者の同一家計の家族人数
個人再生申立者の同一家計の家族人数については、家族構成に一定の傾向が見られます。特に注目すべきは「単身」の割合です。最新の調査では、23.43%の申立者が単身であることがわかります。この数字は増加傾向にあり、単身世帯の申立者が多いことを示しています。これは、個人再生の手続きが、主に安定した収入を持つ給与生活者に利用されることが影響している可能性があります。家族が少ない場合、生活費の負担が軽く、再生計画に集中しやすいため、単身の申立者が多いことがうかがえます。
また、「2人世帯」の割合も19.14%と一定数存在しており、共働き世帯や子供のいる家庭が該当することが多いです。家族構成が小規模であっても、支払い能力に問題が生じることがあるため、個人再生を選択するケースが増えていることがわかります。さらに、「3人」や「4人」の世帯も一定数を占めており、家庭を持ちながら再生手続きを選択している債務者も多いことが特徴です。
破産者の同一家計の家族人数
破産債務者の同一家計の家族人数に関しては、近年「単身」の割合が増加しており、最新の調査では35.97%に達しています。この増加傾向は、1997年以降の最大値となっており、特に社会的な孤立や生活の困窮が影響していると考えられます。単身の破産申立者が多くなる背景には、収入が不安定で支払い能力が低下した結果、家族を養うことができず、最終的に破産を選択するケースが増加していることが影響していると考えられます。
一方で、「2人」世帯も26.45%と多くを占め、こちらは夫婦や親子など、最小限の家族構成を持つ破産者が多いことがわかります。また、「3人」世帯や「4人」世帯も一定数見受けられますが、これらの世帯では家計が困窮し、破産手続きに至ることが多いことを反映しています。「5人」以上の世帯になると割合は減少し、5人世帯は4.76%となっており、規模が大きくなるほど家計の負担が大きくなり、債務整理が困難になる傾向があります。
債務者の同一家計の家族人数の共通点・相違点
個人再生申立者と破産債務者の同一家計の家族人数にはいくつかの共通点と相違点があります。共通点としては、どちらのグループにも「単身」世帯が存在し、単身世帯が一定割合を占めている点が挙げられます。個人再生申立者では23.43%、破産債務者では35.97%が単身であり、いずれも生活の負担が比較的少ないことが影響していると考えられます。
相違点としては、個人再生申立者のほうが「3人」や「4人」世帯が多いことが挙げられます。個人再生手続きは安定した収入を持つ給与生活者が多く利用しており、家庭を持ちながらも支払い能力に問題が生じた場合に選ばれるケースが多いです。そのため、家族人数が3人以上の世帯が一定数存在します。一方、破産債務者のほうが「単身」や「2人」世帯の割合が高く、生活の困窮や経済的な困難から破産手続きを選ぶ場合が多いことがわかります。
また、破産債務者は「5人」以上の世帯が少ないのに対し、個人再生申立者には一定数の「5人」以上の世帯が存在することからも、破産のほうが家計の規模が大きくなるほど債務整理が難しくなりやすいことがうかがえます。
借入れから申立てまでの期間
個人再生申立者の借入れから申立てまでの期間
個人再生申立者の借入れから申立てまでの期間については、申立てまでに時間をかける傾向が見られます。特に「5年以上」の期間にわたる申立てが最も多く、最新の調査では83.67%に達しています。
この数字は以前より若干増加しており、個人再生を選ぶタイミングが長期的な債務整理を余儀なくされた結果であることを示しています。これは、長期間にわたって債務が積み重なり、返済能力が追いつかなくなるまで、申立てに至らないケースが多いことが反映されています。
逆に、「1年未満」や「1年~2年未満」の短期間で申立てを行った債務者は非常に少なく、それぞれ0.13%や0.80%にとどまっています。短期間での申立ては、通常、急な経済的困難や生活の変化が原因であり、少数派であることが分かります。また、「2年~3年未満」や「3年~4年未満」の期間も減少傾向にあり、これらの期間で申立てを行う債務者は少数派です。このデータからは、長期的な経済的圧迫を受け続けた結果、個人再生を選択するケースが多いことがわかります。
破産者の借入れから申立てまでの期間
破産者の借入れから申立てまでの期間についても、個人再生申立者と同様に「5年以上」の期間が最も多く、79.92%を占めています。この傾向は、借金が長期間にわたって膨れ上がり、最終的に返済が不可能になったことを示しています。破産を選択する債務者は、長期間の返済が続いても支払いの目途が立たず、最終的に法的な手続きを選ぶケースが多いことが分かります。
一方で、「1年未満」や「1年以上2年未満」などの短期間で破産を申請する債務者も一定数存在しており、それぞれ0.16%や2.02%となっています。これらの債務者は、急激な収入減少や予期せぬ生活の変化が原因で借金が急増し、短期間で返済が難しくなった結果、破産手続きに至ることが多いと考えられます。また、「2年~3年未満」や「3年~4年未満」の期間で破産申請をするケースも減少傾向にあり、これらの層は過去に比べて減少しています。
債務者の借入れから申立てまでの期間の共通点・相違点
個人再生申立者と破産者の借入れから申立てまでの期間にはいくつかの共通点と相違点が見られます。共通点としては、両者ともに「5年以上」の期間が最も多く、長期的に債務を抱え続けた結果、最終的に法的手続きを選択する傾向が強いことです。両者の間で「5年以上」の割合が非常に高く、債務者が借金問題に対して積極的に対応するのが遅れる傾向があることが分かります。
一方、相違点としては、個人再生申立者は「5年以上」の割合がやや高いことが挙げられます。個人再生を選択する債務者は、収入が安定している場合が多いため、長期間の返済計画が必要となることが多いからです。これに対し、破産者は短期間で申立てを行うケースが比較的多く、特に急激な収入減や生活の変化が原因で、早期に破産を選択することが多いといえます。この点が、破産と個人再生の間の大きな違いです。
また、破産者は「1年以上2年未満」の層が比較的多く見られる一方で、個人再生申立者はこの期間での申立てが少ないため、個人再生はあくまで長期間の計画的な債務整理手続きであることがわかります。