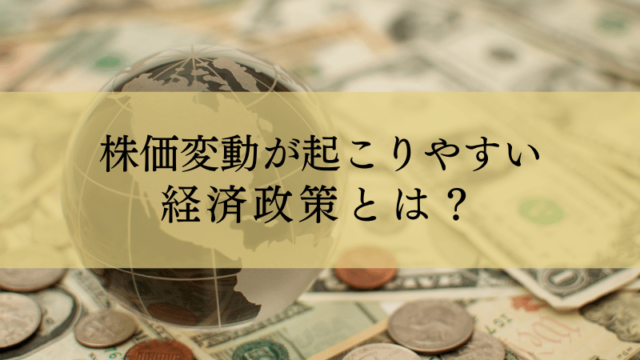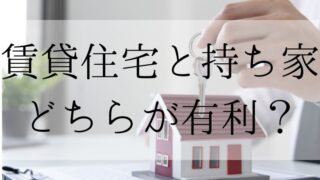「株を買ってみようかな?」そう思って、いざ株価のグラフを見てみると、毎日上がったり下がったりしていて、「どうやって投資先を選べばいいんだろう?」と悩んでいませんか?実は、多くの投資家は、ただグラフの形を見るだけではなく、その会社の「本当の価値」を調べています。それが、ファンダメンタルズ分析と呼ばれる方法です。
ファンダメンタルズ分析とは、会社の成績表や財産状況などを細かくチェックして、その株価が本来の価値より安いのか高いのかを見極めるための手段です。会社のことを深く知ることで、「この会社なら将来きっと伸びる!」と自信を持って投資することができるようになります。
この記事では、そんなファンダメンタルズ分析の基礎の基礎を、ゲームのキャラクターに例えながら、誰でもわかるように解説します。
目次
ファンダメンタルズ分析とは?
企業の本当の価値を見抜くには?
「ファンダメンタルズ分析」と聞くと、なんだか難しそうに感じるかもしれませんね。でも、これは、企業の「健康診断」のようなものだと考えてください。投資家が会社の株を買う時、その会社の価値が本当はいくらなのかを調べるための方法なのです。
株価は日々、上がったり下がったりと変動します。この変動の裏側には、人々の期待や不安、景気の動向など、さまざまな要素が影響しています。
しかし、その株価が、その会社本来の価値と比べて高すぎるのか、あるいは安すぎるのかを見極めるのが、ファンダメンタルズ分析の役割です。この分析によって、一時的な流行や感情に流されず、長期的に成長する可能性のある銘柄をじっくりと見つけ出すことができます。
この考え方の根底には、「株価は、最終的には企業の本質的な価値に収束していく」という考え方があります。たとえば、会社の資産や収益力、将来の成長性などを総合的に評価し、その企業が本来持っている価値を割り出します。
これにより、今買おうとしている株が、お買い得な「割安」な状態なのか、それとも「割高」な状態なのかが判断できるのです。
多くのプロの投資家も、この分析を重視しています。例えば、世界的に有名な投資家であるウォーレン・バフェット氏も、このファンダメンタルズ分析を基礎とした「バリュー投資」(価値のある株に投資する方法)を実践し、大きな成功を収めています。つまり、これはプロも認める、投資の王道と言えるでしょう。

テクニカル分析との違いとは?
投資の世界には、ファンダメンタルズ分析の他に「テクニカル分析」という手法もあります。この二つは、よく比較されますが、そもそも目的がまったく違います。
テクニカル分析は、株価の動きや出来高(取引量)といったデータを重視するに対し、ファンダメンタルズ分析は、株価の動きの理由である会社の「中身」に焦点を当てるためです。
テクニカル分析では、チャート(株価のグラフ)をじっくり見て、過去のパターンやトレンドから、将来の株価の動きを予測しようとします。一方で、ファンダメンタルズ分析は、長期的な視点で投資を考えている人に向いています。
会社の業績や将来性、競争優位性などを深く掘り下げるため、「どの株を買うべきか」という銘柄選定に非常に役立ち、株価が一時的に下がっても、会社の価値に変わりがなければ、自信を持って持ち続けることができます。
要するに、ファンダメンタルズ分析は「どの山に登るべきか」を判断する羅針盤、テクニカル分析は「どのタイミングで一歩を踏み出すか」を判断する地図のようなものです。
どちらか一方だけを信じるのではなく、二つを組み合わせて使うことで、より確実な投資戦略を立てることができます。初心者の方は、まずファンダメンタルズ分析で「良い会社」を見つけることから始めるのがおすすめです。
ファンダメンタルズ分析の3つの手順
ポイント1.財務諸表と経営指標の確認
ファンダメンタルズ分析を始めるとき、まず最初に行うべきことは、企業の「財務諸表」を読み解くことです。財務諸表とは、企業の家計簿のようなもので、会社の財政状態や経営成績を記録した書類です。
- 損益計算書(PL)
会社がどれだけ儲けたか、またどれだけの費用を支払ったかが分かります。
特に、「営業利益」は本業で稼いだ利益、「当期純利益」は最終的に手元に残った利益を示します。 - 貸借対照表(BS)
会社の財産(資産)、借金(負債)、返済不要な自分のお金(純資産)が分かります。
ここから、財務的な健全性を調べることが出来ます。 - キャッシュフロー計算書(CS)
会社にどれだけのお金が入ってきて、出ていったか、その流れが分かります。
特に、「営業キャッシュフロー」がプラスであることは、本業が順調で健全な証拠です。
これらの財務諸表を基に、さまざまな経営指標を計算します。例えば、PER(株価収益率)は、株価が利益の何倍かを示し、株価が割安か割高かの目安になります。一般的にPERが低いほど、割安と判断されます。また、ROE(自己資本利益率)は、株主が出資したお金をどれだけ効率的に使って利益を上げているかを示す重要な指標です。特に日本企業の平均ROEは近年上昇傾向にありますが、10%以上であれば優良と評価されることが多いです。
財務諸表の確認は、難しそうに感じるかもしれませんが、投資の羅針盤となる大切な情報です。
ポイント2.マクロ経済を考慮する
株式投資において、個別の企業分析(ファンダメンタルズ分析)は欠かせません。しかし、どんなに優れた企業でも、その企業を取り巻く国全体の経済状況(マクロ経済)の影響からは逃れられません。マクロ経済は、企業の業績を左右する大きな波のようなものです。
景気は常に「好景気」と「不景気」を繰り返しています。好景気の時には、消費者の購買意欲が高まり、企業の売上や利益は自然と伸びやすくなります。
逆に、不景気になると消費が冷え込み、企業の業績は悪化する傾向にあります。
このため、投資判断を行う際には、内閣府が公表する「景気動向指数」や日本銀行の発表する「日本銀行短観」「金融経済統計」のような重要なマクロ経済指標をチェックすることが不可欠です。
投資先の企業が、現在のマクロ経済環境からどのような影響を受けているのかを把握することで、より多角的な視点からファンダメンタルズ分析を行うことができるのです。
ポイント3.業界の特徴や動向、競争環境にも目を配る
次に、その企業が属する業界の特徴に注目することも非常に重要です。例えば、日本取引所グループの公表する「その他統計資料」を見てみましょう。これを見ると、情報通信業の平均的なROEは14%ほど、銀行業では5%ほどです。それぞれビジネスモデルや収益モデルが違うわけですから、当然です。
つまり、業界によって大きく数字が違い、その数字が業界全体の中でどの位置にあるのかが分からなければ、本当に優れているのか判断できないからです。個別の企業の数字だけを見て「この会社は良さそう!」と判断するのは危険なのです。
例えば、ある企業の売上高営業利益率が5%だとします。一見すると悪くない数字ですが、もし同じ業界の他社が軒並み10%を達成していれば、その会社の収益性は低いと判断できます。
また、業界の動向も重要です。個別の企業が良くても、業界全体のパイが縮小(出版・メディア産業や銀行業などはその事例と言われています。)していれば、将来的には事業の継続や成長は難しくなるかもしれません。
逆に、今後大きく成長すると予想される業界(例えばAIや再生可能エネルギーなど)であれば、業界全体の成長と個々の企業の成長の両方の利益を享受できる可能性があります。
さらに、業界内外での競争環境も確認します。独自の技術やサービスで、他社が簡単に真似できない「参入障壁」を築いている企業は、安定した収益を上げやすいです。特に、強力な知的財産(IP)やブランド力、生産技術力やサプライチェーンなどで他社より有利に立っている場合は、それはその企業の強みだと言えるでしょう。
このように、企業を見る際には、個別の企業の力だけを見るのではなく、業界の特徴や動向、競争環境にも目を配る必要があるのです。
ゲームのキャラクターで学ぶファンダメンタルズ分析
ファンダメンタルズ分析をゲームのキャラクターに例えてみよう
ファンダメンタルズ分析は難しいと思うかもしれませんが、似たようなことは、皆さんが毎日のようにやっているかもしれません。それは、ゲームのキャラクター選択です。
ゲームでキャラクターを選ぶとき、その能力(ステータス)を見て、「このキャラは強いな」「このキャラは防御力があるな」と判断しますよね。また、ゲーム環境に合っているか?同じ役割のキャラクターと比較したらどちらがいいか?など、考えることは無数にあります。
株式投資におけるファンダメンタルズ分析もこれと似ています。会社を「キャラクター」だと思い、その「キャラクター」がどれだけ強いか、安定しているかを判断するのが、ファンダメンタルズ分析の第一歩なのです。
財務諸表はキャラクターの能力値
ファンダメンタルズ分析は、企業の「キャラクター」の能力値を評価するようなものです。
企業の活動を記録した財務諸表は、そのキャラクターの攻撃力や防御力といった様々なパラメーターが記されたシートだと思ってください。
損益計算書は主に「攻撃力」に関する数字が多く、貸借対照表は「防御力」に関する数字が多く書かれています。
たとえば、売上高は、そのキャラクターが出せる攻撃力の最大値だと考えられます。そして、営業利益や経常利益は、実際に敵に与えることができるダメージに当たります。このダメージ量が高ければ高いほど、その企業は相手を倒せる可能性が高まります。
一方で、会社の財政状態を示す貸借対照表は、キャラクターの防御力です。特に、自己資本比率は、キャラクターのHP(体力)のようなものです。この数値が高いほど、借金が少なく、倒産しにくい安定した企業だと言えます。
しかし、たとえHPが高くても、攻撃をよけられなかったり、回復が間に合わなければ簡単に倒されてしまうかもしれません。これが、いわゆる黒字倒産(利益は出ているのに資金が回らなくなること)という状態です。
だからこそ、会社のHPが簡単に尽きないかどうかを判断するために、流動比率や当座比率といった指標も確認することが大切です。これらの指標は、攻撃を回避する能力や、HPの回復力に例えることができます。
HPが高く、攻撃をかわす能力や回復能力が高ければ、簡単に競争相手に倒されることはありません。
キャラクターの特殊アビリティにも注目
ゲームの世界には、能力値だけでは測れない「特殊なアビリティ」や「スキル」によって、数値以上の力を発揮するキャラクターがいます。ゲームではこのような、他のキャラクターとは違う個性が重要になることも多いです。
そして、これは、会社でも同じです。会社の特殊性や独自の技術、他社に負けない能力といった数字だけでは見えない「企業独自の強み」がある会社なら、長期的に成長を続けたり、安定的な経営が望めるでしょう。このような企業独自の強みを見つけることもまた、ファンダメンタルズ分析の醍醐味の一つなのです。
いわゆる「定性的な情報」と言われるもので、例えば以下のようなものが挙げられます。
- ブランド力:顧客からの信頼が厚いか?
- 技術力:他社にはない特許や独自技術を持っているか?
- ニッチ市場での優位性:特定の分野や市場で大きなシェアを占めているか?
これらの強みは、会社の将来的な成長を左右する重要な要素です。
例えば、自動車会社のスズキは、「小・少・軽・短・美」という独自の哲学に基づき、特に軽自動車と小型車に強みを持っています。コストを抑え、燃費が良く、維持費が安いクルマづくりを追求しています。その結果、スズキのインド子会社「マルチ・スズキ・インディア社」は、インド市場で約40%という驚異的なシェアを誇ります。インド市場という巨大な市場で圧倒的な優位性を築く基盤となりました。
また、日野自動車の最大の独自性は、商用車(トラック・バス)に特化している点にあります。この専門性から、日野自動車の2025年5月時点の登録車数では、25.0%のシェアを占めており、国内のトラックメーカーの中でトップに立っています。さらに、過去には1973年度から49年連続で国内大・中型トラックの販売シェアでNo.1を達成しており、長年にわたり業界をリードし続けてきました。
このように、会社の売上や利益、財務体質と言った能力だけではなく、「その会社の特殊性や優位性」を考慮して企業を選ぶのも、ファンダメンタルズ分析の大事な視点なのです。
ゲーム環境に合っているか?
キャラクターの能力値が高く、特殊アビリティが強いとしても、戦うステージの環境や、戦う相手の特殊アビリティに対抗できないのであれば活躍できません。
環境に合っているキャラクターや特定の強いキャラクターを止めるために採用されるキャラクターのことを「メタ」と呼ぶことがありますが、メタゲームで不利だと、実際にゲームをプレイしても、苦戦を強いられることが多いのです。
これは、ファンダメンタルズ分析でも同様のことが言えます。
企業のファンダメンタルズ分析をする際には、マクロ経済や業界の動向を分析し、その会社が「最大限に活躍できる環境にあるか」を見極めることが重要な視点です。競業他社が「メタ」を出してきているなら、その進展を注意深く見守る必要もあるでしょう。中には、新しい分野を開拓し、新たな競争環境を作り出す企業もあります。
成長し続ける企業と言うのは、現在の市場や経済状況という「ゲーム環境」に適応できているかどうかが大切です。
さらに言えば、未来に「ゲーム環境が大きく変わる」可能性がある場合、その変化に適応できるであろう企業を選ぶことが成功のカギとなるのです。