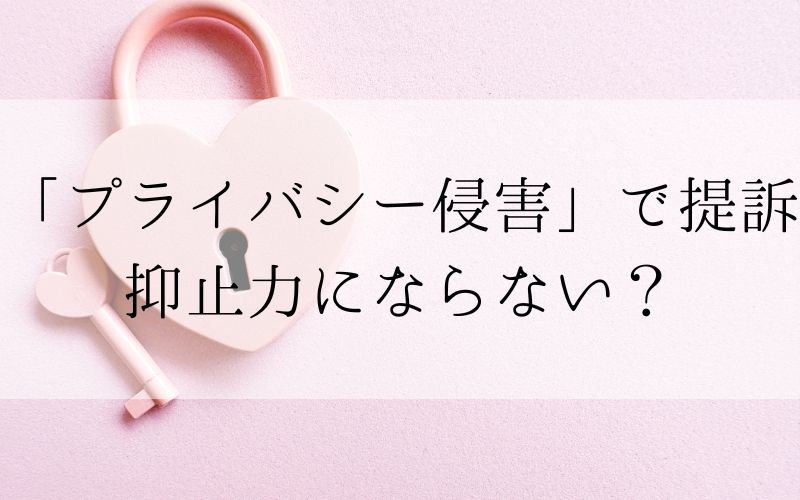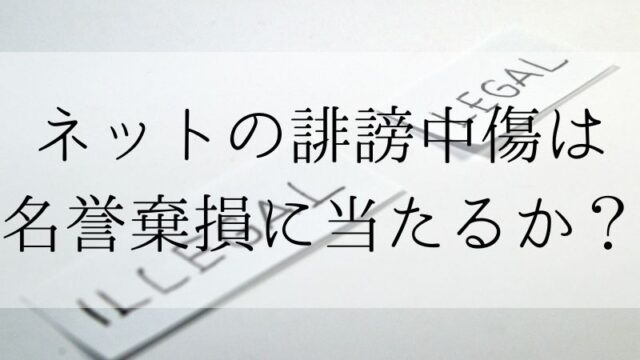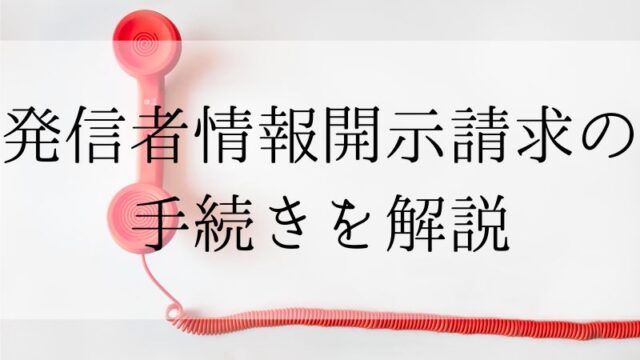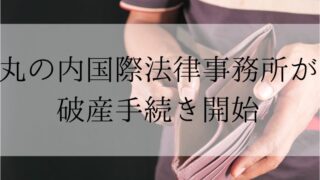編集者・箕輪厚介氏が、自身に関する不倫報道をめぐって、報道元を「プライバシー侵害」で提訴する意向を示しました。事実無根かどうかにかかわらず、私生活を無断で報じられることの違法性を問う、ある種の“正攻法”とも言えます。
箕輪厚介氏、不倫疑惑報道の出版元を提訴の意向示す「名誉毀損じゃなくて…」弁護士事務所と相談(日刊スポーツ)
しかし、実は日本の法律の仕組みでは、このような訴訟(裁判で訴えること)は、週刊誌の報道を止める力があまりないどころか、出版社の利益をさらに増やしてしまう可能性すらあるのです。驚きですよね?
この記事では、「名誉毀損」と「プライバシー侵害」という二つの言葉の違いを分かりやすく説明しながら、なぜ提訴しても週刊誌の報道が止まらないのか、そして、そこにある日本の社会が抱える「構造的な問題」について、具体的な例を交えながら深掘りしていきます。
目次
箕輪厚介氏が「プライバシー侵害」で提訴の意味とは?
名誉毀損じゃない? 「プライバシー侵害」とは
今回、箕輪さんがご自身のSNSで「名誉毀損ではなく、プライバシー侵害で訴える」とハッキリとおっしゃいました。これは、とても重要なポイントです。
そもそも、名誉毀損(めいよきそん)というのは、「事実ではない情報や、人の社会的評価を下げるような情報が広められたことで、その人の名誉が傷つけられること」を指します。もし「記事の内容がウソだ!」と訴えるなら、名誉毀損になります。しかし、箕輪さんはそうではありません。
一方、プライバシー侵害(プライバシーしんがい)は、「個人の私生活に関する情報が、本人の許可なく勝手に公開されてしまうこと」です。これは、「記事に書かれたことが真実かどうか」には関係ありません。たとえそれが事実であったとしても、個人のプライバシーは守られるべきだという考え方です。
つまり、箕輪さんの提訴は、「記事の内容が本当だろうがウソだろうが関係ない。そもそも、私の私生活を勝手に暴いて報道したこと自体が違法だ!」という主張なのです。これは、日本の民法(私たちの日常生活に関わる基本的な法律)で定められている「プライバシーの権利」という、人として当然に持っている権利を守るための行動だと言えます。
しかし、この「法律的な正しさ」と「実際に効果があるかどうか」は、残念ながら全く別の問題として存在しています。
アンジャッシュ渡部さんの「3億円ジョーク」が暴く、週刊誌ビジネスの現実
週刊誌の報道がなぜ止まらないのか、その厳しい現実を分かりやすく教えてくれるのが、過去に不倫報道があったお笑い芸人のアンジャッシュ渡部建さんのエピソードです。渡部さんは、「(週刊)文春に“記事を出さないでくれ”と300万円提示したけど、通らなかった。だって記事にすれば3億円売れるんだもん、そりゃ出すわな(笑)」と自虐的に語ったことがあります。
この話は、報道される側が受ける「損害」よりも、週刊誌の出版社が得る「利益」の方が圧倒的に大きいという現実を、とても分かりやすく示しています。
想像してみてください。もし裁判で報道された側が勝ったとしても、出版社にとっての損害は、本当にごくわずかなものなのです。実は、プライバシー侵害で認められる慰謝料(精神的な苦痛に対する賠償金)の相場は、せいぜい数十万円から100万円台がほとんどです。
特別な事情がない限り、これ以上の高額な賠償が認められることは、日本では基本的にありません。なぜなら、日本の法律では、損害賠償は「実際に受けた損害を補うこと」が目的であり、「罰を与えること」が目的ではないからです。つまり、精神的な苦痛に対する賠償には限界があり、週刊誌の売上など、彼らの事業全体に与える影響はほぼゼロに等しいのです。
その一方で、週刊誌の「スクープ報道」が成功すれば、以下のような莫大な利益が生み出されます。
| 利益の種類 | 概要 | 期待される金額 |
|---|---|---|
| 雑誌部数の増加 | 話題の記事が載ることで雑誌がたくさん売れる | 数千万円単位 |
| ネット記事での広告収入 | ウェブサイトのアクセスが増え、広告表示による収入が増える | 数千万円単位 |
| ワイドショー等での2次的な収益波及 | テレビや他のメディアで報道が取り上げられ、さらに話題になる | 数億円規模に達することも |
このように、週刊誌にとっては、「このスクープを報道しない」という選択肢を選ぶ方が、はるかに経済的な損失が大きくなってしまうのです。この構造が、彼らが次々と報道を続ける大きな理由だと断言できます。
日本と海外の大きな違い:懲罰的損害賠償がない現実
実は、アメリカなどの国では、悪質な違法行為に対して「懲罰的損害賠償」(ちょうばつてきそんがいばいしょう)という特別な制度が認められています。これは、加害者に対して、実際に与えた損害をはるかに超える金額の賠償を命じることで、「こんな悪いことをしたら、とんでもない罰が待っているぞ!」と警告し、同じようなことを二度とさせないようにする「制裁」の意味合いが強い賠償金です。
これにより、加害者には数千万円から数億円という莫大な賠償金が課されることも珍しくありません。だからこそ、アメリカの報道機関は、いい加減な情報やプライバシー侵害に当たるような報道をする際に、非常に慎重にならざるを得ないのです。もし訴えられたら、会社が潰れてしまうほどのダメージを受ける可能性があるからです。
しかし、残念ながら日本では、このような懲罰的損害賠償の制度は認められていません。日本の損害賠償は、あくまで「実際に受けた損害を埋め合わせる」ことだけが目的です。
たとえ週刊誌が悪質な報道をしたとしても、法的に「本当に怖い」と思わせるような高額な賠償金を請求することはできないのです。これが、日本の週刊誌が大胆な報道を続けられる、もう一つの大きな理由と言えるでしょう。
訴訟が“燃料”になる皮肉:報道をさらに広げてしまう可能性
さらに皮肉なことに、訴訟を起こすこと自体が、週刊誌の報道をさらに広げてしまう「燃料」になってしまうという問題も存在します。これは、提訴した側にとっては、まさに“悪夢”のような話かもしれません。
考えてみてください。もし有名人が週刊誌を訴えたとしたら、以下のようなことが起こる可能性が高いです。
- SNSでの拡散: 「あの有名人が週刊誌を訴えたらしい!」と、瞬く間にSNSで話題になり、多くの人々に情報が届きます。
- メディアの「続報」: ワイドショーやネットニュースは、「有名人、週刊誌を提訴」というニュースを「続報」としてさらに大きく取り上げます。これにより、元々の報道の内容を知らなかった人まで、その情報を知ることになります。
- 信ぴょう性の認識: 訴訟を起こされた側(週刊誌)は、「訴えられるなんて、何かよほど本当のことが書かれていたのでは?」と読者に思わせてしまい、かえって記事の「信ぴょう性が高い」と認識されることすらあります。
こうなると、せっかく提訴したにもかかわらず、それが結果的に出版社にとっての「宣伝効果」となり、新たな収益を生む“追い風”になってしまうという、矛盾した状況が生まれてしまうのです。
これは、個人のプライバシーを守ろうとする行動が、かえってそれを侵害する側のビジネスを助長してしまうという、なんともやるせない現実を突きつけています。
まとめ:提訴は正義の行動、でも報道の抑止にはならない現実
ここまで見てきたように、箕輪厚介さんがプライバシー侵害で提訴することは、法的な意味では「私のプライバシーを侵害された!」という正義の主張であり、大切な権利を守るための行動です。
しかし、残念ながら、週刊誌の報道を「止める」という点においては、今の日本の法制度では十分な効果が期待できません。むしろ、提訴そのものが、出版社の話題づくりや収益拡大に利用されてしまうという、皮肉なリスクがあります。
箕輪さんの提訴は、日本のメディアと個人の権利のあり方を改めて考えさせる、非常に重要な一歩です。
しかし、現在の週刊誌報道のビジネスモデルに“制裁”を加えるには、日本の法律はまだ力不足だと言わざるを得ません。
この構造的な問題が解決されない限り、週刊誌報道を完全に止めるのは難しいでしょう。私たちは、この現実をしっかりと理解し、メディアから発信される情報とどう向き合うかを考える必要があるのです。