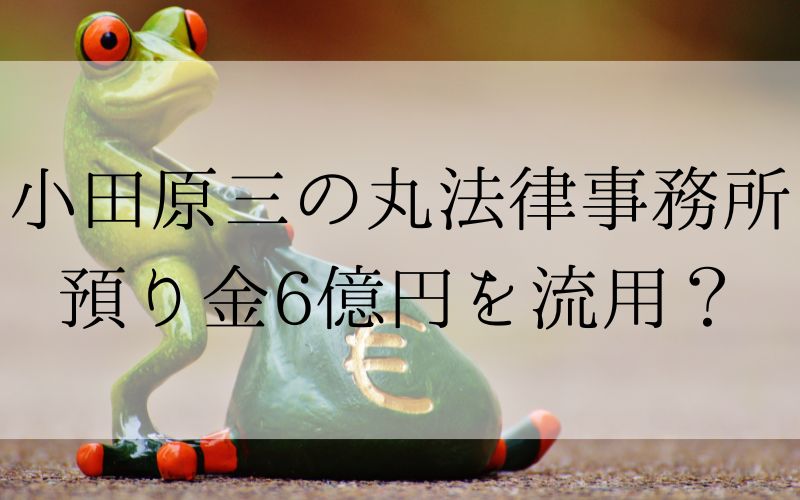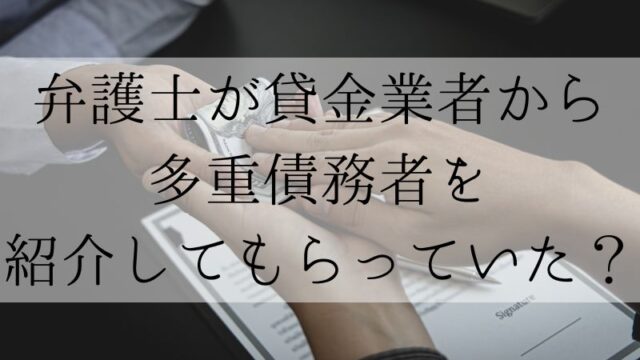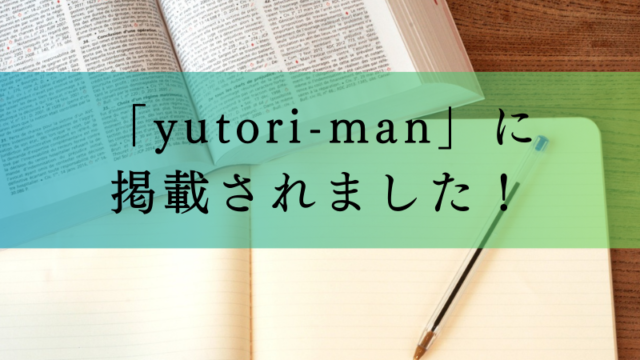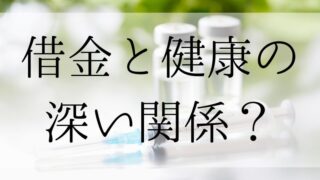弁護士法人小田原三の丸法律事務所が起こした、依頼者からの預かり金約6億円の不正流用疑惑のニュースに、あなたは大きな衝撃を受けていることでしょう。弁護士は、皆さんの大切な財産を預かり、守るべき専門家です。その弁護士による裏切り行為は、私たち市民の信頼を根底から揺るがす、許しがたい出来事だと言えます。
「預けたお金は一体どうなってしまうのか?」「この弁護士と事務所はどうなるのか?」といった疑問や不安で胸がいっぱいになっている方も多いのではないでしょうか。この問題の解決には、依頼者の方々が正確な情報を理解し、適切な行動を取ることが絶対に必要です。
そこで、この記事では、公的機関の発表や信頼できる報道に基づき、事件の具体的な詳細と、預けたお金を取り戻すための今後の法的な道筋について、わかりやすく解説します。
目次
弁護士による巨額流用事件とは?
衝撃の事実:6億円流用の詳細
皆さんは、弁護士に大切なお金を預ける際、「まさか自分の財産が勝手に使われるなんて」とは想像もしないでしょう。しかし、神奈川県でこの信じがたい事態が発生しました。
それは、弁護士法人小田原三の丸法律事務所(神奈川県小田原市)の代表である竹久保好勝弁護士が起こした、約6億円にのぼる依頼者からの預かり金不正流用疑惑です。
この流用は、竹久保弁護士の指示で、、遺産分割や遺言執行などを受任した際に依頼者から受け取った代金(預り金)を、「預かり金口座」から弁護士報酬を管理する「報酬口座」に資金を移していたというものです。
神奈川県弁護士会が公開した情報によると、事務所の会計で「顧客預り金」とされていた金額に対して、実際の銀行口座の残高が大幅に不足していたことが確認されています。この不足こそが流用の明白な証拠だと断定されています。
報道によれば、流用が明らかになった時点で、約6億円の預かり金に対し、口座の残高は約4300万円しか残っていませんでした。実に9割以上が消えていた計算になります(出典:読売新聞「弁護士が依頼人からの「預かり金」6億円流用、懲戒手続き開始…口座の残金は4300万円」 朝日新聞「法律事務所が預かり金約6億円を流用か 神奈川県弁護士会が調査」)。
このような巨額の流用は、依頼者の人生設計を根底から揺るがす重大な裏切り行為に他なりません。弁護士会もこの事態を重く見て、すぐさま懲戒手続きの調査開始を決定しました。
| 資金の状況(2025年10月8日時点) | 金額 |
| 流用が疑われる預かり金総額 | 約6億円 |
| 弁護士口座の残金(報道) | 約4300万円 |
| 不足・流用された可能性のある額 | 約5億5700万円 |
なぜ起きた?弁護士の義務違反
では、このような巨額の不正流用は、具体的にどのような手口で、なぜ発生したのでしょうか。これは単なる個人のミスではなく、弁護士に課された最も基本的なルールが破られた結果です。
まず、竹久保弁護士は、依頼者からの預かり金を自分の事務所の「報酬口座」へと恒常的に移動させていました。この資金移動は、直近の3年間で毎月、数百万円から2000万円という規模で繰り返されていたと、弁護士会の調査で判明しています。
そして、この報酬口座へ移されたお金は、事務所の家賃や人件費などの経費に使われていました。つまり、依頼者の大切なお金を自分の事務所の運営資金に勝手に充てていたのです。
弁護士職務基本規程第38条では、「依頼者から預かった金銭を自分の金銭と区別して管理しなければならない」と定めていますが、本件事件はこの規定に明確に違反していると言えるでしょう。(出典:神奈川県弁護士会 情報提供Q&A)。
今回の事態は、弁護士としての倫理観の欠如と、預かり金管理のルールを意図的に無視した結果です。この行為は、弁護士の社会的な信用を失墜させる極めて重大な非違行為であると断定されています。
弁護士法人小田原三の丸法律事務所 および 竹久保好勝弁護士 基本情報
この巨額の預かり金流用事件の中心人物は、竹久保好勝弁護士と、彼が代表を務める弁護士法人小田原三の丸法律事務所です。読者の皆さんの不安を解消するため、当事者の情報を正確に把握することが大切です。
| 項目 | 弁護士法人小田原三の丸法律事務所 | 竹久保 好勝 弁護士 |
| 会員種別 | 弁護士法人会員 | 弁護士会員 |
| 正式名称 | 弁護士法人小田原三の丸法律事務所 | 竹久保 好勝(たけくぼ よしかつ) |
| 届出番号/登録番号 | H-554 | 13591 |
| 事務所所在地 | 〒250-0012 神奈川県小田原市本町1-7-20三の丸ビル | 〒250-0012 神奈川県小田原市本町1-7-20三の丸ビル 弁護士法人小田原三の丸法律事務所内 |
| 電話番号 | 0465-24-3358 | 0465-24-3358 |
| FAX番号 | 0465-24-3347 | 0465-24-3347 |
この事件は、竹久保弁護士が代表者という立場を利用し、法人の会計管理を掌握していたことから起きました。したがって、弁護士法人そのものにも、管理体制の不備という点で大きな責任があります。
事務所の現状と弁護士会の緊急対応
事件が公になった後、問題の弁護士事務所や弁護士会は、具体的にどのような対応を取っているのでしょうか。特に、依頼者の方々が取るべき行動に直結する弁護士会の緊急対応は、非常に重要です。
まず、竹久保弁護士は、預かり金について一部の依頼者から返還を求められていますが、現在の事務所の財政状況から「返還できない可能性が高い」とされています。このため、依頼者の方々は、自力で資金を取り戻すことが困難な状況に置かれています。
これに対し、神奈川県弁護士会は迅速な対応を取りました。令和7年10月7日に懲戒の相当性を調査する綱紀委員会の調査開始を決定し、翌8日に公表しました(出典:神奈川県弁護士会 情報提供Q&A)。
さらに、最も注目すべきは、依頼者の方々の不安解消と被害拡大の防止を目的とした「臨時相談窓口」の設置です。(神奈川県弁護士会「弁護士法人小田原三の丸法律事務所及び竹久保好勝弁護士臨時相談窓口開設のお知らせ」)
| 臨時相談窓口の概要 | 詳細 |
| 設置期間 | 2025年10月9日~10月23日(土日除く) |
| 対応内容 | 被害状況の把握、今後の法的アドバイス、新たな弁護士への引継ぎに関する助言など |
| 相談方法 | 電話(045-225-9254)または専用のウェブ受付フォーム |
この窓口は、対象弁護士とは全く関係のない外部の弁護士が担当します。このため、被害に遭われた方は、ためらわずにこの窓口を利用し、状況を共有することが、預かり金回収への第一歩になります。
預かり金は戻るのか?今後の展開を予測
預かり金返還の可能性と課題
最も気になる点は、「流用された預かり金は、本当に依頼者の元へ戻ってくるのか?」という問題でしょう。結論から言えば、資金を取り戻すための道筋はありますが、多くの課題が残るというのが現実です。
弁護士会は、現時点で預かり金の返還時期や金額を確約できないと正直に公表しています(出典:神奈川県弁護士会 情報提供Q&A)。これは、流用されたお金の多くが事務所経費として使われ、残高が大幅に不足しているためです。
しかし、依頼者にはお金を取り戻すための二つの重要な選択肢があります。
まず、竹久保弁護士個人と弁護士法人に対し、預けたお金の返還を求める訴訟などの法的手続きを起こすことができます。この手続きにより、竹久保弁護士個人の財産や、法人に残された僅かな財産を差し押さえることが可能になります。
次に、「依頼者見舞金制度」の利用です。依頼者見舞金制度は弁護士、弁護士法人または弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務に伴い、弁護士が預かり保管していた依頼者の金員を横領する事件が発生した場合、その被害を受けた依頼者の方に対し、所定の手続を経て、日本弁護士連合会からお見舞い金を支給するものです。(日本弁護士連合会「依頼者見舞金制度について」)
いずれにせよ、被害に遭われた方は、弁護士会の臨時相談窓口を通じて、速やかに新たな弁護士に依頼することが不可欠です。時間経過とともに、回収できる可能性は低下してしまいます。
重要な注意点として、預かり金の回収と、もともと依頼していた事件(遺産分割など)の解決は別々の問題として進める必要があります。
懲戒処分と破産手続きの行方
この事件は、最終的に弁護士個人と法人にどのような法的結末をもたらすのでしょうか。主に「懲戒処分」と「破産手続き」の二つの側面から解説します。
まず、懲戒処分については、すでに神奈川県弁護士会の綱紀委員会で調査が始まりました。預かり金の流用という行為は、弁護士の信用を失墜させる極めて重大な違反です。そのため、竹久保弁護士には、以下のうち最も重い処分が下される可能性が高いと予測されます。
- 業務停止
- 退会命令(弁護士の資格を一時的に失う)
- 除名(弁護士の資格を永久に失う)
懲戒処分が下されるまでには、数か月程度の期間を要しますが、弁護士会は厳正な審査を行うと断言しています。
次に、破産手続きの可能性です。報道等によると、弁護士法人の口座には約4300万円しか残っておらず、約6億円の負債に対して圧倒的な債務超過の状態にあります。この状況が続けば、弁護士および弁護士法人は破産手続きに移行する可能性が極めて高いです。
法人破産となった場合、残された財産は、裁判所が選任した破産管財人によって公正に管理され、依頼者などの債権者に分配されることになります。この場合も、分配される金額は元金の全額には満たない可能性が高く、全額の返済が求められるかどうかは不透明です。
ですから、依頼者の方々は、懲戒手続きの動向と法人の破産手続きの有無の両方に注意を払い、今後の対応を検討する必要があります。