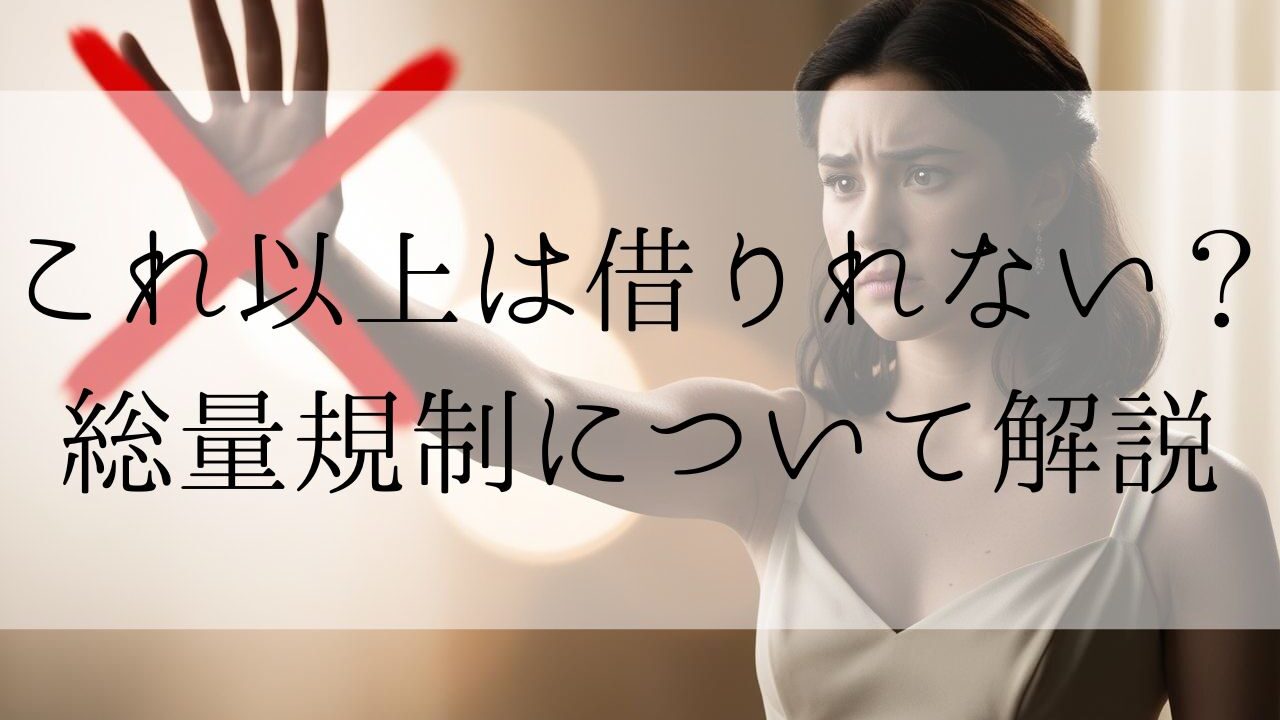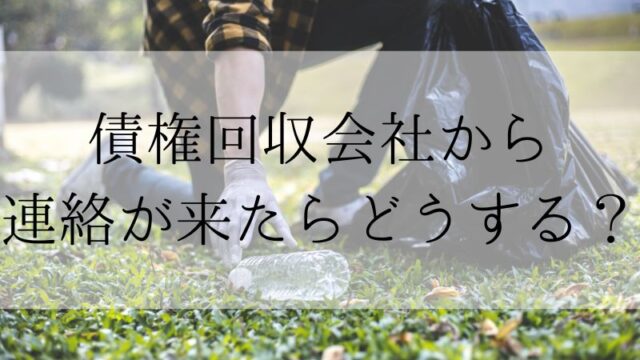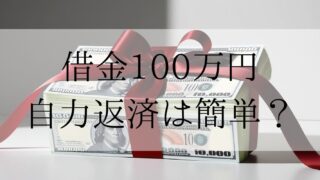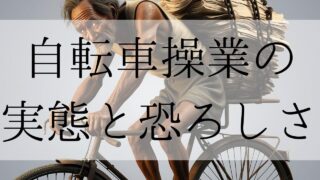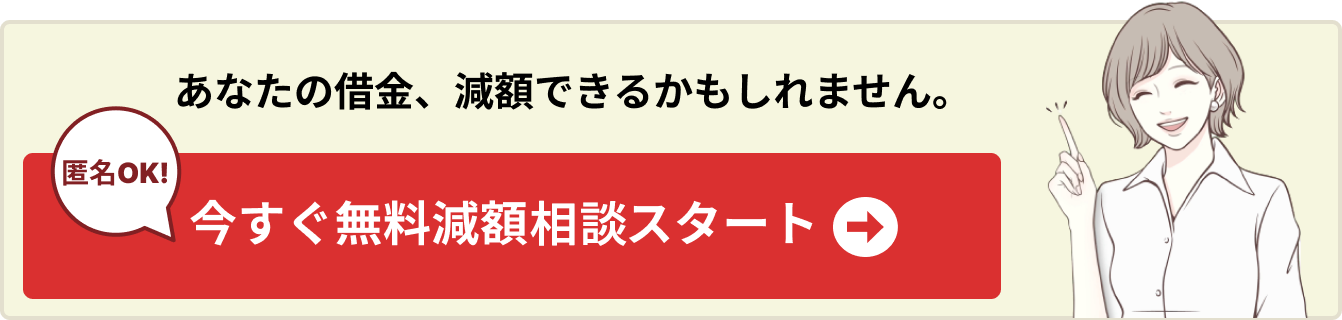お金を借りすぎてしまい、返済が困難になるケースは決して珍しくありません。
そのため、法律では個人が借りられる金額の上限を定めるルールが存在します。それが「総量規制」です。
総量規制は、年収の3分の1を超える借入れを防ぐことで、多重債務に陥るリスクを減らすことを目的としています。しかし、この規制には例外もあり、すべての借入れが制限されるわけではありません。
本記事では、総量規制の仕組みや適用範囲、例外について詳しく解説します。
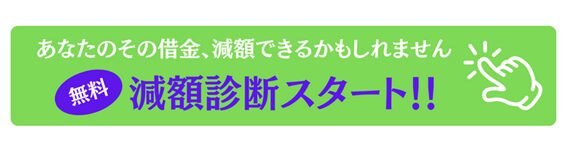
目次
総量規制とはどんなもの?なぜ導入されたの?
総量規制とは、貸金業者からの個人の借入総額を、その人の年収の3分の1までに制限する規制です。これは、消費者が過度な借入れによって多重債務に陥ることを防ぐために設けられている、貸金業者が守らないとならないルールです。
例えば、年収が300万円の方であれば、借入の最大金額は100万円です。また、年収100万円であれば借り入れの最大額は33万円となります。
総量規制とは
総量規制は、貸金業法の改正によって2006年12月に導入されました。具体的には、貸金業法第13条の2第1項では「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、(中略)顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。」と定められています。
また、第二項では「個人過剰貸付契約」とは、貸付額が「その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に三分の一を乗じて得た額」を超えることとなるものと定義されています。(参照:貸金業法第13条の2「過剰貸付け等の禁止」)
つまり、個人の収入の3分の1を超える貸付は返済能力を超える過剰融資であるとして、これを認めないという制度が総量規制であるということです。
総量規制の背景
このような総量規制の背景には、かつて、多重債務者が多数発生したことが背景にあります。
かつては、貸金業者は利息制限法で定められた上限金利(20%)を超える高金利で貸付を行っていました。さらに、消費者の返済能力を十分にチェックせずに、過剰な貸付をしていたケースが多かったのです。そのため、借りたお金の残高がどんどん膨らみ、返済がますます厳しくなるという悪循環が生まれました。
これにより、返済能力を超えた借入れをする人々が多くなり、「多重債務者」と呼ばれる人々が急増したのです。
このような人たちは、複数の貸金業者から借入れを重ね、返済が追いつかずに自己破産や夜逃げをするなど、深刻な問題が社会で広がりました。この問題は、単なる個人の問題にとどまらず、社会全体に大きな影響を及ぼしました。
特に、自己破産の件数は2003年に24万2357件(個人による申し立てのみ)となるなど、過去最高を記録しています。(金融庁HPより)
このような状況を受けて、2006年に貸金業法が改正され、2010年に完全施行されました。改正された貸金業法では、消費者を過剰な借入れから守るため、総量規制が導入されました。
この規制により、消費者が借りることができる金額の上限が設定され、返済能力を超える借入れが制限されるようになりました。さらに、上限金利の引き下げや貸付時の審査強化なども行われ、消費者が無理なく借り入れを行える環境が整備されました。
これにより、近年では自己破産の件数も大きく減少し、現在では6~7万件程度と大幅に減少しています。(令和4年司法統計年報概要版)
このように、総量規制は、多重債務の根本的な解決を目指すものとして、非常に重要な意味を持っているといっても過言ではないでしょう。
総量規制の具体例
貸金業者からの借入金額は年収の3分の1までになる
貸金業者からの借入れは、法律によって年収の3分の1までと定められています。これは、借りすぎを防ぎ、返済不能に陥るリスクを減らすためのルールです。
例えば、年収が300万円の人は、貸金業者からの借入総額が100万円を超えてはいけません。
これは、1社だけでなく、複数の貸金業者からの借入れを合計した金額にも適用されます。
つまり、すべての貸金業者からの借入れ総額が年収の3分の1を超えないように制限される仕組みになっています。(日本貸金業協会「1 お借入れは年収の3分の1までです」)
なぜ総量規制は年収の3分の1を基準にするの?
なぜ総量規制は年収の3分の1を基準にするのかについては、各世帯の毎月の平均貯蓄額を考えるとわかりやすくなるかもしれません。
「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和3年)年間手取り収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合」によると、毎月の平均貯蓄額は、10~15%未満の14.0%、35%以上の13.6%となっています。平均貯蓄率は14%であることがわかります。一方で、貯蓄しなかった世帯が最も高い割合は38.1%あることから、現実的な毎月貯蓄額はもう少し低いかもしれません。
| 総数(金融資産保有世帯) | 5%未満 | 5~10%未満 | 10~15%未満 | 15~20%未満 | 20~25%未満 | 25~30%未満 | 30~35%未満 | 35%以上 | 貯蓄しなかった | 無回答 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1,669) | 5.5% | 9.8% | 14.0% | 3.1% | 8.4% | 1.6% | 5.9% | 13.6% | 38.1% | 0.0% | 14% |
| (91) | (163) | (234) | (51) | (141) | (27) | (99) | (227) | (636) | (0) |
つまり、多くの方は手取り月収の15%程度が、生活に悪影響を及ぼさないで貯蓄に回せる余剰金の額であり、それ以上の捻出をするのは非常に難しいというのが現実だということです。
貯蓄額を基準に返済額を考えると、以下の通りになります。
年収が300万円、借金額が年収の3分の1で100万円の方がいたとします。大手の消費者金融等では、この場合の最低返済額を借入額の2~3%程度に設定をしていることが多く、左記の例では20,000~30,000円となります。(参照:プロミス「ご返済金額」アイフル「ご返済一覧表」)
そして、年収300万円の方の手取り月収はおよそ20万円程度になることが多く、生活に悪影響を及ぼさない程度で捻出できる余剰金の金額が15%とすると、30000円程度になります。
最低返済額をもう少しで越えそうな金額であり、借金額が大きくなれば余剰金の捻出が難しくなりそうです。
以上の通り、最低返済額と貯蓄可能額を考慮すると、年収の3分の1(総量規制)を越える借金の返済が難しいということはご理解いただけると思います。にもかかわらず、これを越える状態を放置すれば、多重債務状態を招くリスクもあるでしょう。
そのため、総量規制は年収の3分の1を基準としていると考えられます。
総量規制の例外とは?
ただし、すべての借入れが総量規制の対象となるわけではありません。
この法律は貸金業者に適用されるものであり、それ以外の金融機関からの借入れには適用されません(貸金業法第3条参照)。
例えば、住宅ローンや自動車ローンは総量規制の対象外です。これらは生活に必要な資金として扱われるため、規制の枠外となっています。
また、銀行からの借入れも貸金業法の規制を受けないため、総量規制の対象には含まれません。
一方で、クレジットカードのキャッシングは総量規制の対象となります。これは、貸金業者が提供するサービスの一種とみなされるためです。しかし、クレジットカードのショッピング枠での分割払いやリボ払い、銀行からの借入れは規制の対象外となります。(参照:金融庁「貸金業法のキホン」)
まとめ
総量規制とは貸し過ぎを防ぐためのもの
総量規制とは、個人の借入総額を年収の3分の1までに制限する制度です。この制度の目的は、消費者が借りすぎによって多重債務に陥ることを防ぐことにあります。貸金業者は、この基準を超えた貸付を行うことが禁止されています。
例えば、年収300万円の人であれば、貸金業者からの借入総額は100万円までに制限されます。この規制は、1社からの借入れだけでなく、複数の貸金業者からの借入れ合計にも適用されます。そのため、消費者が過剰な借入れをしないように管理されているのです。
この制度の導入背景には、かつての多重債務問題があります。総量規制が施行される前は、貸金業者が消費者の返済能力を十分に審査せず、高金利で貸付を行っていたため、自己破産する人が急増しました。そこで、2010年の貸金業法改正により総量規制が導入され、消費者を借りすぎから守る仕組みが整えられました。
総量規制を越えそうなときは専門家に相談を
総量規制によって借入れの上限が定められていますが、生活費や急な出費などで借入れが膨らみ、年収の3分の1を超えてしまうケースもあります。特に、複数の業者から借入れをしている場合は、気づかないうちに総量規制を超えてしまうことがあります。
もし、借入額が年収の3分の1に近づいている、またはすでに超えてしまった場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。弁護士や司法書士などの専門家に相談すれば、債務整理の方法を提案してもらうことができます。
放置してしまうと、利息が膨らみ返済がさらに困難になる可能性があります。早めに対策を講じることで、生活への影響を最小限に抑えることができるでしょう。借金の管理が難しくなったと感じたら、迷わず専門家のサポートを受けることが重要です。