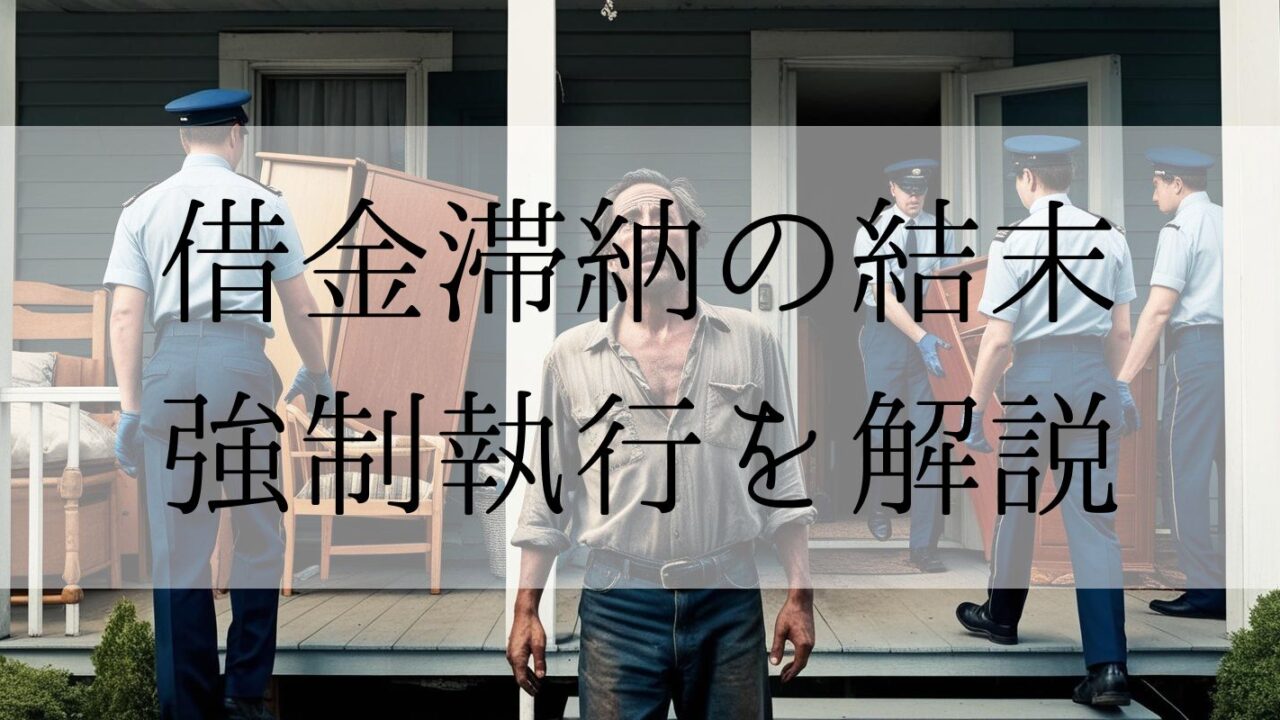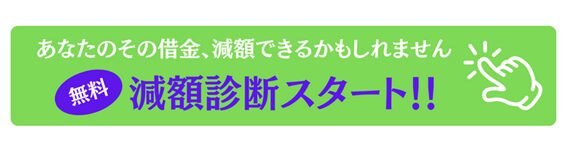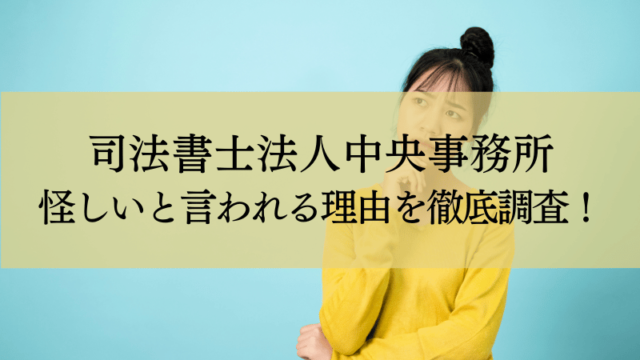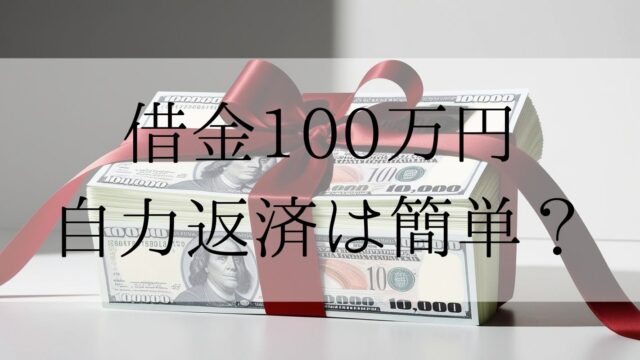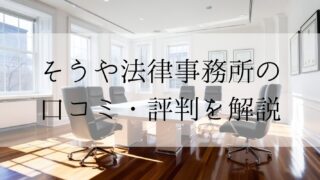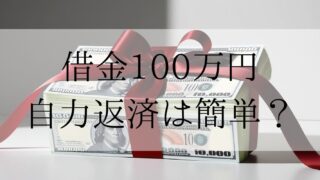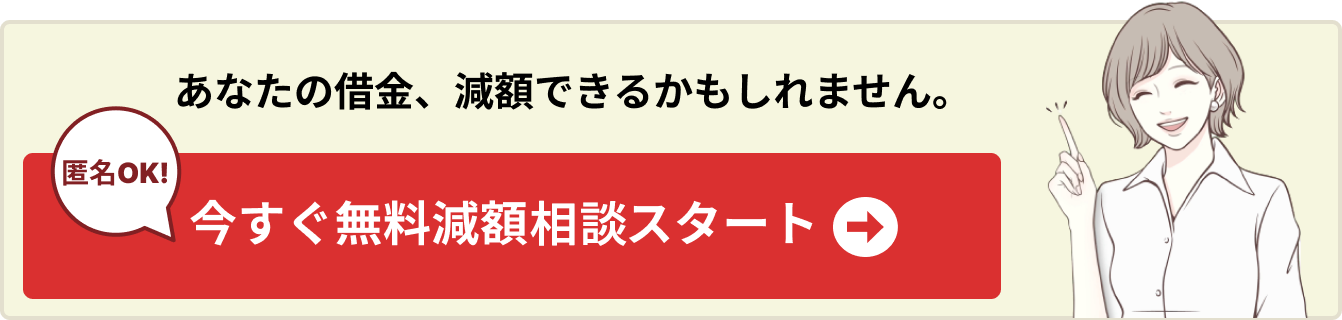借金の返済が滞ると、債権者から強制執行を受けるリスクがあります。
強制執行とは、裁判所の手続きを通じて、債務者の財産を強制的に差し押さえ、債権回収を図る手段です。不動産、給与、預金、動産など、様々な財産が差押えの対象となり、債務者の生活に大きな影響を及ぼします。
もし強制執行の危機に直面したら、どのように対応すべきでしょうか?弁護士や司法書士などの専門家に相談することが、解決への第一歩となります。早期の対応こそが、強制執行による不利益を最小限に抑え、債務者の生活再建につながるのです。
本記事では、強制執行の概要と対策法について詳しく解説します。強制執行の種類や手続きの流れ、差押えを避けるための方法など、債務者が知っておくべき重要なポイントを押さえておきましょう。
なお、本記事は裁判所HPの「民事執行手続」などを参照して作成しています。
民事執行手続きとは
民事執行手続きとは、お金を貸した人(債権者)が裁判所を通じて、お金を返さない人(債務者)の財産を差し押さえ、お金に換えて回収を図る手続きのことです。
借りたお金を返済できない場合、債権者から裁判所に申立てがあると、差押え、換価、配当などの手順を経て強制的に債権回収が行われます。
これにより、知らないうちに財産を失うリスクもあるため、借金の返済が滞っている方は早めの相談が大切です。

民事執行手続きは大きく分けて2種類ある
民事執行手続きには、大きく分けて「強制執行手続」と「担保権の実行手続」の2つの種類があります。これら強制執行、担保権の実行としての競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、民事執行法に定めがあります。
強制執行手続は、勝訴判決や和解調書などの債務名義がある場合に、債権者の申立てにより裁判所が強制的に債務の履行を実現する手続きです。(参照:民事執行法第22条)
一方、担保権の実行手続は、抵当権など債務者の財産に対する担保権を持つ債権者が、その権利を実行して債権回収を図る手続きです。債務名義は不要で、担保権の登記があれば手続きを開始できるのが特徴です。
強制執行手続とは?
強制執行手続は、お金を貸した側が勝訴判決や和解調書などの債務名義を得ているにもかかわらず、借りた側が任意の支払いに応じない場合に取られる手続きです。債務名義を得た債権者の申立てにより、裁判所が債務者の財産に対して強制的に執行を行います。(参照:民事執行法第22条)
強制執行の方法には、以下の3つが代表的です。
- 不動産執行
- 債務者の所有する土地や建物を差し押さえ、競売にかけて売却代金から債権回収を図る方法。
- 債権執行
- 債務者の給料や預金などの金銭債権を差し押さえ、直接取り立てる方法。
- 動産執行
- 債務者の所有する自動車や貴金属などの動産を差し押さえ、換価して債権回収を図る方法。
それぞれの方法には、差押えの対象や換価の手順など、固有の特徴があります。借金の存在を認識していない債務者が、突然の差押えに直面するケースもあるため注意が必要です。
担保権の実行手続
担保権の実行手続は、債務者が担保として提供した不動産などについて、債権者が持つ抵当権などの担保権を実行する手続きです。
住宅ローンの返済が滞った場合などに、金融機関が抵当権を実行して物件を競売にかける事例が多く見られます。この場合、債務名義は不要で、裁判所に提出する登記簿謄本などから担保権の存在が確認できれば手続きが開始されます。所有者の同意なく不動産が売却されるため、担保を提供する際はリスクを理解しておくことが大切です。
不動産執行
不動産執行とは
不動産執行とは、借金の返済ができない場合に、不動産を強制競売又は強制管理して債務の弁済に充てる手続きのことです。(参照:「民事執行法第二章第二節第一款」)
民事執行法では「不動産に対する強制執行は、強制競売又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。(民事執行法第43条)」と定められています。
強制競売は,債務者所有の不動産を差し押さえ,これを売し,その売得金を債権者の債権の弁済に充てることを目的とする執行方法です。
一方、強制管理は,目的不動産を差し押さえ,管理人にこれを管理させ,その不動産から得る収益を債権の満足に充てることを目的とする執行方法です。
不動産執行の流れ
まずは、管轄の地方裁判所に申立てを行い、裁判所が不動産執行の開始決定を行います。これにより、目的不動産が差し押さえられ、管轄法務局に「差押」の登記がされます。同時に、債務者と所有者には、開始決定正本が送達されます。
その後、裁判所は売却の準備を進めます。執行官や評価人による詳細な調査が行われ、買受希望者に閲覧してもらうための書類(現況調査報告書、評価書、物件明細書(通称:三点セットといいます))が作成されます。さらに、評価人の評価に基づいて売却基準価額が定められます。
売却基準価額が決まったら、次は売却の実施です。裁判所書記官が売却の日時、場所、方法を定めます。第1回目の売却方法は通常、期間入札となります。売却情報はインターネット上の不動産競売物件情報サイトBITや、日刊新聞、住宅情報誌などで広告されます。
入札は、保証金を納付し、買受可能価額以上の金額で行います。最高価で落札し、売却許可された買受人は、期限までに代金を納付します。所有権移転などの登記手続きは裁判所が行いますが、登録免許税などの費用は買受人の負担となります。
不動産の引渡しについては、引き続き居住する権利を主張できる人が住んでいる場合、すぐには引き渡してもらえません。そのような権利がない人の場合は、明渡しを求めることができ、応じない場合は引渡命令を出してもらうこともできます。
最後に、裁判所が売却代金を債権者に配当する手続きが行われます。これにより、借金返済が滞った人の財産を売り払って、お金の回収を図ることとなるのです。
債権執行
債権執行とは
債権執行とは、法令上は、「金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権に対する強制執行」(民事執行法第143条)と定められております。
簡単に言うと、債権者が、債務者から直接金銭の支払いを受けられない場合に、債務者の第三者に対する金銭債権(例えば、債務者の勤務先に対する給料債権や、債務者の銀行に対する預金債権)を差し押さえ、それを取り立てることによって、債権の満足を得る手続きのことをいいます。(民事執行法第二章第二節第四款)
債権執行は、民事執行法に基づいて行われる強制執行の一種であり、債務名義(判決や公正証書など)が必要です。
債権執行の代表的な手段と効果
債権執行の対象となる債権は、差押えが禁止されているものを除き、原則としてあらゆる金銭債権が含まれます。(民事執行法第146条)そのなかでも、代表的な手段としては、給料の差押えと預金の差押えが挙げられます。
給料の差押えを受けると、債務者は差押えられた給料を雇い主から直接受け取ることができなくなります。ただし、給料のうち4分の3に相当する額は差押えが禁止されているため、債権者が差し押さえられるのは4分の1相当額のみです。(民事執行法第152条)
給料の差押えは、債権者の債権額が全額回収されるまで継続的に行われ、賞与(ボーナス)も対象となります。
預金の差押えも債権執行の代表的な手段です。これは、銀行口座に預けている預金を差し押さえる手段で、これについては、給料のような差押禁止部分はありません。そのため、預貯金の全額が差押えの対象となります。
ただし、差押えの効力は、差押命令が金融機関に送達された時点の口座残高にのみ及ぶため、その後の入金分は引き出し可能です。また、預金の差押えを受けても、一般的に口座が凍結されることはありません。しかし、差押えを受けた口座を継続して使用すると、再度差押えを受ける可能性があるため注意が必要です。
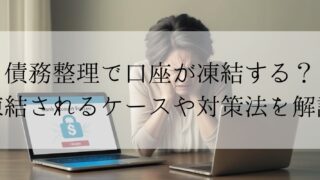
債権執行の流れ
債権執行の基本的な流れは以下のとおりです。
①債権者は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に対し、債権差押命令の申立てをします。申立ては、債務名義及び差し押さえる債権を特定して行います。
②裁判所は、債権差押命令の申立てに理由があると認めるときは、差押命令を発し、債務者と第三債務者に送達します。
③差押命令が第三債務者に送達されると、第三債務者は、債務者に対して弁済をすることができなくなります。他方、差押命令が債務者に送達されてから1週間が経過すると、債権者は差し押さえた債権の取立てが可能になります。
④債権者は、第三債務者から直接取立てを行うことができます。ただし、複数の債権者が差押えをしている場合や、第三債務者が供託をしている場合は、裁判所において配当手続が行われます。
⑤債権者が取立てにより金銭の満足を得られた場合は、差押えは効力を失います。全部の弁済を得られない場合は、不足分について再度差押えを行うことができます。
動産執行
動産執行とは
動産執行(動産の差押え)とは、債権回収の場面において、債務者が裁判で敗訴し支払いを命じる判決が出ているにもかかわらず、それでも支払いをしない場合に行われる強制執行の一つです。(民事執行法第二章第二節第三款)
この手続きでは、債権者が裁判所の執行官とともに債務者の経営する店舗や自宅に立ち入り、そこで発見した債務者の所有する財産を強制的に差し押さえ、売却することで債権の回収を図ります。(民事執行法第122条)
動産執行は、債務者の財産を強制的に差し押さえるという非常に強力な手段であり、執行官には差押えをするに際し、債務者の住居その他債務者の占有する場所に立ち入り、目的物を捜索することができるという権限を与えられています。また、必要があるときは、閉鎖した戸及び金庫を開くため必要な処分をすることができると定められています。(民事執行法第123条)具体的には、扉にかかっている鍵を強制的に開けたり、容器を壊して開けたりすることができるのです。
差し押さえ禁止債権は例外的に持っていかれない
しかし、いくら債務者がお金を払わないからと言っても、すべてを失ってしまっては生活ができません。これでは、憲法25条で定められた生存権の確保さえ困難にしてしまう恐れがあります。
そのため、民事執行法第131条では、差し押さえ禁止の債権を列挙されています。
一方で、同法第131条第1号から第14号までに規定される差押禁止財産は、動産執行の対象となりません。差し押さえ禁止債権は、債務者やその家族の生活や仕事に最低限必要な衣服、家具、道具、書類、現金などが対象となります。
また、民事執行法第132条では、「執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押えの全部若しくは一部の取消しを命じ、又は前条各号に掲げる動産の差押えを許すことができる」として、自由財産の拡張を認める場合があります。
ちなみにですが、破産法第34条(破産財団の範囲)では、民事執行法第131条が準用されていますので、差押え禁止債権の範囲と、自己破産で換価処分の対象とならないものの多くは共通しています。
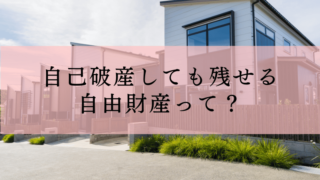
動産執行の流れ
動産執行の手続きは、以下の5つのステップで進められます。
(1)債権者が、債務名義と債務者の財産状況等を記載した動産執行の申立書を、管轄の地方裁判所に提出します。
(2)裁判所の執行官から連絡があるので、執行官と動産執行の日時・場所などを打ち合わせます。その際、債務者宅のドアが開かない場合に備えて開錠業者の手配や、差し押さえ物を運ぶ車両の手配なども行っておく必要があります。
(3)動産執行当日、債権者(または代理人弁護士)は、執行官とともに債務者の自宅や店舗に赴きます。執行官のみが建物内に立ち入ることができ、債権者は外で待機します。
(4)執行官が建物内を捜索し、差押えの対象となる財産(現金あるいは換価可能な動産)を発見した場合、それらを差し押さえて持ち帰ります。この際、差し押さえた動産は執行官が保管します。
(5)執行官から指定された売却期日に、差し押さえた動産が売却され、その売却代金から執行費用などを差し引いた残額が、債権回収に充てられます。売却の方法としては、その場で専門業者に購入させる方法と、債権者自身が買い受けて債権と相殺する方法があります。
差し押さえをされた!差押えされそう……そんなときの対応方法は?
債務の全額弁済
差し押さえを解除する最も確実な方法は、債務を全額弁済することです。
借金や税金などの滞納分を期日までに完済すれば、差し押さえは解除されます。これは、差し押さえの目的が滞納金の回収であるため、全額弁済により差し押さえを継続する必要性がなくなるからです。しかし、借金を払えるんならそもそも借金は滞納していないでしょう。借金滞納は経済的困窮が原因であるため、現実的には全額弁済による差し押さえ解除は難しいでしょう。
債権者との和解交渉
差し押さえを解除するもう一つの方法は、債権者との和解交渉です。
債権者に差し押さえによる競売の取り下げを求め、合意を得ることで解除が可能となります。また、不動産が差し押さえ対象の場合、競売よりも有利な条件で売却できる任意売却を交渉材料とすることで、解除に応じてもらえる可能性があります。
ただし、滞納借金の支払い保証がない以上、債権者が簡単に取り下げに応じることは稀です。
繰り返しになりますが、借金を払えるんならそもそも借金は滞納していません。そして、支払いが出来ないから差し押さえになっているのです。支払の保証がない口約束より、確実に財産を確保できるであろう強制執行の方が有効だと考える債権者の方が、圧倒的に多いことを忘れてはいけません。
不服申立制度の活用
差し押さえに不服がある場合、不服申立制度を活用することで解除を求めることができます。不服申立てとは、差し押さえ処分に対し権利や異議を主張し、取り消しや変更を求める手続きです。
ただし、専門性の高い手続きであるため、単独で行うことは難しいでしょう。弁護士や司法書士などの専門家に相談し、不服申立ての是非や手続きについて助言を受けることをおすすめします。不服申立制度を適切に活用することで、不当な差し押さえから身を守ることが可能となります。
法的整理を行う
差し押さえを解除する抜本的な方法として、法的整理が挙げられます。
自己破産は、借金の返済が不可能な状態であると裁判所に認めてもらい、返済義務を免除してもらう手続きです。給与の差し押さえは、自己破産手続き開始により一旦中止されます。(破産法第249条)
また、個人再生は、借金返済が困難な状況を裁判所に認めてもらい、大幅な債務減額を受ける手続きです。給与の差し押さえは、個人再生手続き開始決定により中止されます。(民事再生法26条1項)ただし、再生計画が認可されるまでは差し押さえ分が管理され、認可後にまとめて支払われるため、すぐに全額受け取れるわけではありません。
法的整理は、差し押さえ解除の有効な手段ですが、弁護士などの専門家と相談の上、慎重に検討する必要があります。
まとめ
強制執行は、債務者が借金を返済できない場合に、債権者の申立てにより裁判所が強制的に債務者の財産に執行を行う手続きです。代表的な方法として、不動産執行、債権執行、動産執行の3つがあります。
不動産執行では、債務者所有の不動産を差し押さえ、競売にかけて売却代金から債権回収を図ります。債権執行では、債務者の給料や預金などの金銭債権を差し押さえ、直接取り立てます。動産執行では、債務者の所有する動産を差し押さえ、換価して債権回収に充てます。
いずれの方法も、債務者の財産を強制的に差し押さえるという非常に強力な手段であり、差押えを受けた債務者は、生活に必要な財産まで失うリスクがあります。ただし、差押禁止財産として、生活や仕事に最低限必要なものは保護されています。
強制執行を避けるためには、早期の借金返済や債権者との和解交渉が重要ですが、それが難しい場合は、不服申立制度の活用や法的整理(自己破産・個人再生)について検討する必要があります。
強制執行が間近に迫ってるなら弁護士や司法書士に相談を!
強制執行は、一度始まると債務者の生活に大きな影響を与えます。差押えにより、生活や仕事に必要な財産まで失うリスクがあるのです。また、強制執行の手続きは複雑で専門的な知識が要求されるため、債務者が単独で対応することは困難を極めます。
そのため、強制執行が間近に迫っている、あるいは既に差押えを受けてしまった場合は、早急に弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。法律の専門家である彼らは、債務者の置かれた状況を的確に把握し、最適な解決策を提案してくれるはずです。
弁護士や司法書士は、債権者との交渉や和解、不服申立制度の活用、自己破産や個人再生の手続きなど、様々な局面で債務者をサポートします。強制執行による不利益を最小限に抑え、債務者の生活再建を助ける心強い味方となってくれるでしょう。
強制執行は、放置すればするほど状況が悪化します。早期の専門家相談こそが、債務者が取るべき最善の行動といえるでしょう。財産を失う前に、一刻も早く専門家のアドバイスを求めることが重要となるのです。