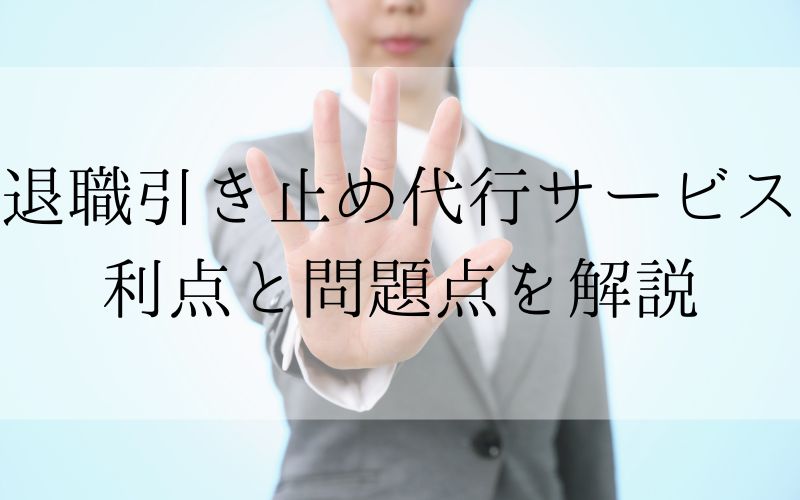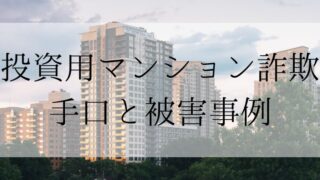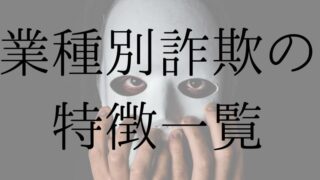「退職代行」という言葉を最近よく耳にするようになりましたね。会社に辞めたいと直接言いにくい人が増えた結果、このようなサービスが広まったのです。
しかし、社員が突然辞めてしまうことに困っている会社も多いです。どうすれば離職の波を止められるのか、多くの経営者や人事担当者が悩んでいます。
そんな中、「退職代行」に対抗するかのように、「引き止め代行サービス」という新しいサービスが登場し、大きな話題となっています。
しかし、この新しいサービスは、本当に社員を引き止められるのでしょうか。また、法的な問題はないのでしょうか。
この記事では、話題のサービス「イテクレヤ」を例に挙げ、そのサービス内容や、会社にとってのメリットとデメリットについて詳しくご紹介します。さらに、引き止め代行サービスが持つ問題点や、どのような時に活用すべきかについても解説します。
目次
話題の引き止め代行サービス「イテクレヤ」とは?
退職代行に対抗する新たなサービス
もしあなたが経営者や人事担当者であれば、従業員からの突然の退職の申し出に頭を抱えた経験があるかもしれません。特に近年、退職代行サービスの普及は目覚ましいものがあります。従業員と直接話す機会がないまま、見知らぬ業者から退職の連絡が来る。この状況は、多くの企業にとっても大きな損失となっています。
こうした背景の中、退職代行に対抗する新しいサービスが登場しました。それが、株式会社おくりバントが2025年9月4日にリリースした、「退職引き止めサービスイテクレヤ」です。この革新的なサービスが、多くのメディアで注目を集めています。(週刊現代「退職代行サービス「モームリ」に対抗か、退職引き止めサービス「イテクレヤ」が登場…両サービスの社長に話を聞いてみた」ABEMAtimes「離職を防ぐ?退職代行「モームリ」の次は…“退職引き留め”サービス「イテクレヤ」が登場」)
イテクレヤは、単なる引き止め交渉を目的としていません。むしろ、社員がなぜ辞めたいのか、その本当の理由を第三者の視点から探り、組織の根本的な課題解決を支援することを目指しています。
つまり、退職代行が「辞める側の味方」であるのに対し、イテクレヤは「企業と社員の関係を修復する仲介役」という立ち位置と言えるでしょう。
株式会社おくりバント「株式会社おくりバント、退職引き止めサービス「イテクレヤ」を正式リリース」(PR TIMES, 2025年9月4日)
引き止め代行サービス「イテクレヤ」のサービス内容と費用
イテクレヤのサービス内容は、一言で言えば「退職を防ぐためのコンサルティング」です。
まず、サービスは経営者や人事責任者への丁寧なヒアリングから始まります。この段階で、会社の現状や、退職が続く背景について深く話し合われます。
次に、最も重要なプロセスである、社員への匿名でのインタビューが実施されます。退職希望者だけでなく、複数の社員に話を聞くことで、普段は口にできない不満や要望、人間関係の悩みといった生の声を集めます。
これらの貴重な情報を整理・分析した上で、経営層へフィードバックされます。これにより、これまで見過ごされてきた組織の課題が浮き彫りになるのです。
そして、この結果をもとに、具体的な改善策が提案されます。
たとえば、人事制度の見直しや、社員が気軽に悩みを相談できる窓口の設置など、多岐にわたる解決策が提示されます。最終的には、イテクレヤの担当者が同席し、経営者と社員が直接対話する場が設けられる場合もあるとのことです。
気になる費用についてですが、提供内容やアウトプット(成果物)に応じて変動するとされ、PR TIMESの記事には具体的な料金は明記されていません。このことから、画一的な料金体系ではなく、依頼企業の状況に合わせて柔軟に対応する形式だと推測できます。
引き止め代行サービスの利点と法的問題点
引き止め代行サービスで離職の根本原因を探ることが出来る
多くの企業が直面している「退職理由が分からない」という問題。この悩みを解決できるのが、引き止め代行サービスの最大の利点です。
転職サービスの大手「株式会社マイナビ」による調査では、退職代行を利用する従業員の約4割が「引き止められるのが嫌だから」という理由を挙げています。(株式会社マイナビ「「退職代行サービスに関する調査レポート(企業・個人)」を発表」)
また、エン・ジャパン株式会社の調査によると、退職時、本当の退職理由を伝えなかった方は半数以上であり、その理由として「話しても伝わらない」「引き止めが面倒だった」という理由を挙げる方が多くいました。(エン・ジャパン株式会社「「本当の退職理由」調査」)
つまり、退職する多くの従業員は引き留められることを回避したいと考えており、また、理由を聞いても本当のことを言ってくれるとは限らないということが分かります。これでは、離職の根本原因を探ることはできないでしょう。
この点、引き止め代行は、この壁を取り払う役割を果たします。第三者が匿名で話を聞くことで、従業員は安心して本音を語ることができますし、給与や人事評価への不満、特定の人間関係のトラブルなど、これまで隠されていた問題が明るみに出るのです。
これは、単に退職を防ぐだけでなく、企業に組織の課題を改善する貴重な機会をもたらします。一時的な慰留(引き止め)ではなく、根本的な問題を解決することで、将来的な離職率の低下にも繋がります。
このように、引き止め代行サービスは、適切に利用することで、離職の根本原因を探ることが出来、企業組織を改善することに役立つという点は、強調しておきたいと思います。
引き止め代行サービスに違法性はないのか?
一方で、引き止め代行サービスを利用する上で、法律的なリスクは無視できません。
最大の懸念は、弁護士法72条です。この法律は、弁護士ではない人が報酬を得て、法律に関する事務を扱うことを禁止していますが、退職の引き止め交渉は、法律事務に該当すると見なされる可能性があります。引き止め代行サービスが、退職条件(退職日や有給休暇の消化など)について、企業側に代わって交渉を行うようなことがあれば、これは非弁行為として違法となる可能性が非常に高いと言えるでしょう。
また、不当な引き止め行為が違法になる可能性もあり得ます。そもそも、日本国憲法第22条では、職業選択の自由が保障されており、これには「退職の自由」も含まれます。また、民法第627条では、「期間の定めのない雇用契約の場合、労働者はいつでも解約(退職)の申し入れをすることができ、申し入れから2週間で雇用契約が終了する」と定められています。この法的根拠があるため、会社が退職を拒否することは原則としてできません。
ですが、現実には、会社が不当な引き止め行為を行うことがしばしば起こります。たとえば、会社が退職届の受け取りを拒否したり、「辞めるなら給料や退職金は支払わない」「損害賠償請求を行う」などと脅したりする行為があります。ですが、これらの脅しは労働基準法違反や民法上の不法行為に該当する可能性が高く、法的には通用しない話なのです。
これらの行為は、企業イメージを著しく損ない、最悪の場合、退職者から損害賠償請求に発展するリスクがあります。
引き止め代行サービスは引き留め行為により、これらの危険な領域に足を踏み入れないよう、サービスの範囲を明確にすることや、直接の交渉は行わず、コンサルティングのみを行うことが必要になるかと思われます。
| 違法となる引き止め行為の例 | リスク |
| 「辞めるなら損害賠償を請求する」 | 強要罪・損害賠償請求 |
| 「話が終わるまで帰さない」 | 監禁罪 |
| 退職届の意図的な不受理 | 従業員の権利を不当に侵害 |
引き止め代行サービスはどのように活用すべき?
引き止め代行サービス「負のスパイラル」を断ち切る
あなたの会社では、退職が連鎖的に起きていませんか?もしそうだとしたら、それは単なる個人の問題ではなく、組織全体に根深い課題がある可能性が高いです。そのような「負のスパイラル」に陥った状況こそ、引き止め代行サービスを活用すべきタイミングです。
例えば、離職率が慢性的に高い企業は、労働環境に問題がある可能性が高く、また、一人一人に理由をヒアリングすることは難しいでしょう。
また、特定の部署やチームで退職が続く場合や、経営者が社員の本音を把握できていないと感じている場合、組織内部での意思疎通や人間関係などに大きな問題を抱えてる可能性があり得ます。
これらの状況では、内部の人間だけで問題解決を図るのは非常に困難です。
ですが、引き止め代行サービスを、組織の「健康診断」として活用することで、離職の原因を客観的に分析し、具体的な改善策を立てられます。つまり、これは一時的な解決策ではなく、未来の組織を良くするための投資なのです。
根本解決の鍵は企業の姿勢
どんなに優れたサービスを利用しても、最終的に組織を改善するのは、企業の姿勢に他なりません。引き止め代行は、あくまでも「きっかけ」に過ぎません。
しばしば、退職代行を「会社に対する裏切り」と捉える見方がありますが、この態度は従業員との信頼関係を根底から損ないます。従業員が退職代行を利用する背景には、「直接退職を伝えられない」「会社に話を聞いてもらえない」といった、企業への深刻な不信感があるからです。
そして、一人の従業員が退職を選択したとき、その背後には「退職予備軍」と呼べる潜在的な不満を抱えた従業員が多数存在すると考えるべきです。退職代行は、そうした組織の課題が表面化したサインであり、企業はこれを真摯に受け止める必要があります。
現代社会において、終身雇用はもはや当たり前ではありません。社員は会社を「選ぶ」時代へと変化しています。企業は、社員を単なる「労働力」として管理するのではなく、共に成長していく「パートナー」として向き合う姿勢が不可欠です。
引き止め代行サービスを通じて社員の本音を知ることは、組織改善の貴重な機会です。給与や役職の改善、適材適所の人事配置、そして風通しの良い職場環境づくりなど、具体的な行動で改善策を示すことが重要です。社員は、こうした企業の真摯な姿勢を見て、「会社が自分たちに向き合ってくれている」と感じ、信頼関係が再構築されます。
この信頼関係の再構築こそが、人材の流出を防ぎ、組織を健全に成長させる最も確実な方法です。