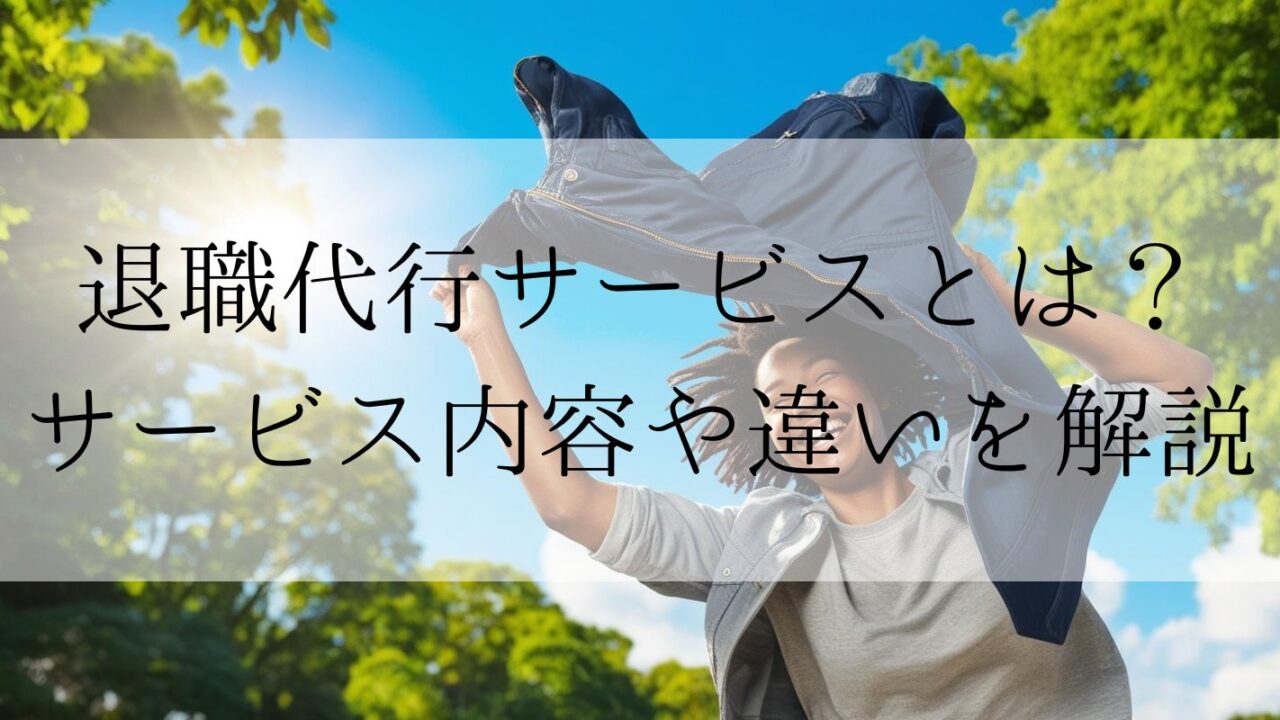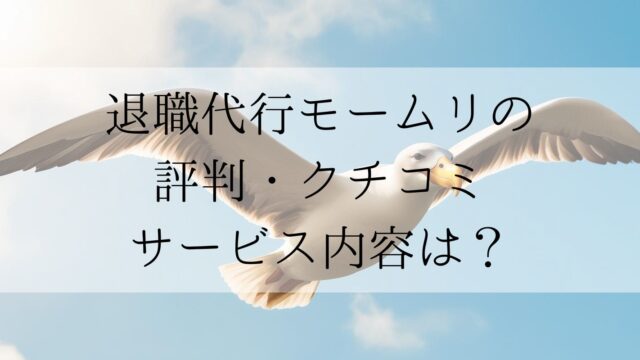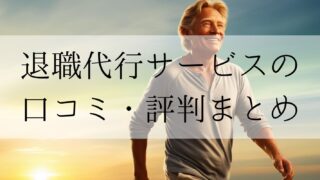退職したいのに「言い出せない」「引き止められそうで不安」──
そんな悩みを解決する手段として注目されているのが退職代行サービスです。
近年、20代・30代を中心に利用者が急増し、メディアでも頻繁に取り上げられています。しかし一口に退職代行と言っても、弁護士、労働組合、民間企業など提供者によって内容や法的な強さに大きな違いがあります。
この記事では、退職代行の基本的な仕組みや利用状況、他のサービスとの違いをわかりやすく解説し、自分に合った選び方を考えるヒントをお届けします。
退職代行とは?職場とのやり取りをすべて任せられる便利なサービス
退職代行サービスとは何か?
退職代行サービスとは、会社を辞めたい人に代わって、専門のスタッフがその意思を職場に伝えてくれるサービスです。
依頼者は会社と直接やり取りをする必要がありません。そのため、上司に引き止められたり、気まずい雰囲気に耐えたりする必要がないのです。特に、職場に行くのがつらくなってしまった人や、上司に話をするだけでもストレスを感じる人にとって、大きな助けとなっています。また、「辞めたい」と何度伝えても、はっきりとした返事をもらえないケースでも有効です。
つまり、退職の申し出が難しいと感じる人にとっては、非常に頼れる選択肢なのです。
もともとはあまり知られていませんでしたが、最近では利用者が急増しています。株式会社マイナビの調査によりますと、2024年1月~6月に退職代行サービスを利用して退職した人がいた企業は23.2%。また、過去の退職代行利用者の実績を年度別に聞くと、2021年は16.3%、2022年は19.5%、2023年は19.9%、となり、退職代行利用による退職者が年々増加傾向にあることがわかっています。
退職代行サービスの3つのタイプについて
退職代行サービスには、大きく分けて3つのタイプがあります。それぞれ対応できる範囲が違うので、自分に合ったタイプを選ぶことが大切です。
まず1つ目は、「弁護士による退職代行」です。
これは法律の専門家である弁護士が依頼を受けて、退職日や引継ぎの内容などについて、正式に会社と交渉してくれる方法です。未払いの残業代がある場合や、パワハラなどの問題が絡むときは、このタイプが安心です。
次に、「退職代行ユニオン」というタイプがあります。これは労働組合が運営するもので、会社に労働組合がない場合でも、外部のユニオンに加入することでサポートを受けられます。
ユニオンには、会社と直接交渉する権利(団体交渉権(日本国憲法第28条,労働組合法))があります。そのため、弁護士運営の退職代行サービスと同様に、退職日や未払いの給与についてもしっかり話し合うことが可能です。ただし、裁判になったときには代理人にはなれないという制限があります。
最後は、一般の「民間企業が行う退職代行サービス」です。こちらは、会社に退職の意思を伝えるところまでを担当します。料金が比較的安く、スピード対応してくれることが多いのが特徴です。また、無料で転職支援・メンタルクリニックの紹介といったユニオンや弁護士事務所では提供していない独自のサービスがある点が魅力です。


費用はどのくらいかかる?相場は?
退職代行サービスの費用は、依頼する先によって大きく異なります。サービスの内容やサポート範囲が異なるため、どこに頼むかで値段も変わってきます。
まず、一般的な民間の退職代行サービスでは、費用の目安は2万円台後半から5万円ほどです。手軽に利用できるうえ、料金も比較的安いため、スムーズな退職を目指す方におすすめです。
次に、労働組合が行う退職代行サービスの相場は2万5千円から3万円前後です。有給休暇の取得や退職日の調整、未払い給与の請求など、具体的な条件を話し合いたい場合に向いています。ただし、組合に加入する必要があり、加入金や組合費が別にかかることもあるため、事前に確認が必要です。
最後に、弁護士が行う退職代行サービスがあります。こちらはもっとも費用が高く、5万円から10万円以上かかる場合もありますが、法的なトラブルに強いという利点があります。たとえば、パワハラや不当解雇など、会社との間で法律問題が起きている方には非常に頼もしい存在です。
費用以外のお金に注意
極端に安い価格を掲げるサービスにも警戒が必要です。たとえば、最初の説明が不十分だったり、退職のサポートが不完全だったりすることもありえます。場合によっては、後から高額な料金を請求されるといったトラブルに発展することもあるので、しっかりと確認しましょう。
例えば、多くの業者では、最初の相談は無料であることが多いですが、中には有料のケースもあります。
また、一見安く見える料金設定でも、後から追加費用が必要となる場合もあるため、事前の確認が欠かせません。基本料金には、退職の意思を伝える作業や、書類作成の支援などが含まれていますが、書類を代行して送付したり、会社とのやりとりを追加で頼む場合には、別途オプション料金が発生することもあります。
なお、一部の信頼できるサービスでは、万が一退職できなかった場合に備えて「返金保証制度」を設けているところもあります。これがあると安心して依頼できるので、選ぶ際のポイントになります。
退職代行の費用についてはこちらの記事をご参照ください

どんな人が利用しているの?利用者の状況は?
退職代行サービスは、近年多くの人に利用されています。
国内最大級の管理部門と士業の専門サイトmanegyの実施したWEBアンケートでは、「退職代行を知っていますか?」という設問に対し「サービス内容を知っている」と回答した割合は66.8%、「聞いたことがあるが、サービス内容は知らない」が25.2%で、「退職代行」サービスの知名度は合計92.0%となりました。
では、実際にどんな人がこのサービスを使っているのでしょうか? 利用者の年齢層や職業、退職の理由などについて、具体的なデータをもとに解説します。
利用者の年代
退職代行サービスの利用者の中で最も多いのは20代です。退職代行モームリの調査によると、全体の約60%が20代という結果が出ており、特に20代前半が多いとされています。この世代は、若年層における退職代行の認知度が非常に高く、8割以上が「退職代行サービスを知っている」と答えています。この背景には、若い世代が転職に対して比較的柔軟な考えを持っていることが影響していると考えられます。また、株式会社マイナビの調査でも20代前半が最も多く、次いで20代後半となっています 。
もちろん、退職代行を利用するのは20代だけではありません。10代後半から70代まで、幅広い年齢層の人々が利用しています。中でも30代や40代の利用者も増えてきており、年齢を問わず「退職をスムーズに進めたい」というニーズが高まっていることが分かります。
利用者の雇用形態
株式会社マイナビの調査によると、退職代行サービスを利用する人々の雇用形態では、正社員が最も多い傾向にあります。
正社員として働きながら、仕事に対するストレスや環境の悪さから退職を決意した人々が利用しています。一方、アルバイトやパートの方々も一定数利用しており、特に仕事の拘束時間が長く、労働環境が厳しい場合に選ばれることが多いです。
利用者の職種
退職代行モームリの調査によると、退職代行サービスを利用する職種では、サービス業や製造業の人々が多いとされています。これらの業界では、人手不足や長時間労働が常態化しており、心身の負担が大きいため、退職代行を頼む人が多いのです。
また、エン転職ユーザーアンケートでも同様の傾向があり、営業職やサービス業等の他には、IT業界のクリエイター、エンジニアなどの職種でも利用が増えてきています。
特に営業職では、過度なノルマや顧客対応のストレスから退職を決意する人が目立っています。
利用者の勤続年数
退職代行サービスを利用する人々の多くは、入社してから半年以内で退職を決めています。退職代行モームリの調査によると、「1ヶ月未満」が24.4%、「1ヶ月~6ヵ月未満」が38.7%を占め、合計で63.2%の人が半年未満で退職しています。また、1ヶ月未満で退職を決意するケースも少なくありません。
新卒入社後の早期離職が目立ち、特に4月や5月に退職を決意する人が多いことが分かっています。これは、採用後のミスマッチや職場環境の不一致が原因である場合が多いとされています。
退職代行を利用する理由
退職代行を利用する理由については、エン転職ユーザーアンケートによると、退職代行を利用する理由はさまざまですが、最も多いのは「退職を言い出しにくい」という点です。また、他にも、「上司のハラスメント」「退職させてもらえない」という理由も挙げられています。
上司に直接退職を伝えることに対する心理的な抵抗感や、言い出しにくい職場環境が影響しています。また、退職を伝えても引き止められることを恐れている人も多く、退職代行サービスを利用することで、引き止めや対話を避けることができます。
そのほか、すぐにでも退職したいという強い希望がある場合や、退職後の手続き(有給消化や未払い賃金の請求)を自分で交渉するのが面倒だと感じる人も利用しています。
弁護士事務所やユニオンの退職代行とは何が違うの?どんな時に選ぶべき?
弁護士事務所やユニオンの退職代行とは?
弁護士事務所の行う退職代行サービスとは
弁護士が行う退職代行サービスは、法律の専門家だからこそできる対応が最大の魅力です。退職の意思を会社に伝えるだけでなく、有給休暇の取得や未払い賃金の請求など、法的な根拠に基づいて交渉を進められます。特に、パワハラやセクハラ、不当解雇といった深刻なトラブルがある場合には、心強い味方となります。
また、弁護士は正式な代理人として会社とやり取りをしてくれるため、ご本人が直接対応する必要は一切ありません。この点でも精神的な負担が大きく軽減されます。
ただし、弁護士による退職代行は費用が高く、相場は5万円から10万円以上になることが一般的です。費用面よりも、法的に確実な退職と安心を重視する方に向いていると言えます。
ユニオンの退職代行サービスとは?
退職代行ユニオンとは、労働組合が提供する退職代行サービスの総称です。一般的な企業が運営する民間のサービスとは異なり、労働組合法に基づく「団体交渉権(だんたいこうしょうけん)」という強力な権限を持っています。
これにより、会社に対して退職日の調整や有給休暇の消化、未払い賃金の請求といった交渉を、依頼者に代わって行うことが可能です。このような交渉は、民間業者では法律上できないため、退職代行ユニオンならではの大きな強みとなります。
また、正社員に限らず、アルバイトや派遣社員、契約社員でも利用できる場合が多く、雇用形態に関係なく退職のサポートが受けられるのも特徴です。
費用相場は2万5千円から3万円程度で、交渉力の高さと比較すればコストパフォーマンスに優れています。ただし、サービスの内容は組合ごとに違いがあるため、事前の確認が大切です。もし裁判になった場合には、別途弁護士を依頼する必要がある点にも注意しましょう。
なお、退職代行ユニオンが、退職代行会社を運営しているケースもありますので、民間のサービスとの違いはそこまで大きくない場合もあります。
一般的な退職代行と弁護士事務所の違いは?
では一般的な退職代行サービスと、弁護士が行う退職代行の違いはなんでしょうか?
まず一般的な事業者が行う退職代行は、主に退職の意思を会社に伝え、その後の事務的な手続きを行うことを中心としたサービスです。依頼者に代わって会社に連絡し、退職の手続きをスムーズに進めます。ただし、会社と交渉することは法律で禁止されており、有給休暇の消化や未払い賃金の請求などはできません。
これに対して、弁護士事務所が提供する退職代行は、法律の専門家である弁護士が依頼者の代理人として交渉を行います。未払い給料や残業代の請求、退職日の調整、パワハラや不当解雇といった法的トラブルへの対応も可能です。
また、必要に応じて労働審判や訴訟の手続きまで視野に入れた対応ができます。
ただし弁護士事務所の退職代行サービスは費用は高く、一般的に5万円〜10万円以上となることが多いです。ただ、やや高めの費用の分、法的な安心感は大きく、精神的負担の軽減にもつながります。
一方で、一般的な事業者が行う退職代行の場合、費用は20000円~30000円程度になることが多く、スピーディに退職をしたい場合にはこちらの方が良いかもしれません。
退職代行サービスと退職代行ユニオンの違いは?
退職代行サービスと退職代行ユニオンは、どちらも「会社に行かずに退職したい人」の味方をする一般企業や団体ですが、退職代行サービスと退職代行ユニオンでは、対応できる範囲に明確な違いがあります。
まず、一般的な退職代行サービスは、主に民間企業が運営しています。退職の意思を会社に伝えることはできますが、交渉はできません。たとえば、有給を消化したい、未払いの給料を請求したいといった話し合いは、法律の制限により対応できないのです。
一方で、退職代行ユニオンは労働組合が運営しています。労働組合は「団体交渉権(だんたいこうしょうけん)」という法的な力を持っており、会社に対して有給休暇の消化や退職日の調整、未払い賃金の請求などの交渉を合法的に行えます。この交渉力の高さが、ユニオン型の最大の強みです。
ただし、退職代行サービスと退職代行ユニオンのいずれも、訴訟などの法的手続きには対応できないため、会社とのトラブルが深刻な場合は弁護士に依頼する必要があります。
費用は退職代行サービスよりやや高めですが、2.5万〜3万円前後が一般的です。サポート内容や料金はユニオンごとに異なるため、事前に比較・確認をしましょう。
まとめ
退職代行とは
退職代行とは、労働者が会社に直接退職の意思を伝えることなく、第三者(退職代行業者)を通じて退職の手続きを進めるサービスです。主に弁護士、労働組合、民間企業の三者が提供しており、依頼者は即日退職の意思を伝えることができる点が特徴です(出典:厚生労働省『労働条件に関する総合調査』2022年)。
退職代行の利用状況
民間調査によると、退職代行サービスの利用経験がある人は20〜30代を中心に増加傾向にあります(出典:株式会社マクロミル「退職代行サービスに関する調査」2023年)。利用理由としては「精神的負担の軽減」「会社とのトラブル回避」「即日退職希望」などが多く挙げられています。特にブラック企業や長時間労働によるストレスからの解放を目的とするケースが目立ちます。
退職代行サービスと他のサービスの違い
退職代行は「依頼者の代わりに退職意思を伝える」点で、転職エージェントやキャリア相談サービスとは異なります。
- 弁護士が行う退職代行は法的交渉(未払い賃金請求など)が可能です(弁護士法第72条)。
- 労働組合による代行は団体交渉権を持ち、企業との交渉が合法的に行えます(労働組合法第6条)。
- 民間企業による代行は、退職意思の「伝達」のみに限定され、交渉はできません(消費者庁「退職代行サービスに関する注意喚起」2021年)。
このように提供者ごとに対応範囲や法的権限が異なるため、利用目的に応じた選択が重要です。