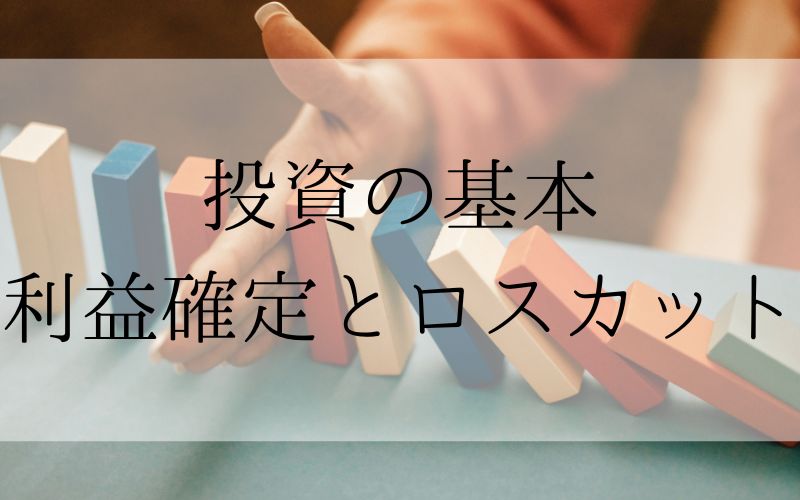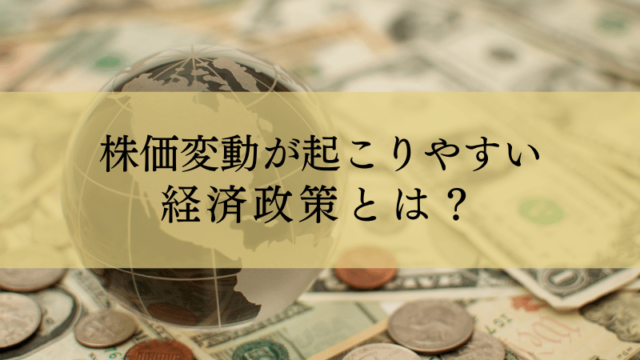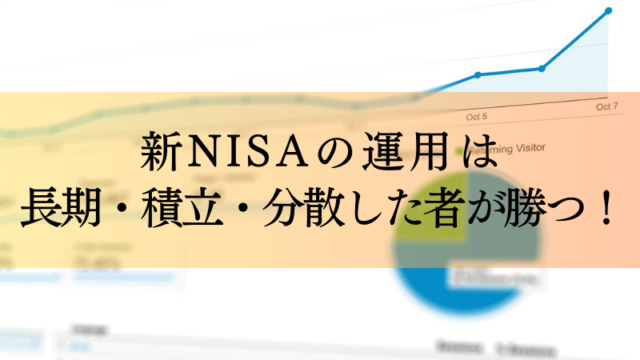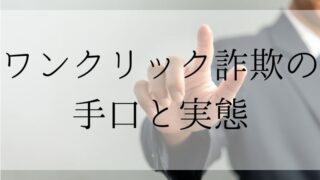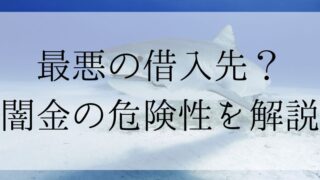「投資に興味があるけれど、何から始めたらいいか分からない…」そう感じているあなたへ。株式投資は、正しい知識があれば誰でも始められます。
しかし、ただ株を買うだけでは、利益を出すことは難しいのです。多くの投資初心者の方が最初にぶつかる壁が、「いつ売るべきか」という問題です。
利益が出ているのに売るのが怖かったり、損が膨らむのをただ見ているだけになったりしていませんか?それは、投資の基本的なルールである「利食い(りぐい)」と「損切り(そんぎり)」を知らないからです。利食いは利益を確定すること、損切りは損失を最小限に抑えること。これら二つは、投資で成功するための必須スキルです。
多くの方が、感情に流されて売買のタイミングを逃してしまいます。実は、プロの投資家も人間なので、私たちと同じように感情を抱くことがあります。だからこそ、感情に左右されないための「ルール」がとても大切なのです。
この記事では、初心者の方でもすぐに実践できる、利食いと損切りの具体的な方法を解説します。また、多くの人が陥りがちな「利食いのワナ」や「損切り貧乏」についても、専門家の意見やデータに基づいてお伝えします。
目次
そもそも「利食い」と「損切り」とは?
利益を確定する「利食い」の目的
投資において「利食い」とは、含み益が出ている投資商品を売って、利益を確定させることです。例えば、1株100円で買った株が130円になったら、この時点で売却して30円の利益を確定します。この行為は、単に利益を得るだけでなく、今後の投資戦略に欠かせない目的があります。
まず、利食いの最大の目的は、利益を確実に自分のものにすることです。含み益は、あくまで「紙の上の利益」です。株価が下落すれば、せっかくの利益は消えてしまいます。利食いをすることで、このリスクをなくし、利益を現金として手元に残せます。
次に、手に入れた現金を再投資に回せることも、利食いの重要な目的です。利益を確定し、別の成長が見込める銘柄に再投資することで、資産を効率よく増やすことができます。これは、利益がさらなる利益を生む「複利効果」を狙うものです。投資家は、利食いをすることで、資金を常に最適な場所に動かすことができます。
また、利食いは精神的な安定にもつながります。利益が目減りする不安から解放され、次の投資機会を冷静に探せるようになります。
このように、利食いは利益を確定させ、再投資によってさらに資産を増やすための戦略的な行動です。投資で得た利益を無駄にしないためにも、利食いの目的をしっかり理解しておきましょう。
損失を限定する「損切り」の重要性
「損切り」とは、含み損が出ている投資商品を売却して、損失を確定させることです。株式投資の世界では「損切りは早く」という格言があるように、多くの専門家がその大切さを訴えています。なぜなら、損切りをしないと、損失がどんどん膨らんでしまうからです。
例えば、1株100円で買った株が、80円に下がってしまったとします。このとき、損切りをしなければ、損失は20円で済みません。さらに株価が下がり続けると、取り返しのつかない大損につながることもあります。そうならないために、損切りによってあらかじめ決めた水準で損失を止め、それ以上の被害を避けるのです。
損切りは、未来の損失を防ぐための「保険」のようなものです。損切りをすることで、資金を守り、他の有望な投資に回すことができます。損失が膨らんだ株に資金を縛られてしまうと、その間に他の銘柄が値上がりしても、投資するチャンスを逃してしまいます。
また、損切りは精神的な負担を軽くします。含み損が拡大していくストレスは、冷静な判断を妨げます。損切りをすることで、いったん冷静になり、次の投資戦略を考えることができるようになります。
このように、損切りは、投資で生き残るために重要なスキルと言えます。
あなたはどのタイプ?利食い・損切りの実践手法
事前に決める!パーセンテージでの設定
「利食いや損切りのタイミングが分からない」という初心者は多いです。そんな方におすすめなのが、事前にパーセンテージを決めておく方法です。これは、感情に流されず、機械的に売買できるため、最もシンプルな手法と言えます。
やり方はとても簡単です。例えば、「株価が購入価格から10%上がったら利食い」「5%下がったら損切り」といったルールを、あらかじめ決めておきます。そして、そのルールに達したら、迷わずに実行するだけです。この手法は、人間の感情が入る余地をなくすことが最大のメリットです。
株価が急騰すると「もっと上がるかもしれない」と欲が出てしまい、利食いが遅れることがあります。反対に、株価が下がると「いずれ戻るだろう」と期待してしまい、損切りが遅れることもあります。
しかし、事前にルールを決めておけば、こうした感情に左右されず、淡々と取引を進めることができます。
多くの投資家がこの手法を採用しています。投資で成功する秘訣は、自分の感情をコントロールすることです。パーセンテージでの設定は、それを可能にする有効な手段の一つなのです。
チャートで判断?テクニカル分析での設定
パーセンテージでの設定が初心者向けだとすれば、より市場の動きを考慮した手法が、「テクニカル分析」を使った設定です。テクニカル分析とは、過去の株価や出来高の動きをグラフ(チャート)にして、将来の価格を予測する分析手法です。
例えば、株価が過去の最高値(レジスタンスライン)に近づいた時や、移動平均線と呼ばれる平均的な価格の線にぶつかった時など、チャートが示す節目を参考に利食いのタイミングを判断します。一方、損切りは、直近の安値(サポートライン)を下回った時や、移動平均線を割り込んだ時など、「これ以上下がる可能性が高い」というサインが出たときに行います。
この方法は、市場の状況をより細かく見て判断できるというメリットがあります。しかし、チャートの読み方には慣れが必要です。最初は難しく感じるかもしれませんが、多くの投資家がこの手法を使っています。
利食いと損切りの注意点
早すぎると失敗する?利食いのワナ
利食いは利益を確定させる重要な行動ですが、そのタイミングを誤ると、かえって大きなチャンスを逃すことになります。特に注意すべきなのが「早すぎる利食い」です。これは、わずかな利益が出ただけで売ってしまうことで、その後の大きな値上がりを取りこぼしてしまうというワナです。
具体的な例を挙げてご説明します。 あなたが1株100円のA社株を1,000株購入したとしましょう。株価が順調に130円まで上昇しました。
【シナリオA:長期保有の場合】
1株100円だった株を保有し続け、130円になった時点で売却します。この場合の利益は30,000円です。(利益: (130円 – 100円)× 1,000株 = 30,000円)
【シナリオB:早すぎる利食いを繰り返した場合】
株価が105円になった時点で、利益が減るのを恐れて売却してしまいました。その後、株価はさらに上昇します。あなたは115円で再び購入し、120円でまた売却しました。(1回目の利益: (105円 – 100円)× 1,000株 = 5,000円+2回目の利益: (120円 – 115円)× 1,000株 = 5,000円)
この例のように、小さな利益を何度も確定させる「こまめな利食い」を繰り返した結果、最終的な利益は10,000円にしかなりませんでした。長期保有していれば得られたはずの30,000円という利益を、早すぎる利食いによって3分の1に減らしてしまったのです。
このように、早すぎる利食いは、一時的な安心感を得られる一方で、最大の利益機会を逃してしまうという大きなデメリットがあります。
投資で大きな成果を出すためには、「利は伸ばす」という原則を忘れてはなりません。
ロスカットで資産が減る「損切り貧乏」の正体
損切りもまた重要なルールですが、闇雲に損切りを繰り返すと、「損切り貧乏」に陥ってしまうことがあります。これは、小さな損失を何度も確定させてしまい、資産がジワジワと減っていく状態を指します。
著作『ロボット運用のプロが分析してわかった 最強の株式投資法』(著者:加藤 浩一)の中で、ある検証結果を紹介しています。
この検証では、日経225ETFで「10%の利食い、5%の損切り」というルールを15年間適用したところ、勝率は30.4%にとどまり、累計損益はマイナスになったそうです。(参照記事: ダイヤモンド・オンライン「損切りをデータで検証してみた!」)
この結果は、損切りはリスクを限定する一方で、そのタイミングを誤ると、かえって資金を減らす原因にもなることを示していると言えるでしょう。
また、著名な投資家であるローレンス・A・コナーズも、著書『コナーズの短期売買入門』の中で、損切りはタイミングが早ければ早いほど、成績が悪化するという検証結果を報告しています。そのため、損切りは長期的には損切り貧乏となる可能性がある「高コストの保険」として扱うべきだと主張しています。(参照書籍: 『コナーズの短期売買入門 トレーディングの非常識なエッジと必勝テクニック』)
以上のことから、多くの専門家たちが指摘する通り、損切りは、精神を安定させたり、運用資金を保全するために使えるものの、適切に行わなければお金を減らしてしまうかもしれないというマイナス面にも目を向けるべきです。