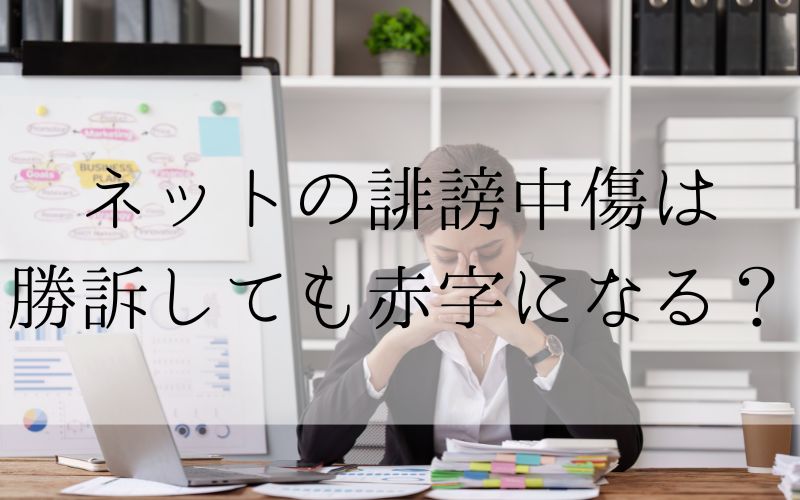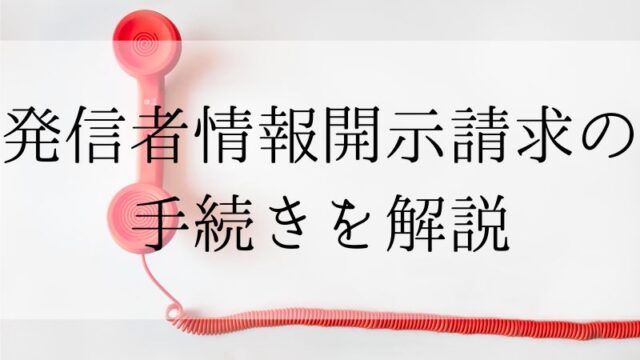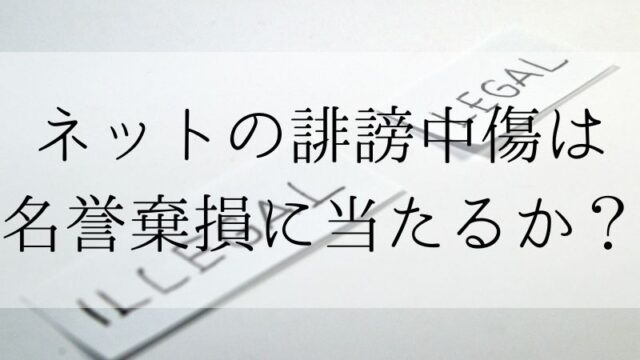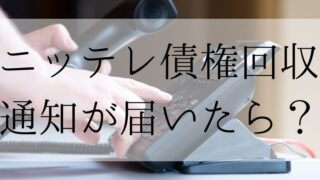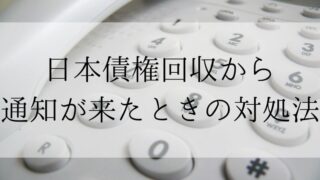インターネットで誹謗中傷されたら、どうしたらいいのでしょうか。裁判で勝てばすべて解決する、そう思っていませんか。実は、裁判に勝っても、かかった費用が原因で赤字になってしまうケースがあります。特に、匿名で投稿した人を特定するための調査費用は、非常に高額になるため、多くの被害者が泣き寝入りをしてしまうのです。
しかし、諦める必要はありません。近年、裁判所の考え方は変わりつつあります。古い判例にとらわれず、ネット中傷の特殊性を考慮した新しい判例が増えているのです。
この記事では、なぜ裁判費用が赤字になるのかという問題から、費用を全額請求出来た最新の判例まで、わかりやすく解説していきます。
目次
勝訴しても赤字になる?
Googleマップ虚偽口コミ問題の事例
誰もが想像する「裁判に勝てばお金がもらえる」という常識が、ネットの誹謗中傷では通用しない現実があります。例えば、産経新聞の報道では、Googleマップに嘘の口コミを書かれた歯科医院の事例が取り上げられています。この歯科医院の親子は、加害者を探し出すために弁護士へ依頼し、55万円という高額な費用を支払いました。しかし、裁判で認められた賠償額は、わずか26万4千円でした。これはつまり、裁判に勝ったのに、28万円以上もの大きな赤字になってしまったのです。一生懸命闘ったのに、損をしてしまう。これはネット中傷の裁判が抱える、とても大きな問題です。(グーグルマップで噓の口コミ、調査費多額で勝訴しても大赤字…ネット中傷裁判の構造的問題(産経ニュース))
なぜ費用が賠償額を上回るのか
なぜこのような、信じられないようなことが起きてしまうのでしょうか。その理由は、裁判で認められるお金の種類と金額にあります。裁判で被害者がもらえるお金は、主に「損害賠償」と「調査費用」に分かれます。しかし、裁判所が認める損害賠償は、世間一般の常識や過去の例から決まるため、金額には上限があります。
それに比べて、加害者を探すために弁護士に開示請求を依頼するための弁護士費用や、証拠をつかむための探偵への調査費用には決まった上限がありません。証拠を集めたり、加害者を探すのに苦労すればするほど、お金はどんどんかさんでいきます。
そのため、弁護士費用や調査費用を相手に負担させられないとなると、赤字になってしまうのです。この費用と賠償額の大きなギャップこそが、被害者を苦しめる大きな原因となっています。
調査費用に関する裁判所の考え方は?
最高裁が示した基本的な考え方は「一部負担」
そもそも、裁判でかかったお金が全額戻ってこないのはなぜでしょうか。実は、このルールには最高裁判所が示した古い考え方があります。最高裁判所昭和44年2月27日判決という昔の判例では、以下のように判示しています。
現在の訴訟はますます専門化され技術化された訴訟追行を当事者に対して要求する以上、一般人が単独にて十分な訴訟活動を展開することはほとんど不可能に近いのである。
従って、自己の権利擁護上、訴(訴訟)を提起することを余儀なくされた場合においては、一般人は弁護士に委任するにあらざれば、十分な訴訟活動をなし得ないのである。
そして現在においては、このようなことが通常と認められるからには、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものにかぎり、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである。
このように、判例では権利侵害等による被害回復のために訴訟手続が必要となった場合には一定程度の弁護士費用が損害として認められるとしています。ただし、弁護士の費用請求に関しては、負担額の「1割程度」しか認められませんと示されました。
これは、
- 日本の民事訴訟法は弁護士強制主義を採っていないため、弁護士を選任して行なうかは当事者が選べること
- 弁護士費用は訴訟費用には含まれていないこと
- 裁判をすること自体が、ある程度の費用がかかるものであること
と考えられていたからだと考えられます。そして、この考え方は今も裁判の場で根強く残っており、「弁護士費用や探偵による調査費用が必要だと認められたのは一部のみ」という判例が数多く出ているのです。
最近の判例では全額の請求が認められるケースも増加傾向に
では、どのような事件であっても、調査費用は一部のみしか認められないのでしょうか?それでは、調査費用で赤字になってしまうことを恐れてしまう人も増えてしまいます。
しかし、希望はあります。さきほどの最高裁判所昭和44年2月27日判決をよく読んでみると、「弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものにかぎり、不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである。」と判示されていることから、証拠の必要性や重要性が高い事案であれば、相当額の費用負担を相手に課すこともあり得るという読み方もできます。また、「現在の訴訟はますます専門化され技術化された訴訟追行を当事者に対して要求する以上、一般人が単独にて十分な訴訟活動を展開することはほとんど不可能に近いのである。」とも指摘しており、本人で手続きをすることの困難性が高い場合には、不法行為と費用の相当因果関係が認められやすいと考えられます。
また、匿名で簡単に誹謗中傷ができてしまうネットの世界では、そもそも加害者の情報を手に入れること(発信者情報開示請求といいます)が、権利行使のために不可欠だと言えます。そのため、近年の判決の中には、「発信者情報開示請求等に関する費用は、この調査費用は、損害賠償請求を行うために必要な費用である」という判断基準が示されているものも多数あります。
以上のことから、弁護士費用や調査費用が訴訟追行、損害賠償請求のためは必要性が高いことや、被害者本人で手続することが困難である事情があれば、相当因果関係は調査費用のすべてについて認められる可能性があるわけです。
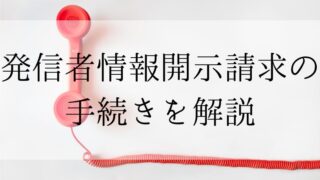
弁護士費用や調査費用の全額を認めた具体的な判例
実際に弁護士費用や調査費用の全額を損害として認めた判決は、増え続けています。これらの判決は、ネット中傷の被害者が泣き寝入りすることなく、正当な費用を取り戻せる可能性を示しています。これは被害者の負担を軽くし、救済に前向きな姿勢を示していると言えるでしょう。時代に合わせた裁判所の新しい考え方が、少しずつ被害者の助けになっているのです。
東京高等裁判所令和2年1月23日判決
東京高等裁判所令和2年1月23日判決(令和元年(ネ)第3668号、令和元年(ネ)第4142号)(判例タイムズ1490号109頁)(銀行法務21 880号71頁)では、東京高等裁判所は、インターネット上の匿名投稿による名誉毀損について、発信者情報の開示に要した費用の全額を、不法行為と相当因果関係のある損害として認めました。
判決文には、費用全額を認めた主な理由が二つ挙げられています。
まず、インターネット上の匿名投稿では、まず加害者の身元を特定しなければ、損害賠償を請求することすらできません。そのため、発信者情報開示は、被害者が正当な権利を行使するために必要不可欠な手続きであるという点です。また、裁判所は、被害者が弁護士に支払った費用が「不相当に高額である」とは認めませんでした。支払われた費用が合理的であり、その一部だけを損害として認めるべき特段の事情も見当たらないと判断されました。
令和3年5月26日東京高等裁判所判決
令和3年5月26日東京高等裁判所判決(令和2年(ネ)第4412号)( LLI/DB 判例秘書登載)では、誹謗中傷を行った加害者を特定するために、発信者開示手続きを行いましたが、その調査費用88万5,600円の全額を、名誉毀損による損害として認めました。
その理由としては、まずは必要性です。匿名投稿の加害者を特定するためには、数段階にわたる専門的な手続きが不可欠でした。そのため、この調査費用は、損害賠償請求を行うためにどうしても必要であった費用だと判断されました。
また、通常の一般人が、複雑な手続きを自力で行うことは非常に困難であるという点も重視されています。名誉毀損という被害を迅速に解決するため、専門知識を持つ弁護士に依頼することは「ごく当然であり、やむを得ないもの」と認められました。
これらのことから、裁判所は調査費用の全額が、名誉毀損行為と直接的な因果関係のある損害であると結論づけています。
東京地方裁判所令和6年9月12日判決
また、東京地方裁判所令和6年9月12日判決(令和5年(ワ)第30002号 )(LLI/DB 判例秘書登載)では、探偵による不倫調査の費用の全額を本件の不法行為と相当因果関係のある損害と認め、全額を認容しています。
東京地裁は「被告の共同不法行為者や不法行為の態様を知り、被告及びその共同不法行為者に対して損害賠償請求をするために必要な調査であったと認められるから、探偵の調査費用合計59万2490円について、本件の不法行為と相当因果関係のある損害と認める」という判断を下しました。こちらもやはり、証拠の必要性が認められたことが大きいと考えられます。
まとめ
泣き寝入りしないための知識
ネットの誹謗中傷は、とても身近な問題です。もしかしたら、あなた自身やあなたの身近な人が被害にあうかもしれません。そんな時、「裁判に勝っても赤字になるのでは?」と不安に思うかもしれません。しかし、ご安心ください。確かに以前は、加害者を見つけるための「調査費用」が十分に認められず、泣き寝入りせざるを得ないケースもありました。
でも、時代は変わっています。近年の裁判所は、ネット中傷の特殊性を理解し、被害者が正当な費用を取り戻せるように、新しい判断基準を示しているのです。これらの新しい判例は、調査費用を「被害回復に不可欠なもの」として、その全額を損害として認めています。つまり、適切な知識を持っていれば、泣き寝入りする必要はなくなったのです。
全額賠償を認めた判例から学ぶこと
実際に調査費用の全額が認められた判例を見てみると、いくつかの大切なことがわかります。まず、弁護士に依頼することは「ごく当然で、やむを得ないもの」だと裁判所が認めている点です。複雑な手続きを一般の人が一人で行うのは難しいため、専門家を頼ることは当然の行為だと判断されたのです。
次に、調査費用が不当に高額でないと認められている点です。これにより、被害者が支払った費用が、そのまま賠償として認められています。これらの判例は、被害者が泣き寝入りせずに済むという大きな希望を与えてくれます。
もしあなたが被害にあったとしても、諦めずに専門家へ相談し、正当な権利を守るための行動をしてください。