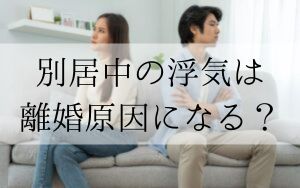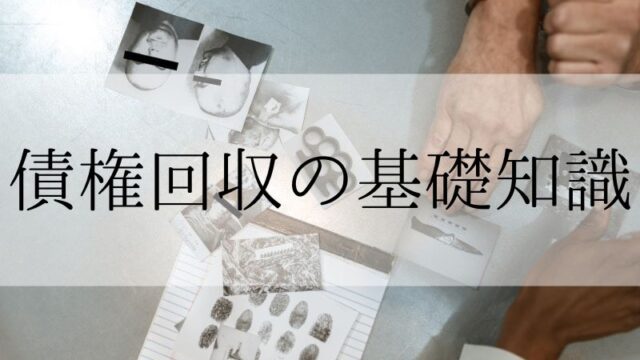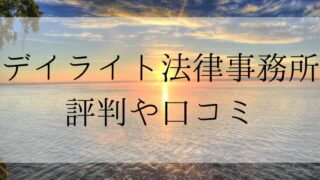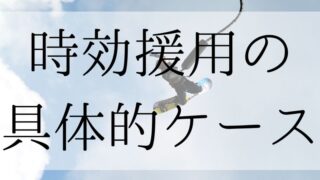民事裁判においては「証拠」がどう扱われるのかは、裁判の結果を大きく左右する重要なポイントです。
裁判では、裁判官がどんな証拠を採用するかは自由に判断できます。これを「自由心証主義」と呼びます。とはいえ、どんな方法で集めた証拠でも許されるわけではありません。もし、反社会的な方法を使ったり、法律に違反する方法で集められた証拠を無制限に採用しては、裁判所が違法行為を推奨していることとなり、司法の公正さを損なう恐れがあります。
そのため、裁判所では自由心証主義の修正として、一定の違法に収集された証拠を排除することを認めています。これを「違法収集証拠排除法則」と言います。
とはいえ、どんな時に違法だと判断されるのか、その線引きはとても難しいものです。そこで、この記事では、民事裁判における証拠の基本的なルールである自由心証主義と、違法な証拠が排除される「違法収集証拠排除法則」について、やさしく解説します。過去の裁判例も交えながら、分かりやすくその内容を紹介していきます。
自由心証主義と違法収集証拠排除法則
民事裁判では、「自由心証主義」という原則に基づいて、裁判官が証拠を評価し、事実を認定します。しかし、この原則には例外があり、「違法収集証拠排除法則」によって、不適切な方法で集められた証拠は裁判で使えない場合があります。
自由心証主義とは?
民事裁判は、個人間の紛争を解決する場です。そのため、証拠の収集方法が厳しく制限される刑事裁判とは異なり、民事訴訟法には「証拠能力」、つまり特定の資料を証拠として使えるかどうかを制限する明確な規定がありません。
民事裁判では、当事者が公権力を行使して強制的に証拠を集める手段がないため、違法な証拠収集を強く抑止する必要性が低いと考えられています。むしろ、裁判官が自由に証拠を評価し、判断を下す方が、事件の「真実発見」につながるとされています。
この考え方に基づき、民事訴訟法第247条で定められているのが「自由心証主義」です。この原則の下では、裁判所は提示された証拠を自由に採用したり、排除したりする権限を持ちます。
自由心証主義の例外:違法収集証拠排除法則
しかし、どのような方法で集められた証拠でも全て有効とすると、犯罪的な行為によって得られた証拠まで裁判で認められてしまうことになりかねません。これは、司法の公正さを損なう恐れがあります。
そこで、裁判例を通じて形成されたのが「違法収集証拠排除法則」という考え方です。これは、特定の条件下で違法に収集された証拠の採用を制限するものです。
証拠能力を否定する程度、つまり民事訴訟における「違法収集証拠の証拠能力の採否」については、様々な理由付けがなされています。判例では、人格権侵害に着目するものや、信義則(信義誠実な訴訟追行に反するかどうか)に着目するもの、問題となっている証拠の重要性・必要性、審理の対象事実の性格と収集行為の態様、被侵害利益とを総合的に考慮して判断する、という見解もあります。ただし、「証拠の収集態様が反社会的であることや違法性の程度が重大な場合には、証拠能力を否定し得る」という点では概ね一致していると言えるでしょう。
民事訴訟における違法収集証拠の証拠能力を判断する際ポイントとしては、様々な要素が総合的に考慮されます。
- 証拠収集の態様が反社会的かどうか: 例えば、プライバシーを著しく侵害する盗撮や盗聴など、社会的に許容されない方法で証拠が収集された場合です。
- 違法の程度が重大かどうか: 証拠収集行為が、法律に違反する度合いが非常に高いかどうかを指します。
- 証拠の必要性・重要性: その証拠が、事件の事実認定においてどれほど重要で、他に代替手段がないかどうかが考慮されます。
- 被侵害利益の重要性: 証拠収集によって侵害された個人の権利や利益(プライバシー権など)の重要性も判断材料となります。
これらの要素を総合的に判断し、特に「証拠の収集態様が反社会的である」場合や「違法の程度が重大である」場合には、証拠能力が否定される可能性が高いとされています。
違法収集証拠の実際の判例
違法収集証拠の代表格ともいえる、対話者の許可を取らず無断で録音された音声テープの事例では、東京高裁昭和52年7月15日判決・判時867号60頁がリーディングケースとされています。
本事件では、無断で録音された音声データの証拠能力について「その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によつて採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである」としています。
ただし、上記判決では、無断で録音された音声データを「単に不知の間に録取したものであるにとどまり、いまだ同人らの人格権を著しく反社会的な手段方法で侵害したものということはできないから、右録音テープは、証拠能力を有するものと認めるべき」として証拠能力を肯定しています。
前項でもご紹介した通り、「著しく反社会的で違法性の程度が高い場合には証拠能力を否定する。一方、違法性があれど、反社会性や被侵害利益の重大性がさほど大きくない証拠については証拠能力を認める」という点を明確にしていると言えるでしょう。
このように、無断で録音をしていることはであれば、違法収集証拠とはならず、証拠能力を認める判決もあります。(盛岡地判昭和59年8月10日、東京地判昭和46年4月26日、最決平成12年7月12日など)東京高裁昭和52年7月15日判決同様の立場を支持していると言えます。
証拠能力が認められた民事裁判例
民事裁判における「自由心証主義」は、裁判官が自由に証拠を評価し、事実を認定する原則です。しかし、この原則には「違法収集証拠排除法則」という例外があり、違法な方法で集められた証拠は原則として認められません。
ここでは、一見すると違法に収集されたように見えながらも、具体的な事情を考慮して証拠能力が肯定された判例を3つご紹介します。
置き忘れられた日記のケース(大判昭和18年7月2日)
このケースでは、養子である被告が、養父である原告の自宅に日記を置き忘れ、それを原告が証拠として提出しました。
裁判所は、この日記を証拠として認めました。
他人の私的な日記とはいえ、相手方が自宅に置き忘れたものであり、その後の取得に強要や不法行為が直接伴わないなど、取得行為が反社会的とは言えず、許容されると解釈されたものと考えられます。
会議室に置き忘れられた手帳のケース(名古屋高決昭和56年2月18日)
このケースでは、会社の人事部長が会議室に置き忘れた手帳のコピーが、労働者側によって証拠として提出されました。手帳自体は一度持ち去られたものの、後に返還されています。
裁判所は手帳のコピーが手に入ったというだけでは、直ちに違法行為とは言えないことや、手帳の内容が「職務上の出来事や行事予定」であり、個人の私生活に関わるものではなかったことを重視し、証拠能力を肯定しました。
東京高裁昭和52年7月15日判決でも示された通り、違法収集証拠となるか否かは、主に反社会的方法を用いて人格権侵害を伴う証拠収集を行ったかどうかで判断されます。
そして、職務上の情報が記載された手帳であれば、そのプライバシー侵害の程度は低く、人格権侵害を伴うとまでは言えないと判断されたということが考えられます。また、手帳が「置き忘れられた」という状況も、悪意のある盗聴や盗撮のような積極的な違法行為とは異なるため、著しく反社会的な方法にもあたらないとして、評価されたと考えられます。
郵便受けから持ち出された手紙のケース(名古屋地判平成3年8月9日)
これは、妻が夫の不倫相手の住居の郵便受けから手紙を持ち出して証拠として提出したケースです。マンションの郵便受けの中からTに無断で持ち出して開披し、隠匿していた信書であることが認められ、夫婦間の一般的承諾のもとに行われる行為の範囲を逸脱して取得した証拠であることから、通常であれば、他人の郵便物を無断で持ち出す行為は違法性が高いと判断されるでしょう。
しかし、裁判所は「夫が不倫相手のために用意した住居であったこと。夫が、不倫相手との関係を妻に隠していなかったこと。現在も不倫相手が夫らと同居し、共に事業を営んでいること」などから、これらの事情を総合的に考慮した結果、裁判所は「証拠収集の方法、態様は、民事訴訟において証拠能力を否定するまでの違法性を帯びるものではない」として、証拠能力を肯定しました。
この判例は、証拠収集の違法性を判断する際に、当事者間の関係性や背景にある事情が重要になることを示しています。夫婦という特殊な関係性や、不倫相手が関係を隠していなかったという事情が、証拠収集の違法性の評価を軽減させたと推測されます。
単に「他人の郵便物を勝手に取った」という形式的な事実だけでなく、実質的な状況を重視した判断と言えるでしょう。
証拠能力が認められた民事裁判例のまとめ
これらの判例からわかるように、これらの判例は、裁判所が証拠収集の経緯や証拠の内容、関係性などを総合的に判断していることを示しています。民事裁判における違法収集証拠の判断は、単純に「違法行為があったかどうか」だけで決まるわけではないということです。
証拠収集の態様、証拠の内容、被侵害利益の性質、そして当事者間の関係性など、様々な要素を総合的に考慮して、その証拠を裁判で使うことが司法の公正さや真実発見の目的に照らして適切かどうかが慎重に判断されていると言えるでしょう。
証拠能力が否定された民事裁判例
民事裁判では、「自由心証主義」という原則に基づき裁判官が証拠を評価しますが、「違法収集証拠排除法則」の例外が適用され、特定の条件下では証拠能力が否定されることがあります。ここでは、プライバシー侵害や訴訟上の信義則に反すると判断され、証拠能力が否定された2つの判例をご紹介します。
夫婦別居中に不法侵入して盗み出した弁護士との打ち合わせメモのケース(東京地判平成10年5月29日)
この判例は、夫婦が別居した後、妻が夫の住居に不法に侵入し、夫が弁護士との打ち合わせ内容をメモした大学ノートを盗み出し、それを証拠として提出したケースです。
裁判所はノートが「依頼者と弁護士との間でのみ交わされる」極めて秘匿性の高い文書であり人格権的利益の侵害が著しいことや、妻の夫の住居に「不法に侵入」し「密に入手」したという証拠収集方法の悪質性が重視されました。
これらの行為が「強い反社会性」を持ち、民事訴訟法第2条の信義誠実の原則に反すると判断され、このノートの証拠能力を否定しました。
ハラスメント防止委員会の非公開審議を無断録音したケース(横浜地判平成26年(ワ)第57号、その控訴審判決)
この事案では、大学職員が、自身が受けたハラスメントの申立てに関するハラスメント防止委員会の非公開審議を無断で録音し、その録音データを証拠として提出しました。
原審・控訴審ともに、この録音データの証拠能力を否定しました。
委員会が「非公開」であり、録音しない運用がされている場で無断録音されたことから、違法性が極めて高いと判断されました。また、ハラスメントというデリケートな情報を扱うため、関係者のプライバシーや委員会の守秘義務が重視され、その秘密性を侵害する行為は訴訟上の信義則に反するとされました。さらに、録音内容の証拠価値が乏しかったことも排除の要因となりました。
証拠能力が否定された判例のまとめ
これらの判例からは、一定の場合に、裁判所が証拠を排除する姿勢を示しています。
まず、証拠能力が否定されるのは、主に証拠収集の違法性が極めて高く、その行為が個人の重要な権利(プライバシーや秘密性)を著しく侵害する場合です。また、その証拠が訴訟上の「信義誠実の原則」に反すると判断される場合も排除の対象となります。具体的には、不法侵入を伴う盗難によって得られた秘匿性の高い文書(弁護士との打ち合わせメモなど)や、プライバシーや秘密性が高く保護されるべき非公開の場での無断録音(ハラスメント委員会の審議など)がこれに該当します。
また、証拠の重要性なども副次的に評価されていると言えるでしょう。ハラスメント防止委員会の非公開審議を無断録音したケースでは、証拠としての価値が低いことから、証拠能力を否定しており「証拠として採用することが適切かどうか」の基準に、証拠価値の高さや立証への必要性なども考慮されているものと思われます。
結論として、証拠の内容の秘匿性、収集方法の悪質性、そして侵害された利益の重要性が総合的に考慮され、証拠として用いることが司法の公正さを損なうと判断される場合には、証拠能力が否定されると考えてよいでしょう。