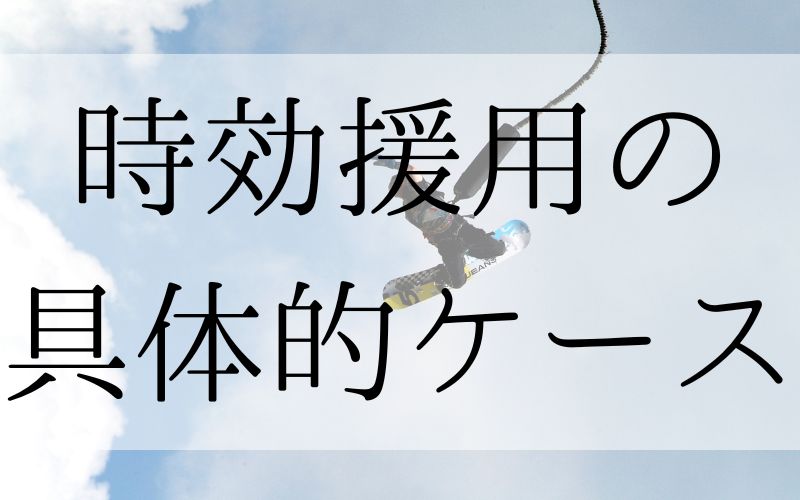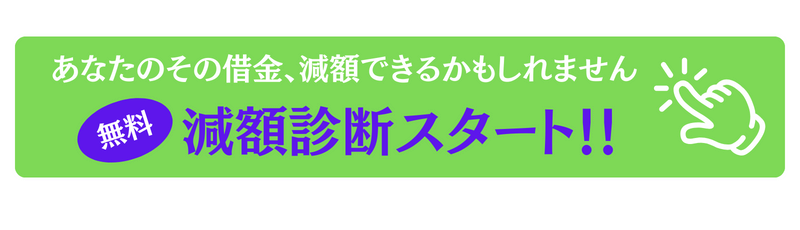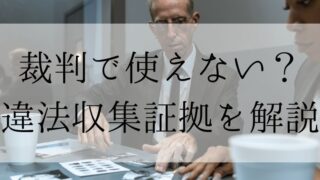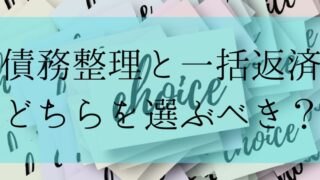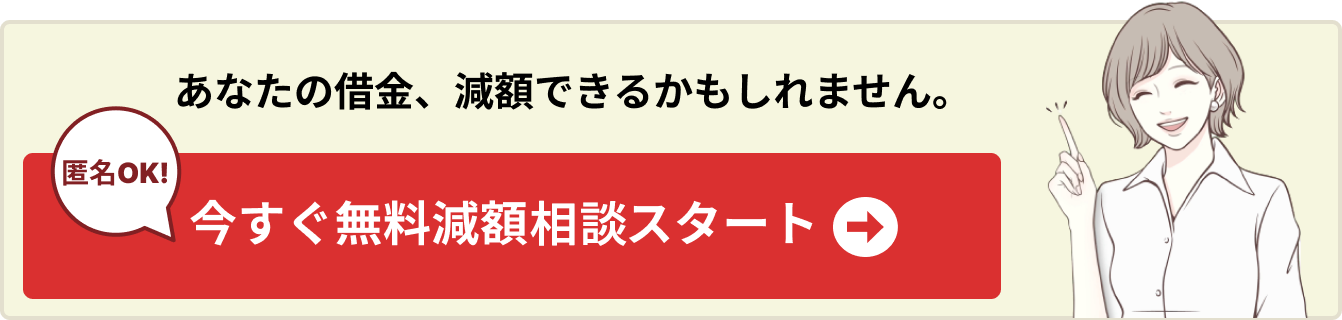「もう時効が過ぎたから大丈夫」と思っている方も多いでしょう。けれども実は、時効が成立していても裁判を起こされることがあります。驚かれるかもしれませんが、これは現実に起きていることです。
しかも、裁判を放っておくと、大きな損をするかもしれません。支払う必要のないお金を、知らないうちに支払わされるようなこともあるのです。だからこそ、届いた書類をしっかり確認し、正しい対応をすることがとても大切です。
たとえば、訴状や支払督促が届いた場合、ある手続きを行うことで借金の返済義務をなくすことができる可能性があります。その手続きのことを「時効援用(じこうえんよう)」といいます。聞き慣れない言葉かもしれませんが、内容はそれほど難しくありません。
この記事では、裁判や支払督促が届いたときには時効援用ができるかについて、わかりやすく解説します。また、うっかり対応を誤ることで時効が使えなくなるケースについても紹介していきます。
借金に悩み続けてきた方こそ、今が行動のチャンスです。不安を少しでも軽くするためにも、まずは正しい知識を身につけていきましょう。
目次
こんなケースでも時効が使える?
訴状が届いた場合(裁判)の時効援用の方法
長年にわたって借金の返済をしていない場合、時効の成立期間が過ぎていることから「もう裁判されることはない」と考えている債務者もいるかもしれません。しかし、中には時効期間経過後でも裁判を起こしてくる会社も存在するのです。
このように時効期間経過後に裁判を起こされた場合、債務者は裁判の手続きの中で「時効の主張をする」ことになります。つまり、時効が成立していることを裁判所に明示し、債務の消滅を主張するのです。
多くの場合、時効が成立していれば裁判は取り下げられることになります。債権者としても、時効の主張に対抗するのが難しいと判断すれば、裁判を継続することは得策ではないからです。
ただし、裁判を放置してはいけません。時効の主張を行うためには、答弁書にその旨を記載し、口頭弁論期日までに提出する必要があります。裁判所から送られてくる書類を無視したり、出廷しなかったりすると、債務者の主張が認められず、不利な判決が下される可能性があるのです。
したがって、時効期間経過後に裁判を起こされた場合は、速やかに弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。時効の主張を適切に行うことで、債務の消滅を認めてもらい、裁判を有利に進めることができます。

支払督促が届いた場合の時効援用の方法
訴状の他に、支払督促が届くこともあります。支払督促は民事訴訟法第382条以下で定められた簡易な裁判手続きですが、同法396条ではこれが確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有するとされており、裁判と同様の効果があるとされています。そのため、、通常の裁判と同様に放置してはならず、債務者は適切な時効援用の手続きを取る必要があります。
支払督促を受け取ったら、2週間以内に異議申立書を作成し、裁判所に提出しなければなりません。この異議申立書を提出することで、支払督促の手続きから通常裁判に移行します。
通常裁判に移行すると、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所から呼出状と答弁書催促状が送られてきます。この答弁書に「時効を援用する」旨を記載し、裁判所と相手方に提出することが重要です。
債権回収会社や弁護士事務所から督促状が届いても時効援用で解決可能
債権回収会社や、弁護士事務所から督促や通知、取り立て等が来た場合、債務の消滅時効の援用で、返済をなくすことができる可能性があります。
✅消費者金融や銀行カードローンなどの借り入れ
✅クレジットカードのキャッシング、ショッピング
✅家賃
✅携帯電話料金
こうした様々な支払いの滞納・未払いで、消滅時効の援用ができる場合があります。
しかし、督促状や催促状、和解提案書などには、「期日までにご連絡ください」という文言が入っていることがありますが、これらの言葉に惑わされてはいけません。安易に自分で連絡してしまうと、時効で消せるはずの返済が消せなくなってしまう恐れがあります。
自分では自覚していなくても、「債務承認」によって時効が中断してしまうことがあるのです。債権者との会話の中で不用意に債務を認めたり、返済を約束したりすると、時効の援用ができなくなる危険性があります。(民法第152条)
したがって、支払督促や督促状が届いた場合は、まず冷静に対応することが大切です。時効の成立要件を確認し、弁護士や司法書士などの専門家に相談して、適切な時効援用の手続きを取ることが賢明でしょう。
時効が認められない代表例|時効の完成猶予・更新事由
裁判上の請求や支払い督促
借金の返済をせずに引っ越しをしてしまうと、債権者からの督促状などが届かなくなり、請求の有無がわからなくなってしまいます。そのような状況が長期間続くと、債権者は裁判所に「支払督促」や「訴訟」を申し立てることがあります。
裁判所から送られてくる支払督促状や訴状が手元に届かない場合、自分が支払督促や訴訟の被告になっていることに気づかないことがあります。「届かないんだから大丈夫でしょ?」と思うかもしれませんが、それは大きな間違いです。
債権者が「公示送達」という原告の意思表示を被告に到達させる申立てを行えば、被告である債務者に支払督促や訴訟の意思が伝えられたとみなされ、手続きが進んでしまうのです。
訴訟提起されてしまった時点で、時効の進行は停止します。債権者が裁判上の請求や支払督促を行うと、手続き中は時効の完成猶予となり、確定判決などで権利が確定すれば時効が更新されてしまいます。
ただし、手続きが取下げによって終了した場合は、取り下げから6ヵ月間の完成猶予となります。また、裁判外の催告書や督促状のような請求については、請求から6ヵ月間の完成猶予になります。
金融業者にとって督促はあくまで臨時的な対処なので、この6ヵ月の間に法的手続きを行ってくると考えておくべきでしょう。
差押え、仮差押え、仮処分
差し押さえとは、借金を返済せずに滞納し続けている債務者の財産を、債権者が法律に基づいて強制的に換金・処分し、借金の回収を行う手続きのことです。これは「強制執行手続」の一つであり、債務者が滞納している借金を法的に回収する方法です。
差し押さえの手順としては、まず債権者が債務者の財産を処分できないようにします。その上で、その財産を取り立てたり、競売で換価する手続きを行い、借金の回収を図ります。
債権者が差し押さえを行うには、「債務名義」を取得し、裁判所を通して強制執行の手続きを進める必要があります。
強制執行による差押えは、時効に関して特別な扱いがあります。差押えの手続き中は時効の完成猶予となり、差押えが終了すると時効が更新されます。ただし、取り下げなどで差し押さえ手続きが終了した場合は、取り下げから6ヵ月間の完成猶予となります。
また、仮差押えと仮処分については、手続き中および手続終了から6ヵ月間が完成猶予の期間となります。
差し押さえは、債務者にとって非常に大きな影響を与える手続きです。財産を失うだけでなく、信用情報にも傷がつき、今後の経済活動に支障をきたす可能性があります。
債務者による債務の承認
債務の承認とは、債務者が債権者に対して、借金の存在や返済義務を認めることを指します。借金には消滅時効という制度があり、債権者が借金の回収権利を行使しないまま、最終取引日から一定期間(5年もしくは10年)が経過すると、その権利が消滅します。
通常、消滅時効が成立すれば、時効の援用手続きを行うことでその借金の返済義務はなくなります。
しかし、最終取引後に債務を承認してしまうと、たとえ規定の期間が経過して時効の援用手続きを行ったとしても、借金の支払い義務は消滅しないのです。
時効の成立には「最後に返済した日」が重要な基準となります。しかし、単に忘れていただけで、時効の成立前に返済を行ってしまうケースが数多く見られ、時効援用失敗の大きな要因となっています。これが「債務承認」です。
債権者からの電話や訪問で「返済します」「〇〇日までに返します」「〇〇円ずつ返します」などの発言をしてしまうと、「債務が存在することを認めた」「返済義務があると認めた」「返済を約束した」と主張されてしまう危険性があります。
債務承認は、時効の援用を妨げる大きな障害となります。たとえ少額でも、時効成立前に返済をしてしまうと、時効の起算点が更新されてしまうのです。また、債権者との会話の中で不用意に返済を約束したり、債務の存在を認めたりすることも、債務承認とみなされる可能性があります。
したがって、時効の援用を検討している場合は、債務承認に十分注意する必要があります。債権者からの連絡には慎重に対応し、安易に返済を約束したり、債務を認めたりしないことが大切です。
裁判で判決が出ると時効はさらに10年延びる
判決で確定した権利の消滅時効については、民法第169条に特別な規定があります。この規定では、「法律で十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は十年とする。」とされています。(民法第169条)
つまり、本来は5年間で時効が成立する借金であっても、裁判を起こされて判決が出た場合、その時点から時効期間が10年に延長されるのです。これは、時効の更新や完成猶予に当たる事由がない場合でも適用されます。
債務者の自宅に裁判所からの通知が届いていない場合でも、債権者は「公示送達」という方法で裁判を起こすことができます。公示送達とは、裁判所の掲示板に呼出状を掲示することで、法律上の送達とみなす手続きです。
したがって、債務者が知らない間に裁判を起こされ、判決が出ていたというケースも起こり得ます。
このような事態を避けるためにも、借金問題には慎重に対応する必要があります。
そもそも、借金の債務者には返済義務があり、債権者は当然の権利として本来回収すべき金額を回収しようとします。債権者は様々な手段を用いて時効の成立を阻止しようとしてくるため、専門家に相談することが賢明です。
また、訴訟提起された場合、被告側が答弁書の提出、出廷、異議の申し立てを行わなければ、原告の請求内容でそのまま判決が下されてしまいます。判決が確定すると、時効期間はそこから10年に延長されるのです。
さらに、判決書は「債務名義」と呼ばれ、給与や口座の預貯金に対する差押えを可能にする強力な武器となります。
以上のように、判決で確定した権利の時効期間は10年に延長され、債務者にとって非常に不利な状況となります。借金問題を抱えている場合は、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な債務整理の方法を検討することが大切です。