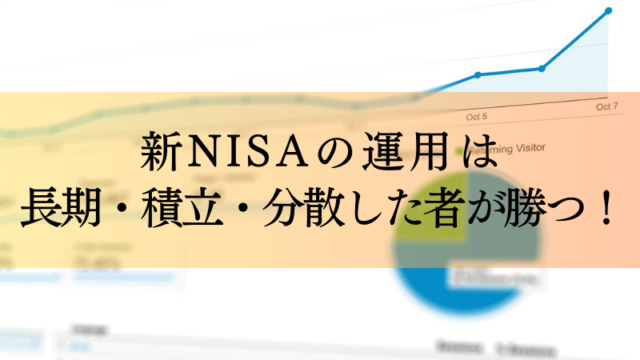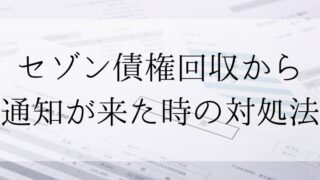「株を始めてみたいけれど、どんな株を買えばいいの?」そう思っている方も多いのではないでしょうか。株にはたくさんの種類がありますが、大きく分けると「高配当株」と「高成長株」の2つがあります。
高配当株は、株を持っているだけで定期的にお金がもらえる「お小遣い」のようなものです。これに対して、高成長株は、大きく伸びることで株の値段が上がり、買った時よりも高く売れることで利益を得るものです。まるで、宝探しのようなワクワク感がありますね。このように、投資の目的によって、選ぶべき株は全く違ってきます。
でも、「どっちがいいの?」「自分に合うのはどっち?」と迷ってしまいますよね。実は、高配当株と高成長株には、それぞれ良い点もあれば、気をつけなければいけない点もあります。
この記事では、そんな高配当株と高成長株について、実在の企業を例として交えてわかりやすく説明していきます。具体的な企業の例を挙げて、それぞれの特徴やメリット、そして注意すべき点までをくわしく解説します。この記事を読めば、あなたにぴったりの株を見つけるためのヒントが必ず見つかります。ぜひ最後まで読んで、ご自身の投資の参考にしてください。
目次
高配当株と高成長株、それぞれの特徴とは?
高配当株は「インカムゲイン」で儲ける
あなたがアルバイトをして、毎月決まったお給料をもらっているとします。高配当株投資は、まさにその「お給料」に似ています。企業が稼いだ利益の一部を、株主へ配当金として定期的に分配する株式が、高配当株です。
たとえば、株価1,000円の株式を100株買ったとしましょう。この会社が1株あたり年間30円の配当を出すなら、毎年3,000円の現金が手に入ります。このように、株を保有することで定期的に得られる利益をインカムゲインといいます。
配当利回りが高い銘柄は、投資した金額に対して、より多くの現金を受け取ることができます。一般的には、配当利回りが3%以上のものが高配当株と呼ばれることが多いです。しかし、配当は企業の業績によって変わる可能性があることを覚えておいてください。
高配当株の運用例【日本たばこ産業(コード:2914)】

実際に高配当株で有名な日本たばこ産業(JT)に投資した場合の例を見てみましょう。JTはたばこ事業で安定した経営を続けており、高配当株として非常に人気があります。
たとえば、2023年1月4日にJTの株式を100株購入し、1年間保有した場合の利益は以下のようになります。
| 項目 | 詳細 | 利益額 |
|---|---|---|
| キャピタルゲイン (値上がり益) | 2024年1月4日の売却価格 3,740円 -2023年1月4日の購入価格 2,609円 =1,131円 (1,131円 × 100株) | 113,100円 |
| インカムゲイン (年間配当金) | 中間配当94円 + 期末配当94円 =188円 (188円 × 100株) | 18,800円 |
| 合計利益 | 113,100円 + 18,800円 | 131,900円 |
このように、購入金額約26万円(2,609円×100株)に対して、合計で13万円以上の利益を得ることができました。特に、株価が大きく変動しない中でも、安定した配当金収入が得られるのが大きな魅力と言えます。
高成長株は「株価上昇」で資産を増やす
あなたは今、新しいゲームソフトや流行のファッションアイテムに興味があるかもしれません。高成長株は、まさに新しい技術や流行のサービスで、急激に売上を伸ばしている企業のことです。
これらの企業は、得た利益のほとんどを、さらに事業を拡大するための研究開発や設備投資に回します。そのため、配当金はあまり出さないのが特徴です。その代わりに、会社の価値がどんどん上がり、それに伴って株価も大きく上昇します。
株を買った時よりも高い値段で売ることで得る利益をキャピタルゲインといいます。高成長株に投資する最大の魅力は、このキャピタルゲインによって、投資したお金が何倍にもなる可能性がある点です。
新しいサービスや製品で、一気に市場を席巻するような企業は、高成長株の代表例です。
成長株の運用例【ジャパンエンジンコーポレーション(コード:6016)】

実際に高成長株の代表例であるジャパンエンジンコーポレーションに投資した場合の例を見てみましょう。同社は2023年に株価が大きく上昇した銘柄として知られています。
たとえば、2023年1月4日にジャパンエンジンコーポレーションの株式を100株購入し、1年間保有した場合の利益は以下のようになります。
| 項目 | 詳細 | 利益額 |
|---|---|---|
| キャピタルゲイン (値上がり益) | 2024年1月4日の売却価格 7,290円 -2023年1月4日の購入価格 1,222円 =6,068円 (6,068円 × 100株) | 606,800円 |
| インカムゲイン (年間配当金) | 期末配当28円 + 中間配当30円 =58円 (58円 × 100株) | 5,800円 |
| 合計利益 | 606,800円 + 5,800円 | 612,600円 |
この例では、購入金額約12万円(1,222円×100株)に対して、1年間で60万円以上もの利益を得ることができました。このように、高成長株は短期間で大きなリターンを生み出す可能性があるのです。
高配当株と高成長株、それぞれのメリットは?
高配当株のメリットは、景気変動に左右されにくい安定感
高配当株の最大のメリットは、何といっても安定性です。たとえ市場全体の株価が下がっても、企業が安定した利益を出し続けている限り、配当金は継続して支払われる傾向にあります。
そして、この安定性を最も象徴するのが、連続増配という企業の姿勢です。例えば、日本を代表する総合化学・日用品メーカーである花王(4452)は、36期連続増配(1990~2025年)を達成しています。同社の年間配当額は増配を始めた1990年頃から21倍以上に増加しています。このように、株主還元への強い意思と安定した経営基盤があるため、高配当株投資の代表例として挙げられます。
花王の事例は、配当の安定性がいかに投資家の心理的支えになるかを示す好例です。
1990年以降、日本経済はバブル崩壊、ITバブル崩壊、そしてリーマンショックや東日本大震災といった大規模な経済的・社会的危機を経験してきました。これらの時期には、多くの企業の株価が大幅に下落し、減配や無配に追い込まれるケースも少なくありませんでした。
しかし、花王はこうした激動の時代を通じても、配当を減額することなく、増配を続けてきました。これは、同社が安定した収益基盤と強固な経営体制を確立していることの確固たる証拠であり、投資家にとっては長期的な投資をしやすいという安心材料となります。

高成長株のメリットは、資産が何倍にもなる可能性
高成長株の最大の魅力は、やはり圧倒的なリターンです。まだ市場にあまり知られていない若い企業が大きく成長すると、株価が数倍、数十倍になることも珍しくありません。このような夢のようなリターンは、テンバガー(10倍株)という言葉で表現されます。
過去には、ファーストリテイリング(ユニクロ)やキーエンスといった企業が、このテンバガーを達成しました。
ファーストリテイリングは、ユニクロのビジネスモデルで急成長を遂げ、テンバガーを達成しました。1997年4月に店頭公開した際の株価は1株あたり2,100円でしたが、ユニクロのフリースブームが到来した1999年には、株価は20,000円を超え、わずか2年ほどで10倍近い成長を遂げました。
キーエンスは、工場自動化を支えるセンサーなどの精密機器を開発する企業で、その圧倒的な利益率と独自のビジネスモデルで知られています。リーマンショック後の2009年3月には、株価は約13,000円の安値をつけていましたが、その後、グローバルな工場自動化の需要拡大を背景に株価は上昇を続け、約10年後の2019年1月頃には130,000円を超え、10倍株となりました。
これらの事例からわかるように、高成長株の特徴は、ビジネスモデルの転換やスキームチェンジを伴うことが多いというものです。このような時代を先取りする動きに着いていくことで利益を得られるという意味では、「アーリーアダプター」には有利かもしれません。
高配当株と高成長株の弱点とは?
高配当株のデメリットは、「減配」と「成長の限界」
高配当株には注意すべき点もあります。まず、一番の懸念は減配リスクです。
減配とは、企業が業績悪化などの理由で、配当金を減らしたり、支払いを停止することです。高配当株の魅力は配当金にあるため、減配が決まると、株価も大きく下がることがよくあります。
また、安定している企業は、すでに成熟しており、株価の大きな上昇は期待しにくいです。そのため、キャピタルゲインはあまり見込めないかもしれません。高配当という理由だけで投資すると、知らぬ間に業績の悪い企業に手を出してしまう「バリュートラップ」に陥る可能性があります。
高配当株投資のデメリットとして挙げられる「減配」と「成長の限界」について、日産自動車の事例を見てみましょう。日産は、かつては高配当を続けていましたが、2010年代後半からの業績不振を背景に、配当を大幅に減らすことになりました。
| 年 | 年間配当金 (円) |
|---|---|
| 2018年3月期 | 57 |
| 2019年3月期 | 10 |
| 2020年3月期 | 0 |
| 2021年3月期 | 0 |
| 2022年3月期 | 5 |
| 2023年3月期 | 10 |
| 2024年3月期 | 20 |
| 2025年3月期 (予想) | 0 |
この表からもわかるように、2018年には1株あたり57円だった配当金が、わずか2年後の2020年にはゼロになりました。その後、一度は回復基調を見せたものの、2025年には再び無配予想を発表しています。これは、企業の業績によって配当が大きく変動する良い例です。
配当の不安定さは、本業の収益が安定せず、成長が上手くいかなかったことにも原因があります。例えば、 日産は、2018年ごろから売上高が横ばいまたは減少傾向にあり、市場全体の成長を捉えきれていない状況でした。また、利益率も不安定で、競争力の低下や、グローバル市場での販売低迷が続きました。2020年には約5000億円の減損損失を計上するなど、大規模な損失が発生しました。
日産の事例は、「高配当を続けているから安心」という単純な判断が危険であることを示しています。高配当の裏側には、事業の成長が止まっていたり、将来への投資を怠っていたりする可能性があり、それが将来的な減配リスクにつながるのです。
高成長株のデメリットは、株価大暴落のリスク
次に、高成長を期待される株が持つリスクについて見てみましょう。高成長株は、その成長性が期待される分、将来の収益を見越して高い株価で取引されることが多く、少しでも期待を裏切るような事態が起きると、株価が急落するリスクを常に抱えています。
近年の代表的な例として、AI開発企業であるオルツの事例が挙げられます。オルツは、AI技術への期待から2024年に株価が急騰しました。実際、上場来最高値/上場時の価格は1.44倍にも上昇していましたが、その後、2021年12月期から2024年12月期にかけて、売上高は公表値の78%〜91%が過大計上されていた売上高の過大計上疑惑が発覚し、株価はわずか数ヶ月で大暴落しました。
| 日付 | 株価 (円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2024年10月上場時 | 570円 | 公開価格540円に対し、初値570円で上場 |
| 2024年12月 | 約823円 | 上場来最高値 |
| 2025年2月 | 約730円 | 年初来高値(売上高過大計上疑惑が発覚する前の高値) |
| 2025年4月 | 約350円 | 疑惑報道直後に株価が急落 |
| 2025年8月 | 約10円 | 半期報告書の提出遅延など、問題が深刻化しさらに下落 |
オルツが発表していた不正会計前の業績と、第三者委員会による調査で明らかになった不正会計後の正しい業績を比較したものです。
| 決算期 | 発表されていた売上高 (百万円) | 不正会計後の売上高 (百万円) |
|---|---|---|
| 2020年12月期 | 55 | 55 |
| 2021年12月期 | 955 | 210 |
| 2022年12月期 | 2,668 | 239 |
| 2023年12月期 | 4,111 | 344 |
| 2024年12月期 | 6,057 | 1,090 |
かなりの金額の架空売上ですね。
オルツの事例はやや極端ではありますが、高成長株のリスクを明確に示しています。
- 期待先行の株価: 将来の成長を織り込んで株価が形成されるため、少しでも悪いニュースが出ると、その期待が剥がれ落ち、株価は適正価格まで急落します。
- 情報開示の重要性: 企業が投資家に対し、正確で透明性の高い情報開示を怠ると、一気に信頼を失い、株価は大暴落します。
- ガバナンスの問題: 経営陣による不適切な行為やガバナンスの欠如は、投資家からの信用を失い、株価暴落の直接的な原因となります。
オルツの株価は、不正会計疑惑や経営陣の辞任、さらには半期報告書の提出困難など、複数の問題が複合的に絡み合い、わずか数ヶ月で時価総額のほとんどを失いました。
このように、高成長株投資は大きなリターンを期待できる一方で、事業内容や経営体制をしっかりと分析しないと、取り返しのつかない損失につながるリスクがあることを理解しておく必要があります。
まとめ
高配当株と高成長株、それぞれの特徴やメリット、そしてリスクについて見てきました。改めて考えてみると、どちらが良い、悪いと単純に決めつけることはできません。なぜなら、それぞれに異なる魅力と弱点があるからです。
高配当株は、安定した収入が期待できるため、日々の生活にゆとりを持たせたい方や、リスクをできるだけ避けたい方にとても向いています。一方で、大きな値上がりはあまり期待できないという弱点があります。
一方、高成長株は、短期間で資産を大きく増やせる可能性があります。夢のようなリターンが狙える一方で、業績が悪くなったり、予期せぬトラブルが起きたりすると、株価が大きく下がり、投資したお金を大きく失うリスクがあります。
このように、高配当株と高成長株は、投資する人の目的や考え方によって、どちらがより適しているかが変わってきます。つまり、「どちらかを選ぶ」というよりも、どちらか一方に偏って投資するのではなく、両方の良い面を理解し、バランスよく組み合わせて投資をすること、ご自身の目標に合わせて賢く使い分けることがとても大切なのです。