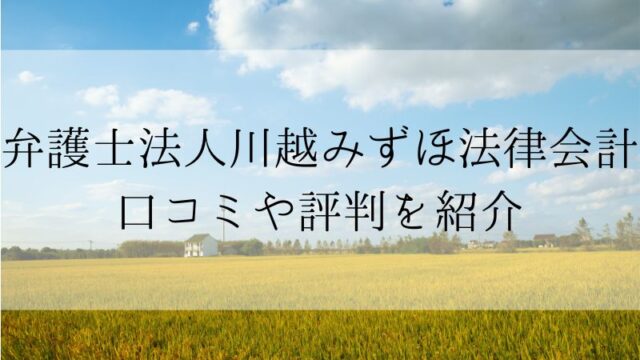「会社を辞めたいけれど、自分で上司に伝える勇気がない」―。そんな悩みを抱える人にとって、退職代行サービスは、今や欠かせない選択肢の一つになっています。多くの方が、その手軽さと早さに助けられ、次のステップへと進んでいるのは事実です。
しかし、その最大手の一つであった「退職代行モームリ」が、2025年10月22日に警視庁による家宅捜索を受けたというニュースは、サービス利用者や、これから利用を考えている私たち全員に、大きな衝撃と不安を与えました。まさか、信頼していたサービスが、このような法律に関わる問題に直面するとは想像もしていなかったからです。
この家宅捜索の背景にあるのは、弁護士法違反という法律の問題です。弁護士ではない一般企業が、お金をもらう目的で法律の仕事(法律事務)をすることを禁止する非弁行為(ひべんこうい)が疑われています。モームリのケースでは、弁護士へ依頼を紹介し、その見返りに紹介料(キックバック)を受け取っていた点が、法律に違反する行為として焦点となっています。
この記事では、退職代行モームリが家宅捜索を受けた具体的な理由と、弁護士法違反の容疑の経緯を分かりやすい言葉で徹底解説します。そして、二度と違法なサービスを選ばないために、安全な退職代行サービスを見分けるための3つのチェックポイントについても詳しく紹介します。
目次
モームリ家宅捜索の全貌
2025年10月、一体何があった?
「退職代行モームリ」というサービス名を聞いたことがある人は、とても多いのではないでしょうか。
このモームリを運営する会社が、2025年10月22日、警視庁による家宅捜索を受けました。
このニュースは、退職代行サービスを利用したことのある人、そして業界全体に大きな衝撃を与えました。
捜索の対象となったのは、運営会社である株式会社アルバトロスと、同社と提携していた弁護士事務所など複数か所に及びます。
なぜなら、警察は、モームリが弁護士法に違反している疑いが強いと判断したからです。
この事件は、単なる一企業のトラブルではなく、退職代行というサービスが持つ「グレーゾーン」を一気に表面化させた出来事だと断言できます。
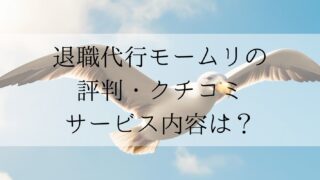
報道ベースで読み解く家宅捜索の経緯
家宅捜索に至った最大の理由は、モームリが「非弁行為(ひべんこうい)」や「非弁提携(ひべんていけい)」と呼ばれる行為に関与した疑いです。
具体的には、報酬を得る目的で、退職希望の利用者を弁護士に紹介し、その紹介料を受け取っていたのではないかという点が焦点となりました。(出典:退職代行「モームリ」運営会社に家宅捜索 退職希望の客に弁護士をあっせんし違法に紹介料受け取った疑い 退職代行「モームリ」捜索 弁護士に違法あっせん疑い )
モームリはこれまで、のべ4万人以上が利用したと言われる、業界でも最大手のひとつでした。急成長を遂げたサービスだからこそ、その裏側で、法律に違反する行為が組織的に行われていたと警察は見ているのです。(出典:捜査関係者「組織的で悪質」急成長の裏で弁護士法違反か…退職代行モームリに家宅捜索)
したがって、警視庁は、押収した資料を詳しく分析し、容疑の全容解明を進める方針を固めています。
この問題は、私たち利用者がサービスを選ぶときに、「安心」と「違法性」の境界線をしっかりと見極める必要性を強く示しています。
核心に迫る!弁護士法違反とは何か
モームリの非弁行為・非弁提携が疑われたワケ
今回の事件を理解するために、最も重要なのが「弁護士法第72条」です。
この法律は、弁護士ではない人が、お金をもらう目的で、法律に関する仕事(法律事務)をすることを禁止しています。この禁止行為こそが、非弁行為(ひべんこうい)と呼ばれています。具体的に法律事務とは、裁判ごとや、会社との和解交渉、損害賠償請求などが含まれます。
退職代行サービスの場合、「会社に退職の意思を伝える」という単なる通知であれば法律事務ではないため、非弁行為には当たりません。しかし、退職金や有給休暇の消化について会社と交渉したり、請求したりする行為は、弁護士資格がないとできない法律事務になります。
さらに、モームリのケースでは、弁護士ではない一般企業が、報酬をもらう目的で法律事務を弁護士に紹介する非弁提携(ひべんていけい)が疑われています。つまり、自社でできない交渉が必要な顧客に対して弁護士を紹介し、紹介料と言う形で利益を得ていたことが問題の中心なのです。(参照:弁護士法第72条・非弁行為の解説 | 札幌弁護士会 )
キックバックの仕組みと法的リスク
今回の捜査の核となっているのは、モームリ運営会社が弁護士から受け取っていたとされる「キックバック」、つまり紹介料です。
モームリは、交渉が必要な利用者を提携弁護士に紹介する見返りとして、顧客一人あたり数万円の紹介料を弁護士から受け取っていた疑いが強いとされています。(出典:朝日新聞「退職代行サービスをめぐる弁護士法違反の疑い、背景にあるのは?」)
このような「報酬目的のあっせん」は、非弁行為として弁護士法で禁止されています。
もし、この事実が立証された場合、モームリ側だけでなく、紹介料を支払って依頼を受けていた弁護士側も、弁護士法第72条(非弁護士との提携禁止)に問われる可能性があります。
利用者の視点から見ると、弁護士に依頼したつもりが、その費用の一部が、法律の専門家ではない仲介業者に流れていたことになります。
これは、弁護士による公正なサービスの提供を妨げ、最終的に利用者の利益を損なう危険性があるため、法律で厳しく規制されているのです。
実は、今回の事件が起こる前から、東京弁護士会などの弁護士会は、退職代行サービス業者による非弁行為の疑いを指摘し、注意喚起を行っていました。(東京弁護士会「弁護士でない者の法律事務の取扱いについて」)
したがって、この問題は業界内で以前からくすぶっていた「火種」が一気に燃え上がった形だと言えるでしょう。
モームリは今後どうなる?退職代行の選び方は何に気を付ければいい?
モームリの事業継続と今後の業界動向
今回の家宅捜索という大きな問題が発生しましたが、モームリの運営会社アルバトロスは、事業を停止することなく、今後もサービスを継続していく意向を示しています。(出典:日本経済新聞「退職代行モームリ、捜索後も事業継続の意向」)
同社は、警察の捜査に協力するとともに、役員体制を見直し、新たな管理体制を構築していくと表明しています。
しかし、今回の事件は、退職代行業界全体に大きな影響を与えたことは間違いありません。
なぜなら、他の退職代行業者も、自社のサービスが合法であることを改めて強調する声明を出すなど、業界全体で法令遵守の意識が高まっているからです。
したがって、今後は、法律を曖昧なままにしてサービスを提供する「グレーな業者」は淘汰(とうた)され、弁護士や労働組合が提供するサービスが主流になるという健全化の流れが進むと予想されます。
退職代行というサービス自体が、働き方の多様化やハラスメント問題に対応するために社会的に必要とされていることは変わりません。
私たちが安全にサービスを利用できるようにするためにも、今回の事件を教訓として、サービスの提供者が「法律を守る姿勢」をより一層明確にすることが求められています。
違法業者を見抜く3つのチェックポイント
退職代行を利用したい読者の皆さんは、今回の事件を受けて「どのサービスを選べば安全なの?」と不安を感じていることでしょう。
最も重要なのは、「交渉ができるかどうか」の権利を誰が持っているかを確認することです。
【チェックポイント1】サービスの提供主体は誰か?
提供主体 交渉の可否 法的な安全性
弁護士・弁護士法人 可能 最も安全
労働組合 可能(団体交渉) 安全
一般企業 不可能 通知代行のみ合法
退職代行を選ぶ際は、まず運営元の情報を調べ、弁護士法人か、または労働組合の看板を掲げているかを確認してください。
【チェックポイント2】料金体系に不透明な部分はないか?
次に、料金体系をよく見てください。
もし、基本料金とは別に「交渉が必要な場合は提携弁護士に依頼します」という流れになっている場合、そこに高額な追加費用や不透明な紹介料(キックバック)が含まれていないか注意が必要です。
したがって、「弁護士が全て対応します」と最初から明言しているサービスを選ぶほうが、結果的に費用も明確で安心です。
【チェックポイント3】宣伝内容に「交渉」や「請求」の言葉がないか?
一般企業が運営するサービスなのに、ウェブサイトなどで「残業代を請求します」「会社と代わりに交渉します」といった表現を使っていたら、それは違法な非弁行為の可能性が高いと断言できます。