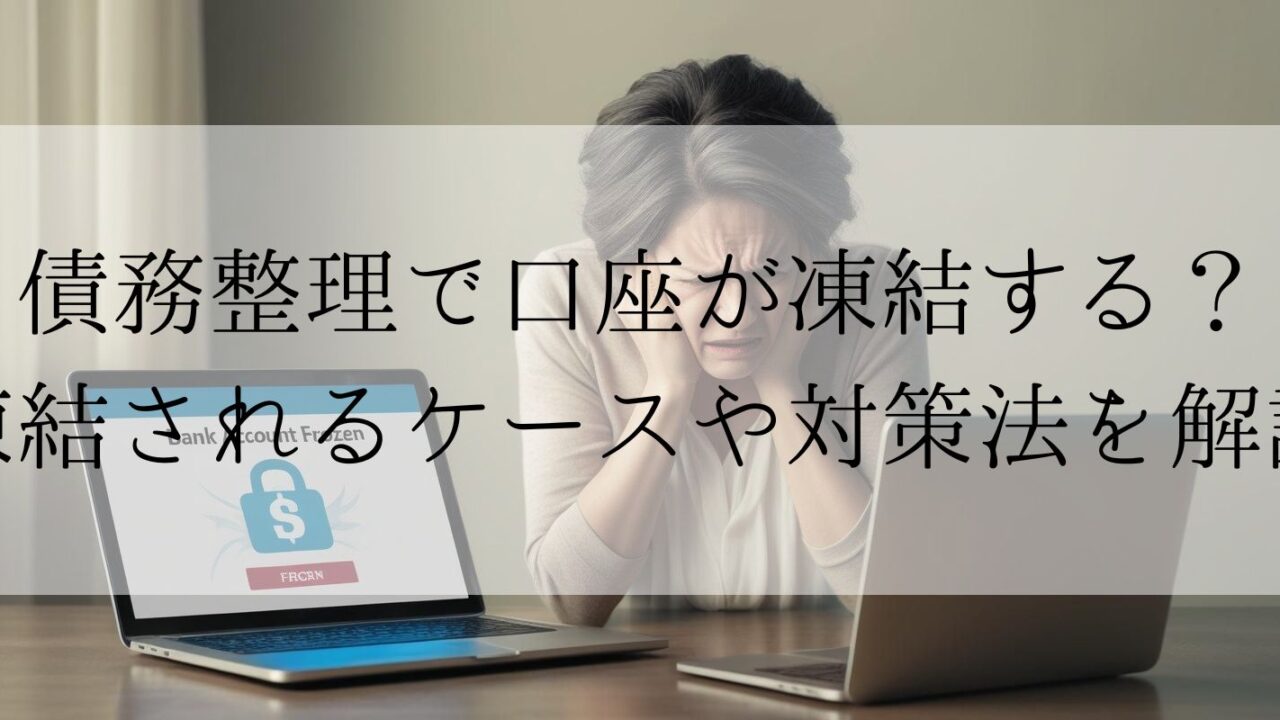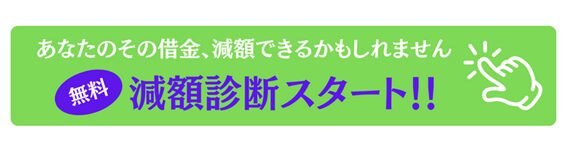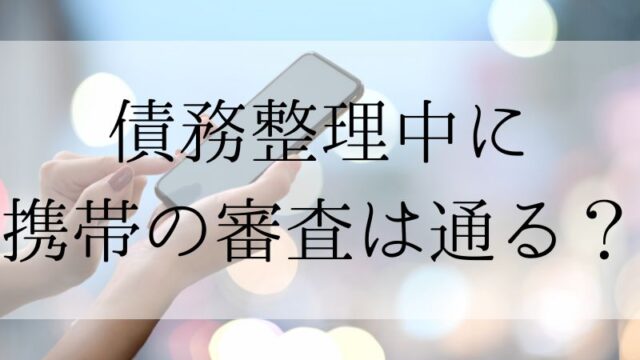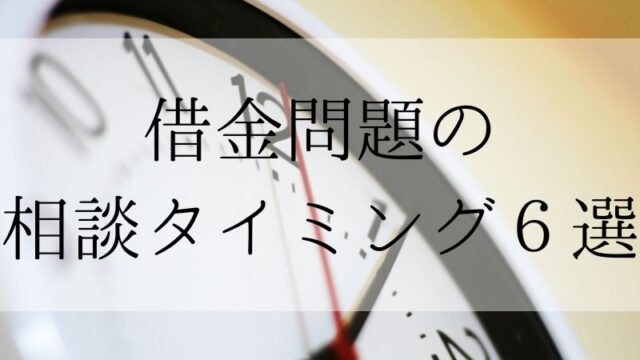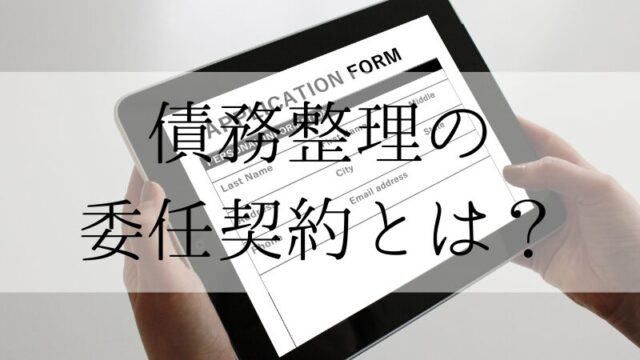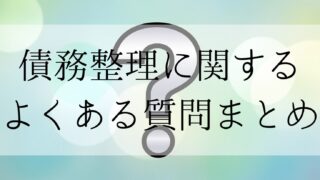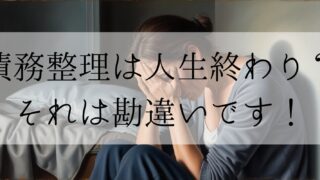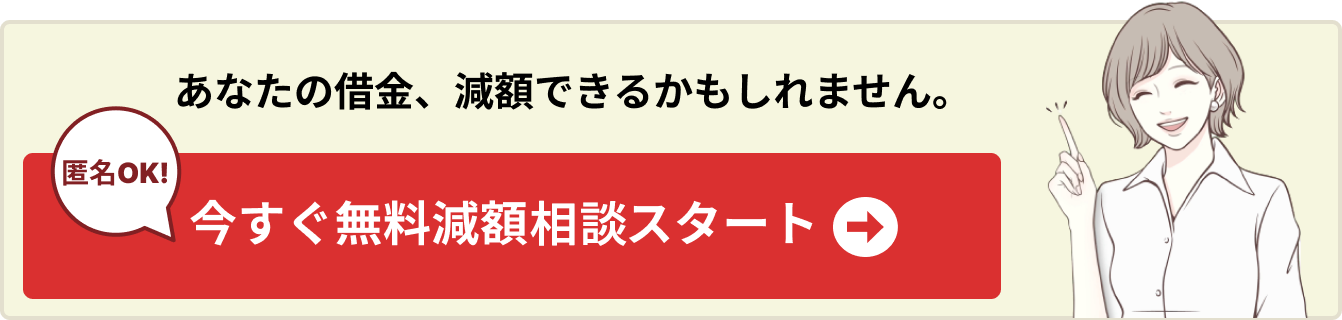借金の返済に行き詰まり、債務整理を検討されている方は少なくないでしょう。しかし、債務整理の手続きを進める過程で、借入先の銀行口座が凍結されるリスクがあることをご存知でしょうか?
口座が凍結されると、預金の引き出しや各種支払いができなくなるなど、日常生活に大きな支障が出ます。
ですので、債務整理を検討するなら、口座凍結の可能性について理解し、適切な対策を講じることが大切です。
本記事では、口座凍結の仕組みや原因、債務整理を行う際に口座が凍結されるケース、そして口座凍結に備えた事前の対策について詳しく解説します。債務整理で生活再建を目指すなら、ぜひ参考にしてください。
「債務整理後も銀行口座開設はできる?できない?その理由を徹底解説」はこちら。

目次
銀行口座が凍結される場合とは
口座凍結とは?
自己破産や任意整理などの債務整理手続きは、借金問題解決の切り札となります。しかし、この手続きを進める過程で、借入先の銀行口座が凍結されるケースがあるのをご存知でしょうか。
口座凍結とは、金融機関が預金口座の利用を一時的または永続的にストップさせる措置のことです。この措置は、口座名義人の判断能力の低下や死亡、不正利用の疑いなどを理由に、預金者保護や法令遵守の観点から必要と判断された場合に実施されます。
口座が凍結されると、ATMでのお金の預け入れや引き出し、振込や振替などの送金取引、公共料金等の口座引き落とし、クレジットカードの利用や支払い、新規の金融商品契約など、様々な取引や手続きが制限されてしまいます。
凍結の手続きは、通常、銀行が状況を確認次第、即時に実施します。この際、事前通知なく凍結されることもあるため、突然の事態に備えた準備が重要となります。
特に注意が必要なのは、同じ銀行の他の口座も連動して凍結される可能性があることで、給与振込や年金受給の口座が凍結されると、収入に直接影響が出ることは避けられません。
また、凍結解除には、状況に応じた適切な手続きと必要書類の提出が求められます。手続きには一定の時間がかかるため、あらかじめ口座から預金を引き出しておく、給与の振込先を変更する、公共料金のお支払方法を変更するなどの対処をするなど、緊急時の対応策を事前に考えておくことが重要となります。
口座凍結されてしまう原因とは
口座名義人の死亡が判明した時
銀行は、口座名義人が亡くなったことを把握すると、その時点で該当する全ての口座を凍結します。
これにより、ATMでの入出金や振り込み、口座引き落とし、通帳の記帳など、全ての銀行取引が停止します。
相続が発生すると、その預金口座は相続人全員の共有財産となります。(民法第249条)相続人全員で遺産分割協議を行い、預金を誰が相続するのか決定する必要があります。(参照:民法256条1項、同907条1項)亡くなった方の戸籍謄本を取得し、法定相続人全員による遺産分割協議を行うなどの相続手続きを完了し、必要書類を提出することで、預金口座の解約や相続人への払い戻しが可能となります。
認知症であることが発覚した時
銀行は、親が認知症であることを知った時点で口座を凍結します。
この凍結は、成年後見人(民法第8条,第843条)が選任されるなどの法的手続きが完了するまで続くことが多いです。ただし、全ての銀行が同じように対応するわけではありません。一部の銀行では、専門のスタッフが家族と相談の上で、一定の取引を許可する場合もあります。それでも、多くの場合、名義人本人が直接銀行に行って取引することはほぼ不可能になります。
銀行が口座を凍結するのは、名義人の判断能力が著しく低下していることを知った時です。特に、認知症の発症により口座名義人が正常な判断を下せなくなった場合、銀行取引に大幅な制限がかかります。
多くの場合、銀行は手続きの際に以下の点を基準に本人の意思確認を行います。
・本人が窓口に来られるか
・名前や生年月日を答えられるか
・直筆で署名ができるか
例えば、本人がまだ暗証番号を覚えていてATMでキャッシュカードを使って入出金をしている場合、銀行は名義人の判断能力について把握できません。しかし、暗証番号を忘れたり、通帳やキャッシュカードを紛失した場合には、窓口での手続きが必要になります。その際、上記の意思確認が行われます。
借金がある金融機関で債務整理手続きを開始した時
債務整理の手続きを始めると、借り入れがある金融機関は顧客の口座を一時的に凍結することがあります。
これは、預金口座に残っているお金から、貸金に対する返済金を回収しようとするためです。銀行としては、債務整理により借金の返済額を減額、あるいは返済を免除するかわりに、債務者の財産である預金があるうちに少しでも返済してもらおうという意図があります。
そのため、凍結された口座から銀行が預金を引き出して、返済されずに残ったままとなっている借金の返済にあてます。
ただし、口座凍結により借金と相殺されるのは、凍結された時点で口座に残っている金額のみです。口座凍結後に入金されたお金がある場合、一般的には、その金額は相殺されずに口座に残った状態となります。
また、これは全てのケースで当てはまるわけではありません。債務整理の対象となっている借金がある金融機関の口座や、消費者金融が同じグループ系列の銀行を持っている場合、その系列内の銀行カードローンの口座も凍結される可能性があります。
口座が犯罪などで不正利用された時
不正使用の疑いがある場合、金融機関は該当の口座を凍結します。
例えば、口座は振り込め詐欺(投資勧誘詐欺や還付金等詐欺など)、資金洗浄(ヤミ金融業者、マネーロンダリング)、ネットショッピング詐欺など、さまざまな犯罪で悪用された場合などが該当します。
特に注意が必要なのは、一度自分名義の口座が犯罪に使われると、他に所有している金融機関の口座も一緒に凍結される可能性が高いことです。
これにより、複数の口座が使えなくなることがあるため、口座情報の管理には十分気を付ける必要があります。
債務整理で口座凍結凍結される場合の具体例
口座凍結とは、金融機関が預金口座の利用を一時的または永続的に停止させる措置のことです。この措置は、口座名義人の判断能力の低下や死亡、不正利用の疑いなどを理由に、預金者保護や法令遵守の観点から必要と判断された場合に実施されます。
口座が凍結されると、ATMでの預け入れや引き出し、振込や振替などの送金取引、公共料金等の口座引き落とし、クレジットカードの利用や支払い、新規の金融商品契約など、様々な取引や手続きが制限されてしまいます。
口座が凍結される主な原因には、以下のようなケースがあります。
- 口座名義人の死亡が判明した時
- 認知症であることが発覚した時
- 借金がある金融機関で債務整理手続きを開始した時
- 口座が犯罪などで不正利用された時
以上のように、口座凍結は突然起こり得る事態であり、日常生活に大きな影響を及ぼします。特に、債務整理を検討中の方は、口座凍結の可能性を視野に入れておく必要があります。
そこで、次に、債務整理をした場合に口座凍結をされる具体的なケースについて紹介します。
預金口座を開設しているのと同じ銀行からの借入を債務整理の対象とする場合
口座凍結が行われる典型的な場合は、預金口座を開設しているのと同じ銀行からの借入を債務整理の対象とする場合です。
債務整理の対象となった銀行は、通常であれば、上述の理由から債務整理をする人の口座を凍結します。
同一の金融機関であれば、カードローンを契約した支店と普通・定期預金口座を開設した支店が異なっていても、全ての口座が凍結されます。
例えば、三井住友銀行のカードローンを任意整理の対象とした場合、所有している三井住友銀行の口座は、支店を問わずほぼ確実に全て凍結されると言えます。
債務整理を依頼する専門家には、必ず口座がある全ての支店を伝えて事前対策をしましょう。
口座を保有する金融機関系列の信販会社から借金している場合
また、口座を保有する金融機関から直接借金をしていなくても、系列の信販会社から借金していたために凍結されることもあります。
信販会社には同じグループ系列の銀行が存在することがあります。
銀行カードローンと、同グループ系列の信販会社どちらにも借金があり、信販会社の借金だけを任意整理する場合、銀行カードローンの銀行口座が凍結される可能性があります。
銀行カードローンは、系列の信販会社を保証会社としていることが多いからです。
なお、銀行カードローンは利用しておらず、信販会社や消費者金融のみの借金を任意整理するような場合は、銀行口座が凍結されることはありません。
債務者の口座が不正利用されてる場合
次に、債務者の口座が不正利用されてる場合も、口座の凍結をされることがあります。
「債務整理が失敗するとどうなる?失敗の原因と失敗しやすい人の特徴とは?」「借金を滞納したらどうなる?借金滞納の結末について徹底解説します」でも紹介しましたが、食い詰めた債務者が犯罪に手を染めることも珍しくありません。
例えば、「銀行口座の売買」は、犯罪収益移転防止法違反、詐欺罪、窃盗罪などに該当する可能性のある違法行為です。
しかし、これらを行う債務者は後を絶ちません。一般社団法人 全国銀行協会によりますと、2022年度の利用停止件数は74,042件、強制解約等の件数は30,711件(うち29,132件は既に利用停止措置が取られていた口座)で、合計件数は75,621件に上りました。これは2021年度と比べて約39%の増加であり、銀行口座の不正利用が急増していることがわかります。
この中には、相当数の債務者が含まれているものと思われます。
また、お金がないのでSNS上の「お金を配るアカウント」に応募してしまう人もいます。この中には、個人情報を不正に取得したり、詐欺に利用されるなど危険性の高いケースも存在します。つまり、前澤氏の企画で注目を集めた「お金配り」という手法が、悪意ある人物に悪用されているのが現状なのです。
SNS上の「お金配り」が詐欺に悪用される代表的な手口が、「振り込め詐欺」との組み合わせです。
犯行グループはまず、SNS上で「お金配り」キャンペーンを宣伝し、応募者の口座情報を入手します。そして実際に少額のお金を配ることで応募者の信頼を得るのです。
信頼を得た後、犯行グループは高齢者などを狙って「振り込め詐欺」を敢行。その際、先に集めた口座情報を振込先として悪用するのです。
さらに口座の保有者に対しては、「誤って100万円振り込んでしまった。10万円は謝礼として受け取ってほしいので、残りの90万円を返金してほしい」などと持ちかけ、不正に得た資金を回収します。
この場合、お金配りキャンペーンの応募者は、知らぬ間に詐欺の片棒を担がされた形になります※。最悪の場合、詐欺の共犯として逮捕される可能性すらあるのです。
※実際の詐欺事件で、加害者がこのようなシナリオを「言い訳」として主張するケースもあるとのこと。
このように、債務者の口座は、不正行為に利用されやすいのです。
債務者が口座を凍結される理由が、「不正利用であった」というケースは数多いため、注意する必要があるでしょう。

口座差し押さえがされた時
口座差し押さえがされた時にも、一時的に入出金等が制限される場合があります。
口座差し押さえとは、債務者が滞納している借金や税金を回収する手段の一つで、債務者が支払いを滞納している場合に、債権者が裁判所を介して債務者の預金口座を強制的に回収する手続きです。
口座差し押さえは、債権者が裁判所に差押えの申立てを行い、裁判所が申立てを認め、銀行に差押え命令を発令します。その結果、銀行が債権者の債権額に応じ、債務者の預金を別に管理する
口座差し押さえと口座凍結は異なる手続であり、口座差し押さえは申立てに基づき裁判所が命令を出すことで行われます。一方、口座凍結は、金融機関が何らかの不正な取引の疑いがあると判断した場合に、独自の判断で行う措置です。。
ただ、どちらも一時的に口座の利用が制限される点では共通しているという点に注意が必要と言えるでしょう。