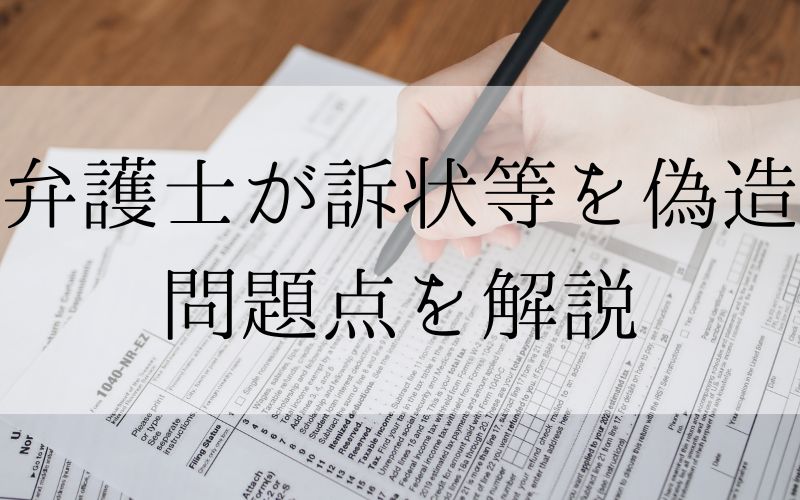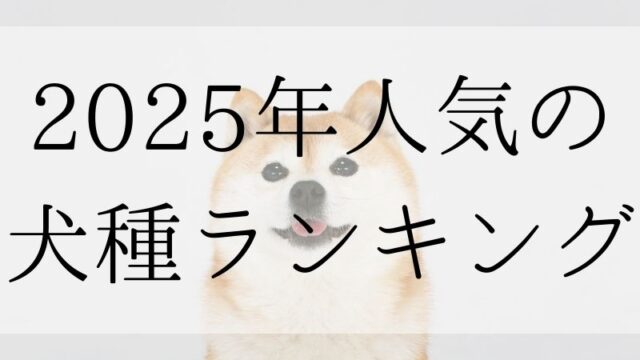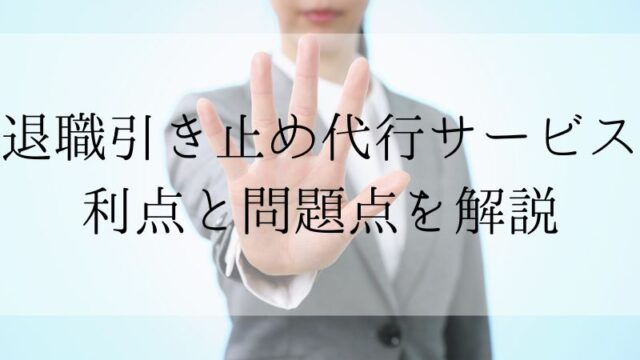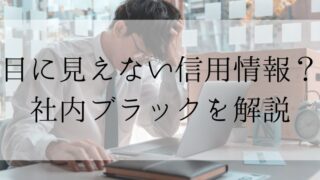元札幌弁護士会所属の井上大造弁護士による、前代未聞の訴状捏造事件が世間を騒がせています。
井上弁護士は、千葉県の女性から依頼された損害賠償請求訴訟の手続きを約1年10ヶ月もの間放置し、依頼者の信頼を裏切る重大な職務怠慢を犯しました。参照元: 読売新聞オンライン「弁護士が訴状捏造、札幌地検が在宅起訴…元札幌弁護士会所属、訴訟放置隠す」
弁護士という多忙な職業の重圧や個人的な問題が背景にあったのかもしれませんが、依頼者にとっては提訴の遅れによる精神的・経済的負担の増大や、訴訟の時効が迫るなどの実害が生じかねない重大な問題です。
さらに驚くべきは、井上弁護士が発覚を隠すために用いた巧妙な手口です。同僚弁護士の職印を無断で使用し、架空の訴状や答弁書を偽造するという常軌を逸した行為に及んでいました。
この記事では、元札幌弁護士会所属の井上大造弁護士による前代未聞の訴状捏造事件について詳しく解説します。
目次
弁護士による訴状捏造事件、その詳細
約1年10ヶ月の放置?依頼者の信頼を裏切る重大な職務怠慢
井上弁護士は、千葉県の女性から依頼された損害賠償請求訴訟の手続きを、約1年10ヶ月もの間放置していたことが明らかになりました。(参照元: 読売新聞オンライン「弁護士が訴状捏造、札幌地検が在宅起訴…元札幌弁護士会所属、訴訟放置隠す」)
弁護士という多忙な職業の重圧や、個人的な問題が背景にあったのかもしれませんが、依頼者にとっては提訴の遅れによる精神的・経済的負担の増大や、訴訟の時効が迫るなどの実害が生じかねない重大な問題です。これは明らかに弁護士としての職務怠慢であり、依頼者の信頼を裏切る行為と言えるでしょう。
巧妙な隠ぺいの手口に呆れる 法律制度の根幹を揺るがす行為
さらに驚くべきは、井上弁護士が発覚を隠すために用いた巧妙な手口です。
同僚弁護士2人の職印を無断で使用し、架空の訴状や相手方の答弁書、準備書面などを偽造。まるで正式な訴訟手続きが進んでいるかのように見せかけました。また、過去に担当した別の訴訟記録から実在する弁護士の印影を複写して使用するという、常軌を逸した行為も行っていました。
偽造された文書はPDFファイルとして依頼者に送信され、依頼者は弁護士がそのような行為をしているとは夢にも思わなかったでしょう。
このような行為は、弁護士資格を持つ者として決して許されるものではありません。私たちの法律制度の根幹を揺るがす重大な問題と言えます。
発覚後は失踪、そして宮崎県弁護士会へ再登録という驚きの展開
さらに驚くべきことに、井上弁護士は事件発覚から間もなくして失踪したといいます。半月後に旭川市内の山奥でテント暮らしをしているところを道警に保護されるなどしたうえで、後に札幌弁護士会への登録を取り消し、再び行方をくらませました。
そして、2021年7月には宮崎県弁護士会へ再登録していたのです。現在も宮崎市内のマンションに事務所を構えていることになっていますが、起訴後に国選で就任した弁護人は「初公判に向けて何度か連絡を試みたが、一度たりともつながらなかった」と証言しており、実態は不明のままです。
弁護士による訴状捏造事件、被告人の初公判無断欠席で異常事態に
同僚弁護士の職印を使って訴状や答弁書を捏造したとして、有印私文書偽造・同行使罪で在宅起訴された井上大造被告が、初公判を無断で欠席するという異常事態が発生しました。被告人が裁判所に出廷しないことは、司法の場において極めて異例の事態であり、事件の解決をさらに複雑にしています。(参照元: 読売新聞オンライン「被告弁護士、初公判無断欠席 訴状など捏造で起訴 行方くらませ審理進まず」)
私たちも、井上被告がなぜ公判に出廷しないのか、その理由を知りたいと強く思っています。
司法の場で異例の事態 被告人の行方は依然不明
初公判当日、井上被告は裁判所に姿を見せず、札幌地検や国選弁護人とも一切連絡が取れない状態に陥りました。刑事事件において、被告が行方不明となり音信不通になることは非常に珍しいケースです。
通常、第一審事件の起訴後勾留率は70%以上と高い割合ですが、本件では在宅起訴とされています。在宅起訴とは、自宅で普段どおりの生活を送りながら刑事事件の捜査が進んだ後、検察官によって起訴されることを指します。
在宅起訴になる条件としては、逮捕・勾留の要件を満たしていないことが前提となります。逮捕・勾留の要件には、「単身身軽でないこと」「罪証隠滅のおそれがないこと」「住居不定でないこと」「身体拘束の必要性がないこと」などがあります。本件では、これらの要件を満たさないと判断され、在宅起訴となったものと考えられます。
しかし、国選弁護人も何度も連絡を試みたにもかかわらず、一度たりとも繋がらなかったと報じられています。このような状況は、被告が自身の責任から逃れようとしていると受け取られても仕方ありません。
被告の出廷なしでは審理は進まず 裁判の行方は不透明
被告の無断欠席により、刑事訴訟法では原則として公判を開くことができません。裁判所は、被告が出廷しない限り、審理を進めることができないのです(刑事訴訟法286条)。
被告人が裁判に出頭しないということが続く場合には、裁判所が被告人を勾引することが考えられます。「勾引」とは、被告人が住所不定である場合や正当な理由なく裁判所からの召喚に応じない場合に、強制的に裁判所に連れていくことができる手続きです(刑事訴訟法58条)。
今後、裁判所は検察庁に対し、被告の捜索と身柄拘束を要請する可能性も出てきます。被告が行方をくらませたことで、裁判の行方は不透明となり、事件の早期解決は難しくなるでしょう。
元同僚の弁護士が「法曹への信頼を損なう行為をしたのだから、ちゃんと出廷して謝罪の言葉を述べてほしい」と語っているように、多くの人々が井上被告の出廷を願っています。今回の事件は、弁護士という職業に対する信頼を大きく損なうものであり、司法制度の根幹を揺るがす重大な問題です。真相の解明と、二度とこのような不祥事が起こらないための対策が強く求められています。
弁護士の信頼と制度の課題、2つの視点から考える
今回の弁護士による訴状捏造事件は、私たち国民が弁護士に対して抱く信頼を大きく揺るがすものです。この事件から見えてくる問題点は多岐にわたりますが、ここでは特に「民事上の問題」と「刑事上の問題」という二つの側面から掘り下げて考えてみましょう。
民事上の問題点 依頼者の損害と社会全体の信頼低下
民事上の問題として最も深刻なのは、依頼者が被った損害です。弁護士が訴訟を放置し、さらに書類を捏造したことで、依頼者は本来得られたはずの利益を失ったり、余計な費用を負担したりする可能性があります。たとえば、時効によって請求権が消滅してしまうケースも考えられます。
また、依頼者の精神的な苦痛も計り知れません。信頼していた弁護士に裏切られたという事実は、依頼者の心に深い傷を残すでしょう。
さらに、この事件は、弁護士に対する社会全体の信頼低下を招き、本当に困っている人が弁護士に相談することを躊躇する原因にもなりかねません。このような不祥事が起きると、一般の人々が「弁護士に相談しても大丈夫なのだろうか」と不安に感じるのは当然です。
弁護士は、法律の専門家として、依頼者の権利を守り、正義を実現するために尽力することが求められています。しかし、今回の事件は、その期待を大きく裏切るものであり、弁護士全体の信用を失墜させかねません。
刑事上の問題点 法律を犯した弁護士と司法制度への影響
刑事上の問題は、まず井上被告が問われている「有印私文書偽造・同行使罪」という犯罪行為そのものです。これは、個人の私文書を偽造し、それを行使(使用)したことを罰するもので、刑法によって定められています。
また、初公判の無断欠席は、司法手続きを妨害する行為に他なりません。たしかに、被告人が公判に出頭しなかったとしても、そのことが何らかの犯罪に該当するわけではありませんし、出頭しなかったことに対する罰則規定も存在しません。
ですが、被告人が正当な理由なく出廷しない場合、裁判は進まず、法の裁きを受けるべき者が責任を回避しているとみられても仕方がないでしょう。
さらには、このような行為は、社会秩序の維持にも悪影響を及ぼします。犯罪を犯した者が、適切な処罰を受けることなく逃げ続けることができるという事態は、国民の司法に対する信頼を大きく損ないます。
最終的に、司法がしっかりと機能し、公正な裁きが下されることが、国民の信頼を回復するためには不可欠です。今回の事件を機に、弁護士の倫理観や責任感を高めるための取り組みが強化されるとともに、司法制度全体の透明性と公正性を確保するための方策が検討されるべきでしょう。