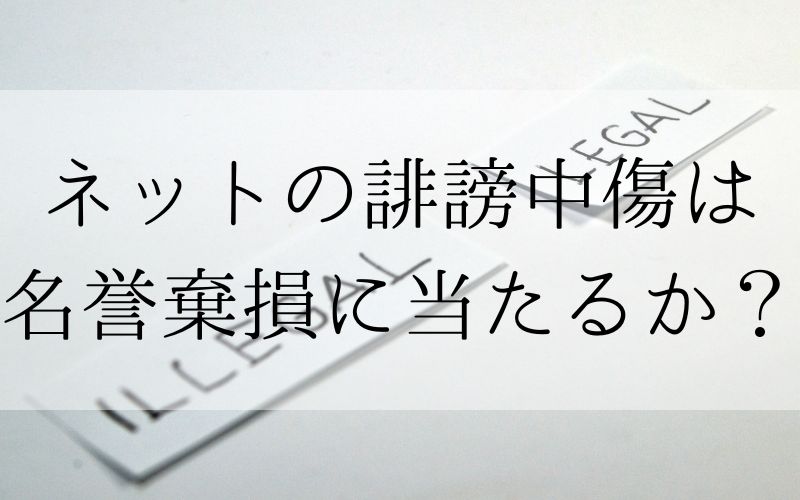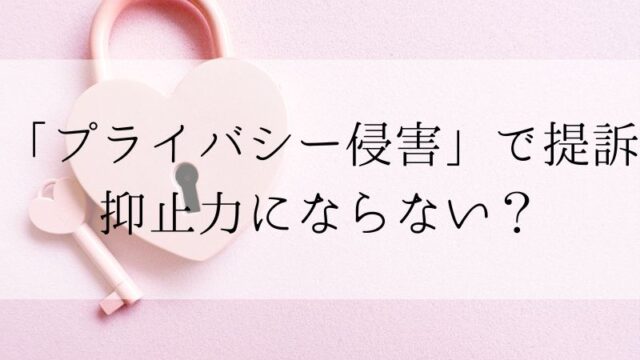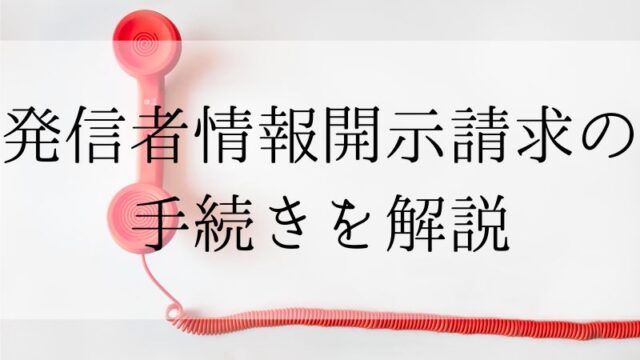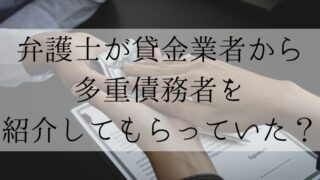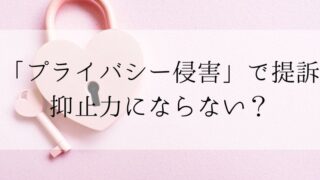現代社会では、インターネットやSNSは私たちの生活に欠かせないものとなりました。しかし、この便利なツールによって投げかけられた、誰かの心ない言葉が、あなたの評価を傷つけたり、信用を失わせたりすることがあります。このような行為は、もしかしたら名誉毀損という法律の問題に当たるかもしれません。
名誉毀損とは、簡単に言うと、人の社会的評価を不当に下げてしまう行為のことです。私たちは皆、社会の中で生きる上で、自分自身の評判や信用を守る権利を持っています。この大切な権利が、誹謗中傷によって脅かされることは決して許されるべきではありません。
では、一体どのような状況で名誉毀損は成立するのでしょうか?そして、もしあなたが被害に遭ってしまったら、どうすれば自分の身を守れるのでしょうか?
この疑問に答えるため、この記事では、名誉毀損がどんな時に成立するのか、民事と刑事それぞれの違いをわかりやすく解説します。さらに、「違法ではない」とされる特別な理由(違法性阻却事由)についても、実際の裁判の例(判例)を交えながら、詳しくお伝えしていきます。
目次
名誉毀損はどんな時に成立する?
私たちは日々、インターネットやSNSを通じてさまざまな情報を発信し、受信しています。しかし、その中には他人の名誉を傷つける情報が含まれてしまうリスクも潜んでいます。名誉毀損は、個人の社会的評価を守るための非常に重要な法律概念です。では、一体どのような状況で名誉毀損は成立するのでしょうか?この問いに答えるため、民事と刑事、それぞれの側面から名誉毀損の要件を掘り下げていきます。
民事・刑事上の名誉毀損の要件と違い
名誉毀損が認められるためには、民事と刑事で共通する要素と、それぞれに特有の要素が存在します。これらの要件を理解することが、名誉毀損の全体像を把握する第一歩です。まずは、民事と刑事それぞれの名誉毀損の要件を、根拠法令とともに確認しましょう。
民事上の名誉毀損の要件
民事上の名誉毀損は、不法行為(民法第709条)として損害賠償請求の対象となります。その成立には、以下の要件を満たす必要があります。
- 1. 事実の摘示: 特定の人の社会的評価を低下させる具体的な事実を指摘することです。その事実が真実であるか、虚偽であるかは問いません。単なる意見や抽象的な悪口とは異なります。
- 2. 名誉毀損性: 摘示された事実が、その人の客観的な社会的評価を低下させる性質を持つことです。実際に評価が低下したことまで証明する必要はありません。
- 3. 故意または過失: 名誉を毀損する意図(故意)があった場合だけでなく、不注意(過失)によって名誉を毀損した場合も成立します。
- 4. 損害の発生: 名誉が毀損されたことによって、精神的な苦痛などの損害が発生したことです。
刑事上の名誉毀損の要件
刑事上の名誉毀損は、刑法第230条に規定される犯罪であり、有罪となれば懲役や罰金などの刑罰が科せられます。その成立には、以下の要件を満たす必要があります。
- 1. 公然性: 不特定または多数の人が認識できる状態にあることが必須です。例えば、インターネット上の書き込みやSNSでの発信、大勢の人がいる場所での発言などがこれに当たります。少数の人に伝わっても、それが不特定多数に広がる可能性がある場合も含まれます(伝播可能性) 。
- 2. 事実の摘示: 特定の人の社会的評価を低下させる具体的な事実を指摘することです。民事と同様、その事実が真実か虚偽かは関係ありません。ただし、死者の名誉毀損に限っては、虚偽の事実であることが処罰の条件です。
- 3. 名誉の毀損: 摘示された事実が、その人の客観的な社会的評価を低下させる性質を持つことです。こちらも実際に評価が低下したことまでは求められません。
- 4. 故意: 名誉を毀損するという認識と意図(故意)があることが必須です。過失によって名誉を傷つけてしまっても、刑事罰の対象とはなりません。
民事と刑事の名誉毀損の主な違い
民事と刑事の名誉毀損は、その目的が大きく異なります。民事は「被害者の損害回復」を目指し、刑事は「社会秩序の維持と加害者への制裁」を目的とします。この目的の違いが、要件の差異に現れているのです。
以下の表で、民事と刑事の要件の主な違いをまとめてみました。
| 違いのポイント | 民事上の名誉毀損(不法行為:民法709条) | 刑事上の名誉毀損(犯罪:刑法230条) |
| 公然性の有無 | 不要:必ずしも不特定多数の人に伝わる必要はありません。少数の特定の人に伝わるだけでも成立し得ます。ただし、損害賠償額には影響します。 | 必要:不特定または多数の人が認識できる状態にあることが必須です。これは、刑法が社会全体の秩序を守ることを重視しているためです。 |
| 故意・過失の範囲 | 故意または過失があれば成立します。不注意で名誉を傷つけても責任を問われる可能性があります。 | 故意があることが必須です。過失によって名誉を傷つけてしまっても、刑事罰の対象とはなりません。 |
| 追求する目的 | 損害賠償、謝罪広告、記事削除などによる被害回復が主な目的です。 | 懲役や罰金などの刑罰を科すことによる社会秩序の維持が目的です。 |
| 主体 | 被害者自身が加害者に対し、損害賠償などを請求します。 | 国(検察官)が加害者に対し、刑事罰を求めて追及します。 |
このように、根拠となる法律が異なるだけでなく、特に「公然性」の有無や「故意・過失」の範囲、そして「追求する目的」において、民事と刑事では明確な違いがあることが分かります。
要件に当たるだけでは足りない。違法性阻却事由について
名誉毀損のすべての要件を満たしたとしても、ただちに責任を負うわけではありません。その行為が「違法ではない」と判断される特別な事情、これを違法性阻却事由と呼びます。これは、憲法で保障される表現の自由という大切な権利と、個人の名誉を守るという利益をバランスさせるために設けられています。
特に、公共の利益に関わる情報については、その発信が保護されるべき場合があります。そのため、名誉毀損における主な違法性阻却事由は、以下の3つの条件を満たすことです。
公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
摘示された事実が、世の中の多くの人々にとって関心があり、知るべき価値がある情報であることです。例えば、政治家の不正、企業の不祥事、公務員の職務怠慢など、社会の健全な運営に関わる事柄が該当します。根拠: 刑法第230条の2第1項に明記されており、民事においても同様の考え方が判例で確立されています。
専ら公益を図る目的であること(公益目的性)
その事実を公表した目的が、個人的な恨みや利益のためではなく、もっぱら社会や公共の利益を守るためであることです。例えば、不正を正したい、被害の拡大を防ぎたいといった動機がこれに当たります。こちらも刑法第230条の2第1項 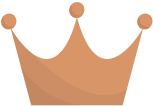 に規定され、民事でも重視される要素です。
に規定され、民事でも重視される要素です。
摘示された事実が真実であることの証明があったこと(真実性)
摘示された事実が、裁判において客観的に真実であることが証明された場合、名誉毀損は成立しません。これは、真実を語る自由を保障するための重要な原則です。【民事と刑事の大きな違い】民事: 事実が真実であると証明できなかった場合でも、行為者が「真実であると信じるに足りる相当な理由があったこと(真実相当性)」が認められれば、違法性が阻却される可能性があります。
こちらの記事もチェック
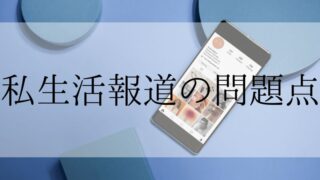
違法性阻却に関する判例は?
刑事事件において、真実性の証明によって違法性が阻却された判例として、「夕刊和歌山時事事件」(最判昭和44年6月25日)が挙げられます。
この事件では、新聞が特定の政治家の不正行為を報道したことが名誉毀損罪に問われました。しかし、裁判所は、報道内容が公共の利害に関する事実であり、もっぱら公益を図る目的で行われた上で、摘示された事実が真実であると認められるため、名誉毀損罪は成立しないと判断しました。
また、同じ判例では、真実と誤信したことに相当な理由がある場合には、名誉毀損罪の故意が否定され、結果として罪が成立しないという法理も示されており、これは刑事事件における重要な考え方です。
民事事件において違法性阻却が認められた代表的な判例では、最判昭和44年6月25日 が非常に重要です。この判例は、刑法230条の2の規定の趣旨から、民事の名誉毀損においても、摘示された事実が公共性や公共目的性、真実性を満たす場合に違法性が阻却されると判示しました。
このように、名誉棄損が行われたからと言って、必ずしも刑事罰や民事の責任追及を受けるわけではないという点に注意していくべきでしょう。
名誉毀損はどんな時に成立する?―まとめ
ネット上での誹謗中傷は、名誉毀損という法律上の問題に発展する可能性があります。名誉毀損が成立するには、民事と刑事それぞれに定められた要件を満たす必要があります。これらの要件には、人の社会的評価を下げるような具体的な事実が示されたこと(事実の摘示)や、実際に社会的評価が下がる可能性がある内容であること(名誉毀損性)などが含まれます。特に刑事では、不特定多数の人がその情報を見たり聞いたりできる状態である「公然性」が非常に重要です。
しかし、これらの要件に当てはまるからといって、必ずしも名誉毀損が認められるわけではありません。特定の状況では、その行為が「違法ではない」とされる「違法性阻却事由」が存在するからです。これは、「公共の利益に関わる事実であること(公共性)」、「もっぱら公共の利益のために情報を出したこと(公益目的性)」、そして「その事実が真実であること」という三つの条件を満たす場合に認められます。また、仮に真実でなくても、「真実だと信じるに足りる十分な理由があったこと(真実相当性)」でも認められることがあります。
ただし、ネット上の誹謗中傷でこの違法性阻却事由が認められる可能性は、一般的に低いと考えてください。匿名での書き込みや、個人的な恨みによる根拠のない悪口、または私的な事柄に関する暴露などでは、公共性や公益目的性が認められにくいためです。真実性の証明も難しい場合が多く、安易な情報発信が大きなトラブルにつながる可能性があることを理解しておくべきでしょう。
誹謗中傷、もし被害に遭ったら?
まずは冷静に証拠を確保
もしあなたが誹謗中傷の被害に遭ってしまったら、何よりもまず冷静になり、徹底的な証拠確保を行うことが重要です。インターネット上の情報は、削除されると復元は困難です。そのため、証拠が消えてしまう前に、速やかに対応する必要があります。
具体的には、誹謗中傷の投稿があったページのスクリーンショットを撮ることが有効です。また、より確実な証拠とするためには、「魚拓(ウェブページの現在の状態を丸ごと保存するサービス)」を取得しましょう。これは、万が一ページが削除されても、その時の状態を証明できる有効な手段です。
他にも、投稿のURL、正確な投稿日時、投稿者のユーザー名(ハンドルネーム)、投稿されたSNSや掲示板の名前、スレッド名など、あらゆる情報を詳細に記録してください。これらの情報は、後の発信者情報開示請求や損害賠償請求において、極めて重要な証拠となります。
個人でこれらの証拠を完璧に保全することは難しい場合もあります。その際、探偵に依頼することも有効な選択肢です。探偵は、専門的な知識とツールを用いて、法的に有効な形で証拠を収集・保全するプロです。彼らは、後の裁判で確実に利用できる証拠を準備してくれます。
専門家への速やかな相談が鍵
誹謗中傷の被害に遭った際、一人で抱え込まず、速やかに専門家へ相談することが問題解決への最も重要な鍵です。適切なタイミングで専門家の力を借りることで、被害の拡大を防ぎ、法的な権利を守ることができます。
まず、誹謗中傷問題に詳しい弁護士に相談することが不可欠です。弁護士は、発信者情報開示請求の手続き、損害賠償請求の交渉や訴訟、そして刑事告訴の検討など、法的なあらゆる側面からあなたをサポートしてくれます。彼らは、あなたの被害状況を正確に評価し、最適な法的戦略を立ててくれるでしょう。
さらに、前述したように、探偵もまた重要な役割を担います。特に、加害者の情報が乏しい場合や、複雑な状況で証拠収集が必要な場合、探偵の専門的な調査能力が非常に役立ちます。彼らは、弁護士と連携し、裁判で必要となる確かな証拠を収集してくれるでしょう。
インターネット上の誹謗中傷は、デジタルタトゥーとして半永久的に残り、あなたの人生に長期的な影響を及ぼす可能性があります。そのため、被害に遭ったら、決して泣き寝入りせず、専門家を頼って積極的に対応することをお勧めします。あなたの権利を守り、平穏な生活を取り戻すために、勇気を持って一歩を踏み出しましょう。