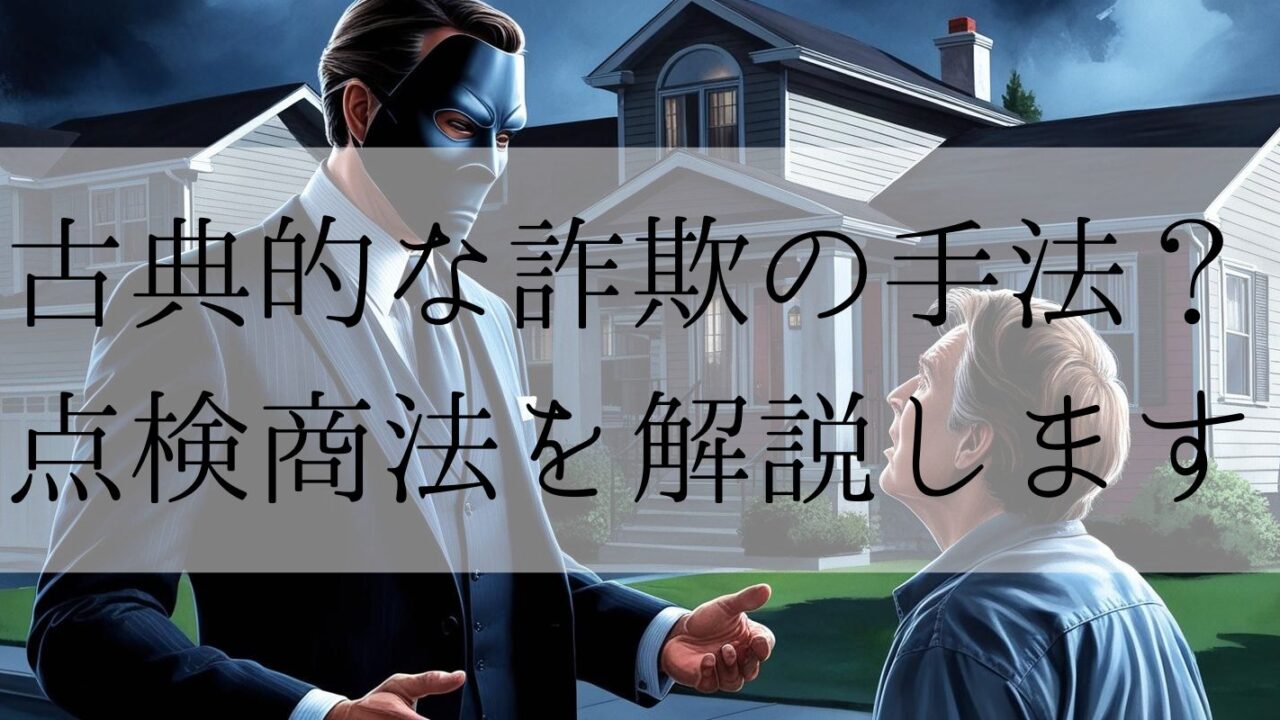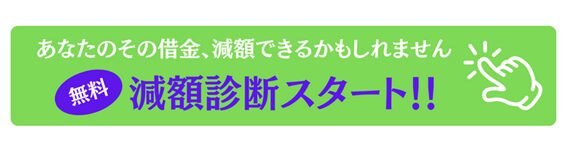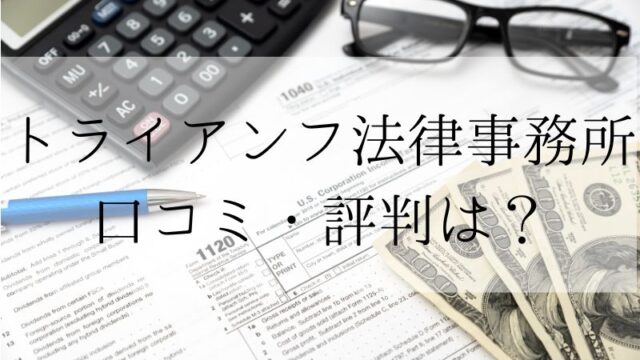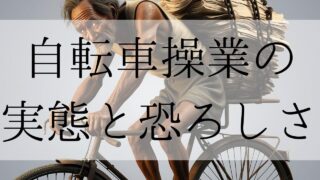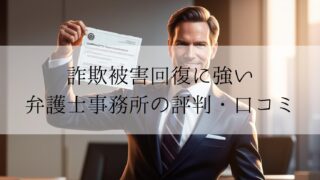点検商法とは、消費者に不必要な点検を提案し、その結果、無理に商品やサービスを購入させる手法です。警視庁のまとめによりますと、2024年に全国の警察が摘発した悪質リフォーム業者による「点検商法」の事件は66件と、これまでで最も多くなっています。また、点検商法などのトラブルは急増しており、全国の警察には昨年、約1万件の相談が寄せられ、前年から倍増しているという事実も見逃せません。
巧妙に仕掛けられた営業手法により、多くの消費者がトラブルに巻き込まれているのです。
この記事では、点検商法の概要や事例、問題点、そしてどのように対策を取るべきかについて紹介します。
点検商法とは
点検商法とは
点検商法は、住宅、車、家電製品などを対象に行われる営業手法で、訪問販売業者が「定期点検」を理由に消費者の自宅や車を訪れ、不必要な修理や交換を提案することが特徴です。この商法では、点検自体が営業活動の口実であり、点検結果を基にして高額な修理費用を請求することが多く見られます。
訪問販売業者は、家庭を訪問し、あたかも正規の点検であるかのように振る舞いながら、消費者が断りきれない状況に追い込みます。そして、不必要なリフォーム工事や商品交換、駆除作業などを行う契約を結ばせるのです。
ただ、実は点検商法自体は、かなり昔からある古典的な詐欺的商法に過ぎません。昭和40年ごろには既にシロアリ駆除を理由とする点検商法が確認されているとの説もあります。
では、このようなある意味古風でクラシックな犯罪である点検証法が、再度注目を浴びるようになったのはなぜなのでしょうか?
点検商法の摘発、相談は増加傾向にある
その理由としては、点検商法の摘発、相談は増加傾向にあることが挙げられます。
NHKニュースの記事「悪質リフォーム業者の「点検商法」事件 過去最多の66件 警察庁」では、全国の警察が昨年1年間に摘発した悪質リフォーム業者による「点検商法」の件数は66件(前年比28件増)に上り、統計が残る2010年以降で最多となったことが明らかになったと報じています。
また、読売新聞オンラインの記事では、「点検商法などのトラブルは急増しており、全国の警察には昨年、約1万件の相談が寄せられ、前年から倍増した。」とも報じられています。
このように、点検商法の問題が深刻化していることが分かります。
点検商法の裏には「トクリュウ」がいる?
警察庁は、点検商法に関与しているとされる犯罪グループ、通称「トクリュウ」にも警戒を強めています。トクリュウとは、SNSでつながる匿名・流動型犯罪グループを指し、資金源として点検商法を利用しているとみられています。
昨年、警察庁が摘発した点検商法の事件は66件にのぼり、特定商取引法違反容疑などで130人(前年比74人増)が摘発されました。そのうち56人は、SNSの「闇バイト」に応募するなどして活動に参加し、トクリュウとして認定されたのです。
最近でも、屋根の修繕工事で、契約時にクーリングオフについて説明しなかったとして、京都府警は、トクリュウの中心人物とみられる、兵庫県芦屋市の会社役員を特定商取引法違反で逮捕された事件(読売新聞オンライン「芦屋の「牛飼」名乗る男、特商法違反容疑で逮捕…「トクリュウ」の中心人物か」)がありました。
本件では、SNSでアルバイトを募り、高齢者宅などを訪問して「屋根に隙間がある」などと不安をあおって工事契約を結ばせる点検商法を繰り返していたとされています。
このように、点検商法は
点検商法の事例~巧妙化する手口~
屋根や家の不具合を指摘する事例
点検商法の代表的な手口の一つは、屋根や家の不具合を指摘して工事契約を迫るものです。
例えば、「屋根がずれている」、「水漏れの危険がある」等と言われたことから、業者を屋根に上げて確認させたところ、屋根を壊された上、その写真を見せられて、修理費用を請求されたなどという事例も報告をされています。
京都府警が昨年11月に摘発した大阪市のリフォーム会社では、訪問時に業者が準備した台本に従い、住民に対して「屋根の木材が腐っており、強風に耐えられない」と告げ、不安を煽って修理契約を結ばせていました。
また、警視庁が摘発した横浜市の業者は、訪問時にわざと屋根を壊し、その破片を見せて「すぐに修理しないと危険だ」と消費者を説得していました。このように、業者は不具合を強調し、消費者に即時の契約を促す手口を取ります。
不必要な工事を提案する事例
訪問販売業者は、消費者に「屋根に不具合があります」「床下が腐っています」と伝え、不安を煽って工事を進めます、業者が「土台の木が腐っている」と言い、必要のない工事を強制することがあります。
さらに、「家が傾いている」と言って高額な修理を提案し、契約を迫ります。「屋根がずれている」と指摘し、屋根を壊した後に修理費用を請求するケースも多いです。また、「近くの工事現場から屋根が壊れているのが見える」と不安を煽り、急いで修理を進めることもあります。
定期的な点検を強調して契約を迫る事例
点検商法では、一度契約すると追加で別の修理や工事を提案されることがあります。
例えば、しろありの駆除を名目に床下に入り、そこで「湿気で土台が腐っている」「地震が来ると危険だ」と不安を煽り、契約を結ばせる手法が使われます。
さらに、エアコンや家電の点検を名目に訪問し、不要な修理や交換を提案することもあります。業者は「定期的な点検を受けないとエアコンが故障する」と消費者に不安を与え、高額な費用を請求します。
追加で別商品を売りつける事例
点検商法の中には、消火器やガス警報器、表札などの、それっぽい商品を高額で売りつけるケースもあります。
例えば、シロアリや害虫の駆除の件であれば、殺虫剤や防虫ネットなどを高額で売りつけるなどのことを考えられます。
また、業者の中には、まるで役所の職員のような服装と口調で、「消火器は法律で義務づけられている」と偽って販売を迫るようなものもいるのです。
点検商法って何が問題なの?
ここまでは、「点検商法の具体的な手口」などを紹介をしてきました。
点検商法の最大の問題は、消費者が誤った情報や嘘を信じ込まされた結果、不必要な工事を強引に受け入れさせられ、高額な費用を支払うことになってしまうことです。
1. 不必要な工事の提案
点検商法の業者は、消費者に不必要な工事や商品を提案することが多いです。
例えば、耐震補強金具や換気扇など、本来必要のない修理や改善を行うよう勧められるケースがあります。消費者はその必要性を理解せずに契約を結ばされることが多く、後で無駄な費用を支払う羽目になることがあります。
例:耐震補強金具の提案。実際には耐震診断をせずに工事を進めることは稀であり、無駄な費用が発生する可能性があります。
2. 高額な契約金額
点検商法の問題点として、必要性がない工事に対して非常に高額な契約金額を請求されることがあります。場合によっては、数十万円から数百万円、場合によっては数千万円に上ることもあります。
こうした高額な請求は、消費者にとって経済的な負担となるだけでなく、法律的にも暴利行為と見なされることがあり、消費者保護の観点から問題です。
3. 契約を急がせる手法
点検商法では、契約を急がせる手法が使われることが多く、例えば「今すぐ決めなければ地震が来た時に困る」などと不安を煽ることで消費者を焦らせます。
また、借家住まいの消費者に対して、「大家さんに相談しなくても大丈夫」といった誤った情報を提供し、消費者が契約を結ばざるを得ない状況に追い込むこともあります。
こうした営業手法は、消費者の権利を侵害するものです。
4. 被害者の意識の欠如
点検商法の被害に遭った消費者は、実際には不必要な工事を行って高額な費用を支払ったことに気づいていない場合があります。
業者が提供するきれいなパンフレットや施工後の写真アルバムなどが、消費者に「自分は良い仕事をしてもらった」と錯覚させるため、被害に遭ったという自覚が薄くなることが問題です。
しかし、高額な工事費を支払ったり、必要のない工事を行っているということには変わりません。このように、被害者が被害を受けたと認識しずらいという点も、点検商法の問題だと言えるでしょう。
点検商法に遭わないためには
安易に契約を結ばないことが大切
最初に必要なのは、自らの力で自分を守ることです。
点検商法のような手法に遭わないためには、まずは点検の目的をしっかりと確認することが大切です。信頼できる業者かどうかを事前に調べ、突然訪問されても冷静に対応しましょう。
また、不審に思った場合、点検が本当に必要かどうかを慎重に見極めることが重要です。特に、急かされて契約をさせられそうになった場合、焦らずにその場で契約を結ばないことを心がけましょう。
内容に納得できない場合は、契約をせず、帰ってもらうことを伝えましょう。他の業者に見積もりを取ることで、適正な価格を知ることが出来る場合もあります。
納得できない内容の契約を結んでしまう前に、その場で断る勇気を持つことが必要です。業者がしつこく勧誘してきても、強引に契約を結ぶ必要はありません。
このような意識を持つことで、点検商法に巻き込まれるリスクを大幅に減らすことができます。
クーリング・オフを利用する
ただ、「既に契約を結んでしまった」「強引な営業に負けてしまった」という方もおられるかもしれません。そのような方は、クーリングオフを検討してください。
クーリング・オフは、消費者が契約を締結した後、一定期間内であれば契約を解除できる制度です。この制度は、訪問販売や電話勧誘販売、エステや学習塾などのサービス提供契約などに適用され、消費者が無理に契約を結ばされないように守るために設けられています。消費者は、特定の条件を満たす場合、契約を無条件で解除することができます。
クーリング・オフの対象となる取引は、主に訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステティックや語学教室、学習塾など)、訪問購入(商品の買取)などです。これらの取引には、それぞれクーリング・オフの期間が定められており、通常、8日間または20日間以内に通知する必要があります。特定商取引法に基づく期間内に手続きを行えば、消費者は契約を解除できます。
クーリングオフには期間制限があり、契約書や申込書など、消費者が書面を受け取った日から起算されます。ただし、契約書類に不備がある場合、消費者は規定の期間を過ぎてもクーリング・オフを行えることがあります。
クーリング・オフの手続きについて不明点がある場合や、トラブルに遭遇した場合には、消費生活センターや専門の相談窓口を活用することができます。
消費者ホットライン(電話:188)や最寄りの消費生活センターに相談すれば、適切なアドバイスや支援を受けることができます。クーリング・オフ手続きがスムーズに進まない場合でも、これらの窓口がサポートしてくれるので、安心して相談しましょう。(参照:国民生活センター「クーリング・オフ」)
困ったときには、専門機関に相談を
点検商法に遭遇したり、相手の勧誘に不安を感じたりした場合は、すぐに専門機関に相談することが大切です。
警察や消費者相談窓口では、あなたをサポートしてくれます。まずは最寄りの警察署で対応を受けることができますし、警視庁総合相談センター(電話:#9110)は、相談内容に応じて適切な窓口に案内してくれるので、連絡先が分からない場合は、まずはここに連絡してみましょう。
警察以外にも、民事的な問題に対応してくれる相談機関があります。もし契約後に解約を希望する場合や、リフォームに関するトラブルが発生した場合は、専門的な窓口に相談しましょう。例えば、リフォームに関する問題では、(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル、電話:0570-016-100)が役立ちます。
また、信頼できるリフォーム業者を探すためには、国土交通省の「住宅リフォーム事業者団体登録制度」を活用すると、安心できる業者を見つけることができます。
最後に、詐欺被害の救済のために
これにより、不必要なトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
まとめ
点検商法は、訪問販売業者が不必要な点検を名目に消費者に訪問し、高額な修理や工事を契約させる手法です。2024年、警察庁は悪質リフォーム業者による点検商法の摘発件数が過去最多の66件に達し、相談件数も急増しています。この手法は、消費者に不安を煽り、高額な契約を結ばせることが特徴です。
点検商法に対する対策として、契約を急がせる営業手法に巻き込まれないよう冷静に対応し、契約内容に納得できない場合はその場で断ることが重要です。また、もし契約後に不安を感じた場合は、クーリングオフを利用することができます。この制度により、一定期間内に契約を解除することが可能です。
さらに、点検商法に遭遇した場合は、警察や消費生活センターなどの専門機関に相談することが勧められます。こうした機関は、消費者をサポートし、トラブルの解決に導いてくれます。信頼できる業者を選ぶためにも、事前にリフォーム業者の評判を調べることが重要です。