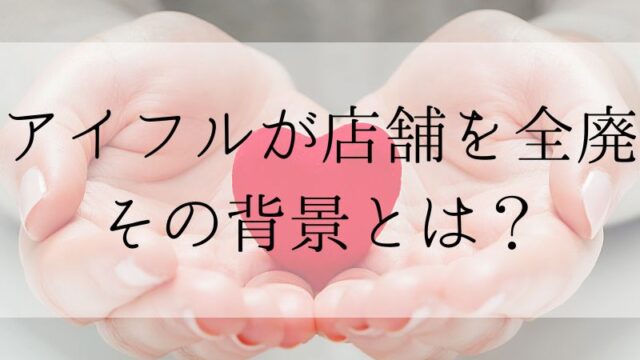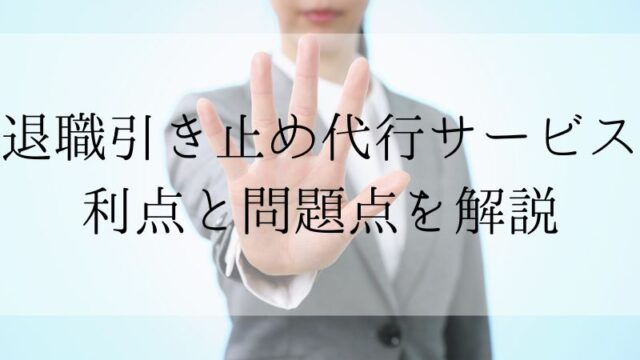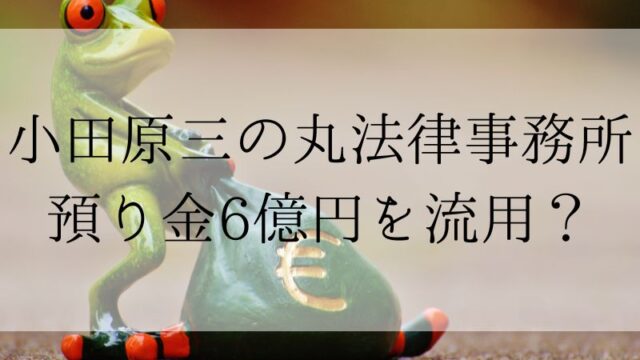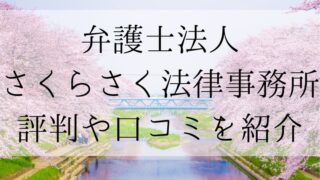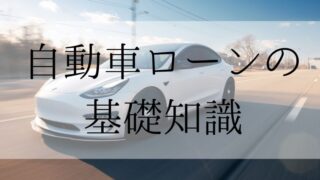目次
木下優樹菜“恫喝DM騒動”の余波で起きた約3億円訴訟とは?
本件は、木下優樹菜“タピオカ騒動”をきっかけに、ロハス製薬株式会社が広告会社Birdmanに対して起こした訴訟
2019年10月に発覚した女優の木下優樹菜さんによる「タピオカ店への恫喝DM騒動」は、大きな社会問題となりました。この騒動の影響で、木下さんは芸能活動を自粛することになったのです。
しかし、騒動はそれだけでは収まりませんでした。実は木下さんを広告に起用していた広告会社のBirdman社が、広告主であるロハス製薬やアイア社から約3億円もの損害賠償請求を受ける事態に発展していたのです。
Birdman社は、木下さんをロハス製薬株式会社の化粧品ブランドの広告に出演させるため、アイア株式会社や木下さんが所属していたプラチナムプロダクションとの間で広告出演契約を結んでいました。ところが、タピオカ騒動によって木下さんが活動自粛に追い込まれたため、契約不履行の状態になってしまったのです。
この事態について専門家は、「契約途中にタピオカ騒動を起こして木下さんは活動できなくなった。契約不履行となり、損害賠償請求は一定程度生じる」と説明しています。一方で、Birdman社に対する損害賠償については「騒動によって売り上げが落ちたことへの損害ではないか」とも指摘されています。
ただ、タピオカ騒動と売り上げ減少の因果関係を立証するのは容易ではありません。結局のところ、ロハス製薬とアイア社は2021年4月1日付で東京地方裁判所に訴訟を提起したのです。
彼らは「本件騒動により本件ブランドのイメージが毀損された」と主張し、木下さん、プラチナムプロダクション、そしてBirdman社に対し、イメージ毀損に伴う損害などの賠償を求めているのです。
そして2025年7月、この訴訟は「和解金ゼロ」で決着
2019年の木下優樹菜さんによる「タピオカ店への恫喝DM騒動」に端を発した損害賠償請求訴訟が、2025年7月、ついに決着しました。
Birdman社は2025年7月10日付の発表で、「ロハス製薬株式会社及びアイア株式会社とは代理人を通じて和解に向けて交渉を続けてまいりましたが、この度、裁判所より和解の打診を受け、双方協議の結果、和解に至りました」と伝えました。
驚くべきは、和解の内容です。Birdman社は「本件和解に伴う被告らによる和解金の支払いはございません」と明かしたのです。つまり、和解金はゼロだったということになります。ただし、和解の詳細な内容については非開示とのことでした。
(参照:木下優樹菜のタピオカ騒動をめぐる巨額訴訟の和解が成立「支払いはございません」(Yahoo!ニュース))
騒がれた「スゴ腕弁護士」の裏にある本当の構造とは
木下優樹菜さんのタピオカ騒動に端を発した損害賠償請求訴訟が、和解金ゼロで決着したことが大きく報じられました。メディアは弁護士の活躍を讃える論調でしたが、果たしてそれは正確な見方なのでしょうか。
成功事例ではあるが、奇跡ではない
注目すべきは、裁判所が提示した和解案の内容です。通常、和解では双方が歩み寄る内容が示されるものですが、今回はゼロ円でした。これは非常に重要な事実だと言えます。
なぜなら、それは次のことを示唆しているからです。
・原告側の主張に法的根拠がほとんどない
・損害を証明する証拠が不十分だった
・裁判所自身が請求の成立可能性を低く見ていた
つまり、実際には、裁判所が“支払いゼロ”の和解を勧告していた時点で、誰がやっても勝てる訴訟であり、弁護士の手腕というよりは、そもそも勝つべくして勝った訴訟だった可能性が高いのです。
もちろん、被告側の弁護士が適切に事件を処理したことは間違いありません。その意味では立派な成功事例だと言えるでしょう。
しかし、法律的に見れば、この訴訟は被告側が圧倒的に有利な案件だったのではないでしょうか。派手な逆転劇というより、勝って当然の結果だったということです。
メディアが演出する「奇跡の勝訴」の罠
木下優樹菜さんの騒動から始まった損害賠償請求訴訟は、和解金ゼロという結果で決着しました。多くのメディアは「スゴ腕弁護士が3億円をゼロにした」と報じ、弁護士の手腕を讃えました。
しかし、実際には、訴訟自体に意味がなかったり、請求の法的根拠が希薄でそもそも勝ち目の薄いケースも数多くあるというのが実態です。
さらには、こうした報道には危険な罠が潜んでいます。こうした“手柄強調型”の報道は、一般の人に誤った期待や幻想を抱かせてしまいます。つまり、「高額な弁護士費用を払えば、必ず裁判に勝てる」「派手な勝利を収めた弁護士ほど優秀で信頼できる」というような誤った期待を抱かせてしまうおそれがあるのです。
勝てる訴訟を「奇跡」に仕立て上げる危うさ
今回の訴訟の報道を見ていると、勝てる訴訟を「奇跡」に仕立て上げる危うさが浮き彫りとなっています。結果だけを見て、「弁護士が奇跡を起こした」と鵜呑みにするのは危険であり、そう思い込んでしまうと、不必要な裁判や高額報酬に巻き込まれるリスクがあります。
今回の訴訟でも、評価されるべきは「勝訴」という結果ではありません。むしろ、原告側とその代理人が抱いていた「甘い見通し」と「リスク判断の誤り」にこそ、私たちは目を向けるべきなのです。
真に優秀な弁護士は、むしろ争わないことを選択する判断力を持っているものです。
派手な演出で勝利を誇示するよりも、最初から「この請求は無効だ」と見抜いて無用な争いを避けること。それこそが、弁護士のプロとしての仕事だと言えるでしょう。
大切なのは、弁護士をヒーロー視しすぎないこと。そして、訴訟の本質を冷静に見抜く目を持つことです。