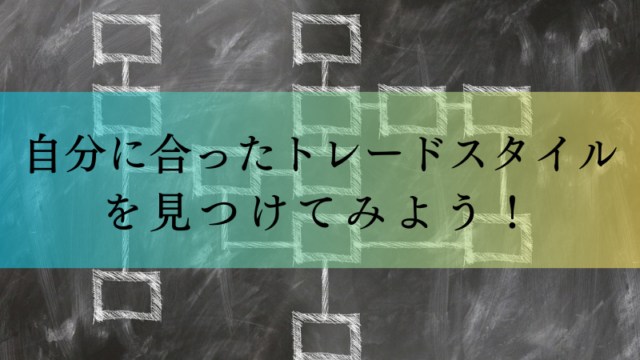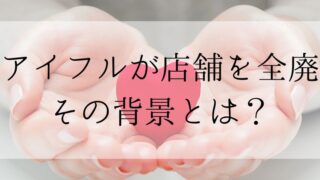投資って、なんだか難しそうに感じませんか? 特に、「どの株を買えばいいんだろう…」と悩んでいる人は多いはずです。 市場には、ものすごいスピードで成長する会社もあれば、昔からずっと安定している会社もあります。
でも実は、その中間に位置する「バリュー株」に注目する投資家が増えているんです。 バリュー株投資は、将来の大きな値上がり益(キャピタルゲイン)も、安定した配当金(インカムゲイン)も、どちらも狙える欲張りな投資方法だと言えるでしょう。
この記事では、そんなバリュー株投資の魅力や、具体的な銘柄について、分かりやすく解説します。 この記事を読めば、あなたの投資に対する不安がきっと解消されます。

目次
バリュー株投資とは?その基本を徹底解説
バリュー株投資、その定義は?
バリュー株投資とは、企業の本来の価値に比べて、株価が安くなっている銘柄を買う投資方法です。
この投資法の考え方を簡単に例えると、1万円の価値がある財布を5000円で買うというイメージに近いです。 投資家は、市場で安く売られている財布(株)を見つけ、その財布の中身(企業の本来の価値)が1万円あることを分析して確認します。
そもそも、なぜ株価が安くなるのでしょうか。それは、一時的な業績不振や、投資家の注目が集まらないなど、さまざまな理由があります。しかし、その企業の価値が正当に評価されれば、株価は上昇すると考えられます。
そのため、バリュー株投資では、企業が持っている財産や、将来稼ぐ力から見て、市場から低く評価されている株を探すのです。
バリュー株投資の変遷、グラハムからバフェットへ
バリュー株投資の父ベンジャミン・グラハム
バリュー株投資の考え方は、時代とともに大きく変わりました。その中心にいたのは、バリュー投資の父とされるベンジャミン・グラハムと、その考え方を受け継いだウォーレン・バフェットだと言えます。
この投資法の考え方を最初に広めたのは、「証券分析」という本を著したベンジャミン・グラハム氏です。彼は、数字に基づいた徹底的な分析の重要性を説きました。
ベンジャミン・グラハムは、企業の帳簿上の資産価値が最も重要視していました。「資産と株価の差」に着目するものです。彼は、企業を徹底的に数字で分析し、PERやPBRが抑えられており、かつ、企業がすぐに現金化できる資産から負債を引いた金額が高いものを選んでいます。
つまり、その企業が持つ資産価値に比べて、市場での株価が極端に安くなっている企業を探しました。
これはまるで、吸い終わった葉巻に残ったわずかな価値を見つけるような考え方で、シガー・バット投資とも呼ばれます。
ベンジャミン・グラハムの投資哲学は、1929年のウォール街大暴落(世界恐慌)によって決定的に形作られたと言えます。
当時は多くの投資家と同様に、企業の将来の成長期待や市場の熱狂に頼った投機的な手法を用いていました。しかし、1929年の大暴落とその後の市場の長期低迷を経験したことで、彼の財産はほとんど失われました。
この壊滅的な経験から、グラハムは、市場の熱狂や感情に左右される投機がいかに危険であるかを痛感しました。彼は、企業の実際の価値(内在的価値)を徹底的に分析し、その価値よりも株価がはるかに低い銘柄を探すという、より堅実で科学的なアプローチへと投資哲学を転換させました。
この考え方が「バリュー株投資」の基礎であり、彼は後に「賢明なる投資家」や「証券分析」といった著書でその理論を体系化しました。
バリュー株投資を発展させたウォーレン・バフェット
ウォーレン・バフェットは、グラハムの考え方をさらに発展させました。
彼は単に「安い株」を探すのではなく、「優れたビジネスを、手頃な価格で買う」ことを目指しました。これは、企業の質に着目したものです。
- 重視する要素:
- 経済的な堀(Moat): 競合他社が容易に真似できない、その企業独自の強みや競争優位性を指します。強力なブランド力(コカ・コーラ)、規模の経済(BNSF鉄道)、高い参入障壁(保険会社ガイコ)などがこれにあたります。
- 経営者の質: 誠実で有能な経営者が率いているかどうかも重要な判断基準です。
- ビジネスのシンプルさ: 誰にでも理解できる、シンプルで安定したビジネスモデルを持つ企業を好みました。
- 高い収益性: 長期にわたって高いROE(自己資本利益率)や利益を安定して生み出せる企業を選びました。
バフェットは、たとえPBRやPERが少し高くても、長期的に成長し続ける確固たる強みを持つ企業であれば、投資対象になると考えました。彼の投資は、徹底した財務分析に加え、企業の事業内容や市場における立ち位置を深く理解する定性分析が不可欠です。
これにより、現代のバリュー投資は、単なる定量的な分析のみではなく、企業の質や将来性といった定性的な分析も重要視するようになり、投資先を探しているのです。
| 項目 | ベンジャミン・グラハム | ウォーレン・バフェット |
| 重視点 | 徹底的な「数字」と「価格」 | 「ビジネスの質」と「将来の収益力」 |
| 分析方法 | 主に定量分析 | 定量分析に加え、定性分析も重視 |
| 投資対象 | PBRが極端に低い割安株 | 「経済的な堀」を持つ優良企業 |
| 比喩 | 「吸いかけの葉巻」を探す | 「素晴らしい企業を適正価格で買う」 |
成長株・配当株との違いを明確に
株式投資には、バリュー株投資の他に、成長株投資や配当株投資などがあります。それぞれの違いを理解することが大切です。
まず、成長株投資は、将来大きく伸びる企業に投資し、株価が急上昇することを目指します。
たとえば、新しい技術を持つスタートアップ企業などが典型です。これらの企業は、利益を再投資するため、配当をほとんど出さないことが多いです。
次に、配当株投資は、安定した配当金をもらうことを目的にします。
成熟した大企業など、定期的に安定した利益を出せる企業が中心です。株価の急な変動を気にせず、不労所得を得たい人に人気があります。
対して、バリュー株投資は、株価の上昇と配当の両方を狙います。つまり、成長株と配当株のいいとこ取りを狙うような投資法なのです。
バリュー株投資の何がいい?ポイントを解説
株価下落リスクが低い
バリュー株投資が持つ最大の利点は、株価の下落リスクが相対的に低く、安全マージンを確保しやすいことです。
安全マージンとは、企業の内在的価値(本来の価値)と、その企業の株価の差額を指します。 グラハムは、投資家は常にこの安全マージンを確保すべきだと考えました。なぜなら、企業の本当の価値を完璧に知ることは誰にもできないからです。
例えば、1万円の価値があると分析した企業の株を5000円で買えば、5000円の安全マージンを確保したことになります。もしあなたの分析が間違っていて、実はその企業の価値が7000円だったとしても、まだ利益を出せる可能性が高いです。これは、投資する時点ですでに株価が企業の本来の価値よりも安く評価されているためです。いわば、すでに底値に近い状態で投資を始めるようなものなので、もし市場全体が不況に陥ったとしても、株価の下げ幅が限定的になりやすいのです。
もちろん、景気後退や企業の業績悪化によってさらに株価が下がる可能性はゼロではありませんが、グロース株のように、将来の成長期待だけで株価が大きく膨らんでいる銘柄と比較すると、ショックに強いと言えます。
高い配当利回りを期待できる
バリュー株は、配当利回りが高い傾向にあることも大きな魅力です。
バリュー株の多くは、すでに成熟した大企業や老舗企業であることが多く、安定した収益基盤を持っています。企業が十分な利益を出せるようになると、その利益を株主に還元する配当金に回す余裕が生まれます。
2024年4月11日の日本経済新聞の報道によると、TOPIX(東証株価指数)の配当利回りが2.1%であるのに対し、PBR1倍未満の銘柄の配当利回りは2.8%でした。これは、バリュー株に分類されることが多いPBR1倍未満の銘柄は、市場平均より配当利回りが高いことを示しています。
株価が大幅に上がらなくても、定期的に入ってくる配当収入は、長期投資における重要な収益源となります。特に、リタイア後の資産運用として、安定した収入を得たい人にとって、このメリットは非常に大きいです。
バリュー株投資の最大の注意点「バリュートラップ」
バリュー株投資の最大の注意点は、「バリュートラップ」です。「バリュートラップ」とは、投資したバリュー株の株価が再評価などによって上昇せず、割安なまま放置され続けてしまう状態のことを指します。
例えば、株価が会社財産と比べて割安ということは、正当な評価を受ければ株価が上昇する可能性はあります。ですが、それはあくまで現有財産と比べて割安というだけの話で合って、将来的にその状態が存続するとは限りません。
多くの人が、その企業の将来の成長性の低さや業績悪化のリスクなどを市場が織り込んでいるために株価が割安なまま放置され、いつまで経っても株価が上がらない可能性もあるでしょう。
そのため、バリュー株投資をする際には、貸借対照表や損益計算書と言った数字を見る定量的な分析はもちろん、企業の競争力や将来性といった定性的な分析も重要となるのです。
バリュー株の具体例
日本のバリュー株2銘柄
日本のバリュー株として、花王と積水ハウスを紹介したいと思います。
両社に共通しているのは、華々しい成長はないものの、安定した収益基盤と健全な財務体質を持っている点です。これにより、市場から一時的に過小評価されたとしても、その内在的な価値は変わらず、株価は長期的に上昇する傾向にあります。
また、安定した利益から生まれる潤沢なキャッシュフローは、配当という形で株主に還元され、それが投資家にとっての安全マージンとなります。つまり、株価が上がらなくても、配当という形で着実にリターンを得られるため、安心して長期保有できるのです。
花王
花王は、シャンプーや洗剤といった生活必需品を扱う企業で、その強固な事業基盤が魅力です。
過去10年間(2015年~2024年)で株価は約1.5倍に上昇しました。さらに、1991年から連続増配を続けており、30年以上の増配実績は日本企業の中でもトップクラスです。
花王の最大の強みは、生活必需品を扱う事業の安定性にあります。過去5年間、売上高はほぼ横ばいで推移していますが、営業利益や経常利益も、大きな変動がなく安定しています。
このことは市場の変動に左右されにくい強固なビジネスモデルであることを示しています。
特に注目すべきは、高い流動性と健全な財務体質です。潤沢な現預金と少ない負債は、新たな事業投資や不況時の備えとなり、株主への安定した還元を可能にしています。参照(花王「財務ハイライト」)
積水ハウス
積水ハウスは、住宅事業の老舗企業であり、安定した収益力が強みです。過去10年間(2015年~2024年)で株価は約2.1倍に上昇しました。長年にわたる連続増配を続けており、配当収入を重視する投資家にも人気があります。
積水ハウスは、住宅事業を主軸とし、国内住宅市場の縮小にもかかわらず、過去5年間で売上高を着実に伸ばしています。これは、海外事業の拡大やリフォーム事業の強化など、成長戦略が成功している証拠です。
営業利益や経常利益も売上高に連動して増加傾向にあり、企業の収益力が継続的に向上していることがわかります。
また、積水ハウスも自己資本比率が高く、有利子負債が少ない強固な財務体質を持っています。これにより、安定した配当を継続的に実施することが可能となり、投資家にとって大きな魅力となっています。(参照:積水ハウス「業績ハイライト」)
米国のバリュー株2銘柄
米国のバリュー株として、コカ・コーラ(KO)とジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)を挙げます。
コカ・コーラは、世界的なブランド力という強固な「経済的な堀」を持っています。これは、他社が容易に真似できない強力な競争優位性です。過去10年間で株価は約1.4倍に上昇し、60年以上の連続増配実績を誇ります。飲料という生活必需品を扱う事業は景気に左右されにくく、安定した収益基盤が強みです。
ジョンソン・エンド・ジョンソンは、医薬品や医療機器、生活用品という多角的な事業ポートフォリオを持つことで、安定性と成長性を両立しています。過去10年間で株価は約1.3倍に上昇し、60年以上の連続増配を達成しています。
S&Pから最上位のAAAの信用格付けを取得していることからもわかるように、非常に強固な財務基盤も大きな魅力です。
これらの企業は、単なる安さだけでなく、確かな事業基盤と株主還元への姿勢によって、長期的なバリュー株として評価されています。