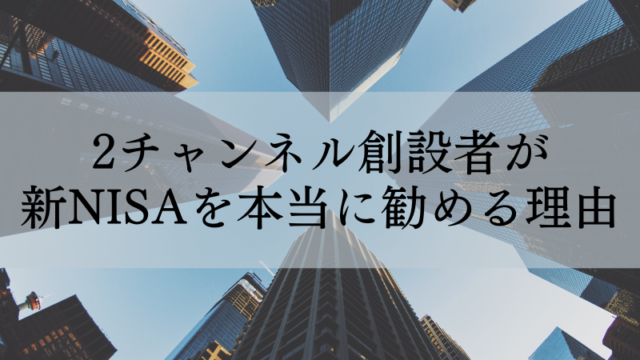投資を始めようと考えている皆さん、PER、PBR、ROEという3つの言葉を聞いて、なんだか難しそうだと感じていませんか?
これらの指標は、投資先の会社を選ぶ上で、とても大切なヒントを与えてくれます。しかし、それぞれの意味や、どうやって活用すれば良いのか分からず、なかなか一歩を踏み出せないという声もよく聞きます。でも、ご安心ください。これらの指標は、「速度」「距離」「時間」のようなもので、その関係性を知れば、誰でも簡単に使いこなせるようになります。そして、その関係を読み解くことで、将来大きく成長する会社や、安定した配当を出し続ける会社を見抜くのに使えるかもしれません。
この記事では、PER、PBR、ROEの関係を初心者の方にも分かりやすく解説し、投資に役立つ具体的な見分け方についてご紹介します。
目次
PER、PBR、ROEとは?
PER:株価が割安か割高か知る方法
PERは、株価が企業の1株あたりの純利益の何倍かを示す指標です。PERは「株価収益率」とも呼ばれ、その会社の利益から見て、今の株価が安いか高いかを判断するのに使われます。これは、一般的に、PERが低いほど「割安」、高いほど「割高」と見なされます。
具体的には、「株価が1株あたりの純利益の何倍か」を示すものです。
PER=株価/1株あたり純利益 (EPS)
例えば、株価1,000円で、1株あたりの純利益が100円の会社があれば、PERは10倍になります。
1,000円(株価)/100円(1株あたりの純利益)=10倍
この10倍という数字は、「この会社が今の利益水準を維持すれば、投資したお金を回収するのに10年かかる」ことを意味します。
日本の株式市場全体では、PER15倍程度が平均的な水準とされています。ただし、この数字はあくまで目安です。例えば、IT企業のような急成長が期待される業界では、将来の利益拡大を見込んでPERが高くなる傾向にあります。一方で、銀行株やインフラ系、鉄鋼系などは、規制や設備投資などの理由から急激な成長は見込めないと考えられやすく、PERが低く抑えられる傾向にあります。
PBR:企業の資産価値を知る方法
もう一つの重要な指標があります。それがPBRです。PBRは「株価純資産倍率」と呼ばれ、その会社の資産から見て、今の株価が妥当かどうかを判断するのに役立ちます。「株価が1株あたりの純資産の何倍か」です。
PBR=株価/1株あたり純資産 (BPS)
計算式は、例えば、株価が500円で、1株あたりの純資産が500円の会社があれば、PBRは1倍になります。
500円(株価)/500円(1株あたりの純資産(BPS))=1倍
PBRは、企業が解散したときに株主にどのくらいの資産が戻ってくるかを示す「解散価値」と、現在の株価を比較するのに使われます。仮に、PBRが1倍を下回る場合、その会社の株価は、保有する純資産の価値よりも低いことになります。つまり、その会社が今日この場で解散したら、手元に返ってくるお金の方が株価より高くなるということです。
言い換えれば「市場がその会社の解散価値以下と評価している」ことを示唆し、「割安」と見なされます。
ROE:経営の効率性を知る方法
PERとPBRで割安な株を見つけても、その会社のお金の使い方が効率的でなければ、将来の成長は期待できません。ここで登場するのがROEです。ROEは「自己資本利益率」と呼ばれ、株主が出資したお金(自己資本)を、どれだけ効率的に使って利益を上げているかを示します。
ROEの計算式は、「当期純利益 ÷ 自己資本 × 100(%)」です。ROEが高いほど、その企業は株主の資本を有効活用して、より多くの利益を生み出していることになります。
一般的に、ROEが8%以上の企業は優良と評価されることが多いです。しかし、これも絶対的な基準ではありません。例えば、電力会社、鉄道、ガス会社などは、設備投資を積極的に行わないとならず、また、これらの資産は、自己資本として計上されるため、ROEの分母が大きくなります。そのため、ROEが低く抑えられやすいのです。
ですが、ROEが低いのが安定したビジネスモデルと強固な資産基盤を持つが原因なのでしたら、一概に「悪い投資先」とは言えません。むしろ、これらの企業は、安定した収益を基盤とした配当や株主優待を期待できることが多いです。
そのため、ROEも、他の指標と同様に、絶対的な指標ではなく、「業界」「ビジネスモデル」なども考慮する必要があると言えます。
PER、PBR、ROEで高成長株、高配当株がみぬける?
PBRとPERは、いずれも株価が妥当かどうかを判断するために不可欠な指標です。しかし、両者は算出する際の要素が異なります。PBRが純資産(会社の安定性)に着目しているのに対し、PERは収益力(会社の稼ぐ力)に着目しています。
ROEは、経営の効率性・収益性を示す指標であり、ROEが上昇している企業は、自己資本を効率良く活用して利益を生み出せていることを意味します。
これらの指標は密接に関連しあっていることから、したがって、株価を判断する際には、3つの指標を組み合わせて総合的に判断することが求められます。
さらに、これらの指標が高い会社や低い会社は、どんな傾向があるかについても知っておいていいでしょう。結論から言えば、PER、PBR、ROEは高成長株を見抜くのに役立つ可能性があると言えるのです。
PER、PBR、ROEの関係
ここまでの解説を見ても、「PER、PBR、ROE、なんだか難しい」と感じたかもしれませんね。しかし、これら3つの指標はバラバラなものではなく、実は密接に関係しあっています。
投資家にとって、少ない自己資本で大きな利益を出せる企業は投資対象として非常に魅力的ですよね?このように収益性の高い優良企業として評価されることによって、資金調達がしやすくなり、結果としてPBRも上昇するケースが少なくありません。
つまり、PBR(純資産)=PER(利益を出す力)×ROE(経営の効率性・収益性)という関係が成り立つのです。この式から、ROEとPBRは互いに影響し合う関係にあることがわかります。
この式はPER=PBR÷ROEのように変形することもできます。ROEが上昇すれば、PERが低くなることがわかります。これは、「経営の効率性・収益性(ROE)が上がれば、利益に対する株価(PER)が割安になる」という状況を意味します。高ROEかつ低PERの企業は、収益性に対して株価が割安である可能性が高いため、投資家にとっては理想的な状態であり、買い手が増えることで株価の上昇が期待されるのです。
PER、PBR、ROEで高成長株を見抜く(サンリオの事例)
高成長株は、投資家の将来への大きな期待を反映して、PER、PBR、ROEといった指標がすべて高水準にある傾向があります。キャラクタービジネスで世界的な人気を誇るサンリオは、近年、まさにこの特徴を示しています。
サンリオの株価は、5年前の2020年8月下旬には1,000円台で推移していました。しかし、直近の2025年8月には7,000円台にまで上昇しています。この間の上昇率は、およそ400%以上に達します。つまり、5年前にサンリオ株を100万円分購入していれば、その価値は500万円以上に膨れ上がっていた計算になります。
PER・PBRに注目しますと、2024年3月期にはPERが37.2倍、PBRが15.9倍と、一般的な企業の平均値を大きく上回る水準に達しています。さらに、ROEは2024年3月期には48.6%という驚異的な数値を記録しました。これらの数値が高いことからは、多くの投資家が「サンリオは今後も高い成長を続ける」と強く期待していること、資本の効率が高いことを評価していることがうかがえます。
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
| 売上高 | 417億円 | 496億円 | 647億円 | 727億円 | 790億円 |
| 純利益 | -33億円 | 11億円 | 98億円 | 129億円 | 145億円 |
| PER | – | 42.1倍 | 36.5倍 | 37.2倍 | 38.5倍 |
| PBR | – | 1.8倍 | 11.2倍 | 15.9倍 | 16.5倍 |
| ROE | -7.2% | 2.1% | 23.5% | 48.6% | 49.3% |
※各指標は年度末の数値であり、変動します。
このように、サンリオは売上高と純利益の急成長に加え、PER、PBR、ROEといった主要な株価指標が軒並み高水準にあることから、典型的な高成長株であると判断できます。

PER、PBR、ROEで高配当株を評価する(日本郵政の事例)
日本郵政グループ(証券コード: 6178)の株価指標は、全体的に低水準で推移しています。
以下の表は、最新のデータに基づいて修正した、日本郵政の過去5年間の主要な財務データと株価指標です。
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
| 売上高 | 11.2兆円 | 11.0兆円 | 11.0兆円 | 10.9兆円 | 10.8兆円 |
| 純利益 | 4,206億円 | 4,887億円 | 4,375億円 | 4,286億円 | 4,124億円 |
| PER | 9.0倍 | 7.9倍 | 8.8倍 | 9.2倍 | 9.5倍 |
| PBR | 0.2倍 | 0.2倍 | 0.2倍 | 0.2倍 | 0.49倍 |
| ROE | 3.3% | 3.5% | 3.2% | 3.0% | 2.86% |
*注記: PBRの数値は、決算発表日や株価によって変動します。
日本郵政のPER、PBR、ROEが全体的に低いのは、まず、事業の成長性が限定的であるためです。郵便物の減少や市場の成熟により、大きな利益増加が見込めません。このため、投資家からの将来への期待が低く、株価が純資産や利益に対して割安に評価されます。
さらに、日本郵政は、郵便局ネットワークや金融事業が保有する巨大な自己資本を持つため、ROEの分母が膨大になります。分子となる純利益は安定しているものの、分母の大きさに比べて相対的に小さいため、ROEは常に3%前後という低い水準にとどまります。
ただし、日本郵政は、その安定した収益モデルと強固な財務基盤を背景に、継続的に安定した利益を確保しています。この安定的な利益を、積極的な事業拡大よりも、株主への還元に優先的に充てるという経営方針を取っているため、安定した高配当が可能となっています。実際、「数字で見る日本郵政」で公表される配当性向は62.6%と極めて高いです。
この「安定配当」という点が、日本郵政が投資家にとって魅力的な銘柄である主要な理由です。