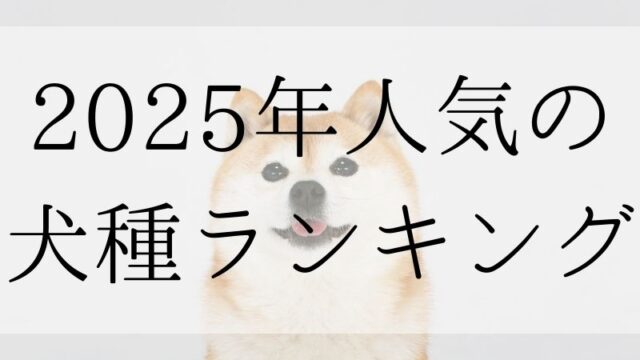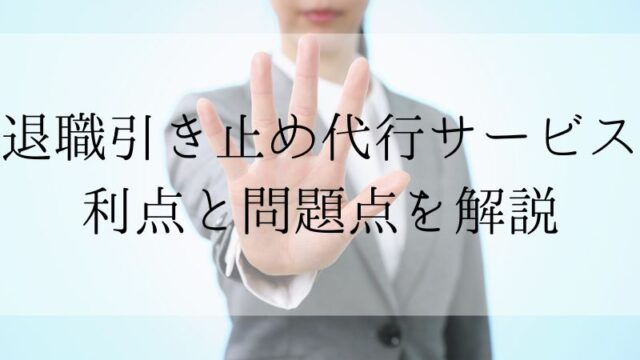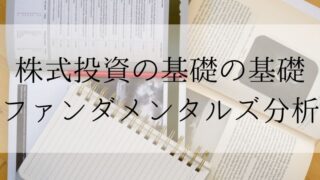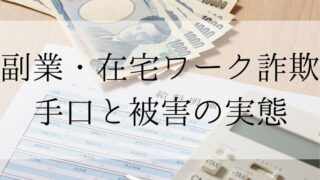人生の中で、「持ち家」と「賃貸」のどちらを選ぶべきか、一度は悩んだことがあるのではないでしょうか。毎月の家賃を払い続けるのはもったいないと感じる一方で、住宅ローンを組んで大きな借金を背負うことには不安がありますよね。この決断は、あなたの今後の人生を大きく左右すると言っても過言ではありません。後悔しない選択をするためには、感情ではなく、きちんとしたデータや客観的な視点が必要です。
この記事では、持ち家と賃貸それぞれのメリットとデメリットを、経済的観点やライフスタイル、そしてリスクという3つの側面から徹底的に比較します。また、公的な機関が発表している最新の統計データや具体的なシミュレーションを交えながら、あなたにとって最適な答えを見つけるためのヒントを提供します。
目次
持ち家がもたらすメリット・デメリットは?
持ち家最大のメリットは生涯コストを減らせること
多くの人が、住宅を持つことに対して、憧れを抱いているようです。
総務省統計局の「平成30年住宅・土地統計調査」によれば、全国の持ち家率は61.2%に達しています。多くの人が持ち家を「資産」として捉え、購入していることがわかります。
持ち家の最大の魅力は、まさに「生涯のコストを抑えられること」です。賃貸に住み続ける限り、家賃という支払いは一生涯続きます。一方、持ち家の場合、住宅ローンを完済すれば、それ以降は家賃という大きな出費がなくなります。この違いが、老後の生活を大きく左右するのです。
では、具体的な数字で比較してみましょう。
賃貸の場合、例えば、月10万円の家賃を払い続けたとします。30歳から80歳までの50年間で考えると、家賃の合計額は 6,000万円(10万円 × 12ヶ月 × 50年)にもなります。この金額は、住居費として完全に消費されるお金です。
一方、持ち家の場合、例えば、3,000万円の住宅を35年ローン(金利2%)で購入したとします。ローン完済までに支払う総額は約4,160万円となります。この金額には元金(3,000万円)と利息(約1,160万円)が含まれますが、ローンを完済すれば、その家は資産としてあなたのものになり、その後の家賃はかからなくなります。
このシミュレーションからわかるように、賃貸は50年間で6,000万円を「消費」しますが、持ち家は4,160万円の支払いで「資産」を手に入れることができます。最終的に手元に残るものが全く異なるのです。
持ち家には控除制度や団信がある
また、持ち家には、「住宅ローン控除」という国の支援制度があります。これは、年末時点の住宅ローン残高に応じて、所得税や住民税から一定額が控除される制度です。現在の控除率は、年末のローン残高の0.7%です。例えば、年末のローン残高が3,000万円の場合、控除額は年間で最大21万円にもなります。。この控除制度を賢く利用することで、実質的な住宅コストを大きく下げることができ、生涯のコスト削減に貢献します。
さらに、持ち家購入の際に、ほとんどの人が加入する「団体信用生命保険」(団信)も大きな安心材料です。団信とは、住宅ローンの返済中に、契約者が死亡したり、高度障害状態になったりした場合に、残りの住宅ローンを保険金で完済してくれる制度です。これにより、万が一のことがあっても、家族はローンの支払いに追われることなく、住み慣れた家に住み続けることができます。
そして、持ち家は最終的に「資産」として手元に残ります。売却すれば現金化できますし、賃貸として貸し出すことも可能です。また、子どもに相続させることもできます。これは、どれだけ家賃を支払っても何も手元に残らない賃貸にはない、持ち家だけの大きなメリットです。
この経済的な優位性こそが、多くの人が持ち家を選ぶ最大の理由と言えるでしょう。
持ち家が抱える「リスク」を直視する
一方で、持ち家には注意すべきリスクが確かに存在します。
まず、価格変動のリスクです。持ち家は「資産」になる一方で、その価値が将来、下がる可能性もゼロではありません。不動産価格は常に変動しており、地域によってその動きは大きく異なるのです。
国土交通省が発表している「地価公示」によれば、都心部や一部の地方中枢都市では住宅地の地価が上昇傾向にあります。たとえば、東京都の地価は近年、一貫して上昇を続けており、駅近や人気エリアの物件は価値が維持されやすい傾向が見られます。しかし、全国的には地価が横ばい、あるいは下落している地域も多く存在します。特に、人口減少が続く地方では、空き家が増え、不動産価値が下落する傾向が顕著です。
さらに、近年は物価高騰の影響で、住宅価格全体が上昇傾向にあります。建設資材の価格高騰や人件費の上昇が要因となっており、特に新築物件は高値になりがちです。現在の高値で購入した物件が、将来的に市場価値に見合わなくなる可能性も考慮しなければなりません。(新築マンション平均価格1億円超 首都圏1都3県 7月発売分)
また、住宅ローンを組む際に、変動金利を選ぶと、将来の金利上昇リスクを常に抱えることになります。金利が上がれば、毎月の返済額が増え、家計を圧迫する可能性があるのです。
金融機関が公表しているデータによると、2025年9月時点の住宅ローンの平均金利は、変動金利の平均は0.4%〜0.8%程度、固定金利の平均は1.5%〜2.0%程度です。
変動金利は、固定金利に比べて金利が低いため、月々の返済額が抑えられるというメリットがあります。しかし、日本銀行の金融政策によって金利が引き上げられれば、返済額は一気に増える可能性があるのです。低金利時代がいつまでも続くとは限らないため、変動金利を選ぶ際には、将来の金利上昇に備えた返済計画を立てる必要があります。
さらには、持ち家には、毎月のローン返済以外にも「維持費」という見えない出費が必ず発生します。代表的な維持費は、毎年課せられる固定資産税と、災害に備える火災保険・地震保険料です。
さらに、建物の老朽化に伴う修繕・リフォーム費用も大きな負担となります。屋根の塗り替え、外壁の補修、水回りの設備交換など、これらは計画的に行うべき必須のメンテナンスです。
そして、近年は物価高騰の影響がリフォーム代にも及んでいます。建材や設備の価格が上昇しているため、以前よりもリフォーム費用が高くなりがちです。特に、築年数が経過した物件は、突発的な修繕が必要になることもあり、予期せぬ大きな出費が発生するリスクがあるのです。持ち家は、購入して終わりではなく、常にメンテナンスが必要な「生き物」であると考えるべきでしょう。
賃貸住宅のメリットとデメリットは?
身軽に生きる!賃貸がもたらす最大のメリット
賃貸生活の最大の魅力は、何といってもその「身軽さ」にあります。つまり、賃貸に住む人は、ライフステージの変化や転勤、そして人間関係のわずらわしさから解放される「自由」を手に入れることができるのです。
たとえば、会社から転勤を命じられた場合、他にも、結婚や出産で家族が増えることへの変化などに強く、その時々のライフスタイルに合わせて住まいを変えることが可能です。
この柔軟性は、持ち家では決して得られない大きなメリットと言えるでしょう。
また、煩わしい人間関係に強いという点も魅力だと言えます。
フリエ住まい総研「ご近所トラブル」に関する実態調査によると、「これまでにご近所トラブルを経験した方の割合は62%と半数を超えているとの報告があり、また、隣人がどんな人かを調べたいと考える人の割合は9割以上」とのことです。近隣にどんな方が住んでいるのか、その情報性の需要は非常に高いことが分かります。この点、賃貸なら、万が一近隣住民とのトラブルが発生した場合でも、契約満了を待って新しい場所に移動できるので、隣人トラブルを経験しても、持ち家より簡単に問題から距離を置くことが出来るのです。
さらに、住居の維持管理に手間がかからない点も大きな利点です。建物の老朽化による大規模な修繕費用や、設備の故障による修理費用は、基本的に大家さんや管理会社が負担します。自分で修繕費を積み立てたり、業者を探したりする心配がありません。
家賃だけじゃない、賃貸に潜む「見えないコスト」
賃貸には、家賃以外にも見落とされがちな「見えないコスト」が存在します。まず、契約時の初期費用です。敷金、礼金、仲介手数料、前家賃など、合計で家賃の数ヶ月分に相当する費用が必要になります。これは、引っ越しをするたびに発生する出費です。
また、更新料も大きな負担となります。多くの賃貸契約は2年ごとに更新が行われ、その際に家賃の1ヶ月分程度の更新料を支払う必要があります。引っ越しのたび、更新のたびにコストがかかるため、生涯にわたる支出を計算すると、想像以上に大きな金額になることがあります。
そして、最も重要なのが、老後の住居リスクです。高齢になると、収入が年金だけになり、家賃の支払いが困難になる可能性があります。また、連帯保証人を見つけにくくなったり、高齢者であることを理由に、入居審査が厳しくなるケースも少なくありません。
このリスクは、持ち家にはない、賃貸ならではのデメリットと言えます。
賃貸と持ち家は結局、どちらを選ぶべき?
後悔しないための判断基準は?
持ち家と賃貸、どちらを選ぶべきかという問いに、「これが正解」という答えはありません。なぜなら、どちらがあなたにとって有利かは、あなたのライフプランや価値観によって決まるからです。後悔しないためには、まずご自身の状況を客観的に見つめることが大切です。
まず、「経済的安定」を最優先するなら、持ち家の方が有利かもしれません。住宅ローンを完済すれば、老後の住居費の心配がなくなります。
一方で、持ち家の場合は急な状況の変化に対応しずらいというデメリットがあります。
持ち家の場合、人生が好調なことを前提にして住宅ローンを組むことになります。借金がない、仕事を数十年に渡り続けられるなど、安定した状況が続くことが前提なのです。
しかし、人生は思い通りにいかないこともあります。転勤、金銭問題、離婚や病気、勤務先の倒産など、少しのトラブルに見舞われるだけで状況が悪化する可能性も多いのです。(参照「債務整理をすると住宅はどうなる?気になる影響と対策方法を解説」)
一方、賃貸は「何かあったら引っ越せる」という「生活の自由度」や「身軽さ」が魅力で、このような身軽さは、持ち家のリスクを回避させてくれます。転勤や転職が多い方、将来の居住地が未定な方には、賃貸の方が適していると言えるでしょう。
あなたのライフプランに合わせた最適な選び方
最終的な判断を下す前に、あなたのライフプランを具体的に考えてみましょう。
【持ち家が向いている人】
- 今後数十年、同じ場所に住む予定がある人。
- 安定した収入があり、ローン返済の見通しが立つ人。
- 家を「資産」として残したい人。
【賃貸が向いている人】
- 転勤や転職の可能性がある人。
- ライフステージの変化に合わせて、住み替えたい人。
- 住居の維持管理に手間をかけたくない人。
どちらの選択肢もメリットとデメリットが存在します。重要なのは、「自分にとっての幸せな暮らし」とは何かを明確にし、その目標に合った選択をすることです。この情報を参考に、ぜひご自身の最適な答えを見つけてください。