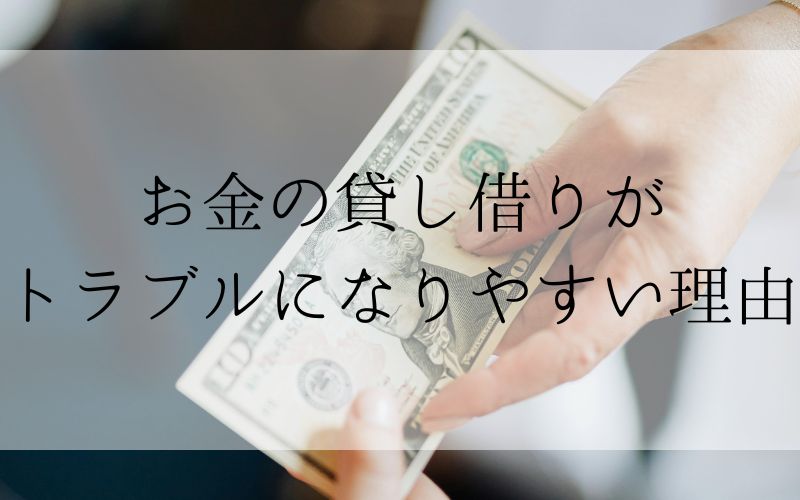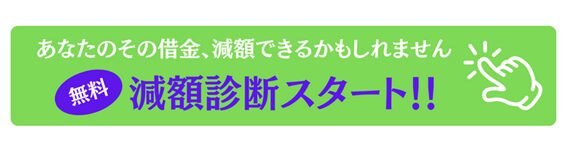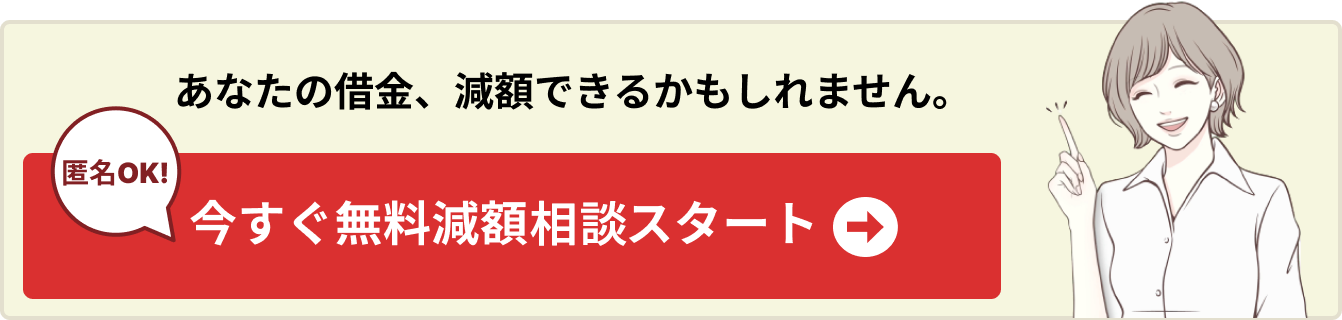「友人に急にお金を貸してほしいと頼まれたけど、どうしよう…」「家族が困っているなら、助けてあげたい」
親しい人からのお金の相談は、誰でも一度は経験することです。ですが、個人間のお金の貸し借りは、想像以上に危険な行為です。
それは、あなたの大切な人間関係を壊してしまうだけでなく、ときに、人生を左右するような重大なトラブルに発展することがあるからです。
この記事では、個人間のお金の貸し借りがトラブルになる本当の理由や、実際に起きた恐ろしい事例、そして、あなた自身を守るための具体的な自己防衛策について、わかりやすく解説します。
目次
個人間でのお金の貸し借りがトラブルにつながる理由
【理由1】返済能力の把握が甘くなる
個人間でのお金の貸し借りがトラブルにつながる理由として、まず、貸し手側の審査能力が十分ではなく、返済能力の把握が甘くなるということが挙げられます。
仕事としてお金を貸す銀行や消費者金融では、融資を行う際、彼らは専門的な知識とツールを駆使して、借り手の返済能力を厳しく審査します。たとえば、信用情報機関(CICやJICCなど)に照会し、過去の借入・返済履歴、延滞の有無、現在の借入状況などを細かくチェックします。
しかし、個人間のお金の貸し借りでは、このような客観的な審査は行われません。貸し手は、借り手から聞いた「給料が入ったら返す」「ボーナスで返す」といった言葉を安易に信じてしまいがちです。しかし、これらの言葉に明確な根拠はありません。
多くの場合、借り手は自分の経済状況を正確に伝えていません。なぜなら、収入や他の借金の状況を正直に話せば、お金を借りることができなくなるかもしれないからです。
結果として、貸し手は、借り手の本当の返済能力を把握できないまま、貸し倒れのリスクを背負うことになってしまうのです。

【理由2】法令違反や不備があるリスク
次に、法令違反や不備があるリスクです。プロの金融機関は、このような記録のミスをすることは稀ですが、個人間では非常に頻繁に起こるのです。
例えば、プロの貸金業者と異なり、個人間のお金の貸し借りでは、契約書や借用書が作成されないことが多く、これがトラブルの元になります。貸し借りの記録がないと、貸した側は「お金を貸した事実」そのものを証明することが難しくなるためです。
また、たとえ契約書を作成したとしても、利息は完全に自由に設定できるわけではありません。日本の法律では、利息制限法と出資法という二つの法律が金利を規制しています。利息制限法では、貸付額が10万円未満の場合は年20%が上限と定められており、これを超える部分は無効となります。また、出資法の上限金利は年20%で、これを超えて貸付を行うと刑事罰の対象になる可能性があります。
例えば、「10万円を貸して、来月までに11万円返して」という話は、一見すると少額のやり取りに聞こえるかもしれませんし、個人間ではよくある話ではないかと思います。しかし、この利息を年利に換算すると、その年利は約120%に相当します。これは、利息制限法や出資法の制限を越えてしまった違法な貸し付けだと言われてしまう可能性が十分にあります。
【理由3】個人に頼る借り手は、貸し手を甘く見てる
個人に頼る借り手は、貸し手を甘く見てることが多いというのも、トラブルに発展する原因です。
そもそも、親しい人からお金を貸してほしいと頼まれたとき、「なぜこの人は、銀行や消費者金融ではなく、自分に頼みに来たのだろうか?」と考えたことはありますか?
その答えは、多くの場合、彼らが正規の金融機関の厳しい審査に通らないほど、信用力が低いからです。
銀行や消費者金融は、お金を貸すプロです。彼らは収入や勤務先、そして信用情報機関(CICやJICCなど)に記録された過去の借金の履歴を徹底的に確認します。
この審査を通過できないということは、お金を貸すプロの目から見て「お金を返す能力がない」か、「返済する意思がない」と判断されていることを意味します。
言い換えれば、個人間のお金の貸し借りは、最初からきわめて信用力が低い人と取引することがほとんどです。
そのような人が、「銀行や消費者金融でお金を借りられなかったから」という理由で、あなたに近寄ってくるわけです。つまり、個人に頼る借り手は、貸し手が素人であることを見越して、こいつなら貸してくれると舐めているのです。
【理由4】貸し手と借り手の間に存在する期待のズレ
最後に、貸し手と借り手の間に存在する期待のズレもトラブルの原因です。
個人間の貸し借りがトラブルになる大きな原因の一つは、貸し手と借り手の間に存在する期待のズレです。借りた側は「親しい間柄だから、少しぐらい返済が遅れても大丈夫だろう」と甘く考えていることがよくあるのです。
「債務整理が失敗するとどうなる?失敗の原因と失敗しやすい人の特徴とは?」でも解説をしましたが、借金問題が泥沼化していく債務者は、自分の都合ばかり優先しているような人も多いですし、平気で嘘を吐きます。金借りる時にさえ本当のことを申告していないことさえあります。
一方で、貸した側は「お金は当然返ってくる」と信じています。法的には当然、返済を受ける権利があるのですが、現実的には、相手がお金を返さないということもよく起こります。
そもそも、お金は貸す側に決定権があり、その決定をしたのは貸した人です。当然、返ってこないリスクを考慮して貸す決定をしなければおかしいわけですし、現実にお金が返ってこなかったとしても、貸した側がリスクとして飲み込まないといけません。
ですが、個人の方がこのような現実を理解していないでお金を貸してしまうことは非常に多いのです。そして、この期待のズレが、やがて不信感を生み、人間関係を壊してしまうのです。
お金の貸し借りが命に関わるトラブルに発展する?
金銭トラブルが犯罪に変わる瞬間
金銭トラブルが犯罪に発展する過程は、債務者の不誠実な態度と、債権者の期待のズレが重なったときに起こります。
まず、お金を借りた債務者が、返済能力がないにもかかわらずお金を借りてしまうことがあります。これだけでも問題ですが、さらに返済を求められると、連絡を無視したり、言い訳を繰り返したりするなど、不誠実な態度を取ることが多々あります。
この行動は、貸し手である債権者の「いつか返してくれるだろう」という期待を大きく裏切ります。貸したお金が戻ってこないという現実と、借り手の不誠実な態度に直面することで、債権者は深い怒りや裏切り感を抱きます。
やがて、その怒りは精神的なストレスとなり、冷静な判断力を奪っていきます。借り手もまた、催促に追い詰められ、自暴自棄になることがあります。このように、双方の感情が限界に達したとき、口論がエスカレートし、暴行や傷害事件、最悪の場合は殺人といった取り返しのつかない犯罪につながってしまうのです。
金銭トラブルが犯罪のきっかけとなることは、警察庁の統計データでも明らかになっています。
警察庁が公表している「犯罪統計資料(令和5年)」によると、殺人事件の動機の内訳において、「金銭関係」は常に上位に位置しています。
たとえば、令和5年(2023年)のデータでは、殺人の動機として、「借金」や「金銭」が全体の約5%を占めており、これは「痴情(しじょう)」や「不倫」といった動機に匹敵する、あるいはそれを上回る割合です。
さらに、令和5年版の犯罪白書でも、過去5年間の「殺人」の動機として「金銭・借財」が一定数発生していることが示されています。これらの統計データは、お金の問題が個人の関係性を超え、社会全体で重大な犯罪の引き金となっていることを客観的に示しています。
実際にあった恐ろしい金銭トラブルの事件
ニュースの報道を振り返ると、金銭トラブルが殺人事件に発展したという痛ましい事例が多数存在します。
1. 借金返済を巡るトラブルで知人を殺害
2024年5月に宮城県岩沼市で発生した女性殺害事件では、逮捕された男が被害者の女性と金銭トラブルを抱えていたことが明らかになりました。男は複数の知人や消費者金融から借金を重ねており、自宅には督促状が届くほど経済的に困窮していました
khb東日本放送: 借金を重ねていた殺人容疑で逮捕の男 金銭トラブルを慎重に捜査 宮城・岩沼市女性保育士殺害事件 | khb東日本放送
2.長年の金銭トラブルが引き金となった夫婦殺害事件
2024年12月に千葉県柏市で発生した夫婦殺害事件で逮捕された77歳の男は、被害者の夫婦と「長年の金銭トラブル」があったと報じられています。この事件は、単発的な貸し借りではなく、解決されないまま放置された金銭問題が、長期間にわたって当事者の精神を蝕み、最終的に取り返しのつかない悲劇を引き起こすことを示唆しています。
めざまし8ニュース(YouTube): 「長年の金銭トラブル」 か? 柏市夫婦殺害で近所に住む77歳男を逮捕 放火の疑いでの逮捕状も【めざまし8ニュース】
3. 投げ銭から多額の金銭貸借へ発展した配信者殺害事件
2024年3月に東京・高田馬場で起きた女性配信者殺害事件は、当初「投げ銭トラブル」と報じられましたが、その後の捜査で、加害者とされる男性が被害者に対し、総額250万円を超える金額を「貸し付けていた」ことが判明しました。加害者は返済を求めて民事訴訟まで起こし勝訴していましたが、返済が滞ったため、最悪の事態へと発展しました。
東洋経済オンライン: 「ライバー刺殺」で見過ごされる”隠れた戦犯” | 東洋経済オンライン
このように、お金が絡むと、人は冷静な判断を失うということをこれらの事件は私たちに教えてくれます。感情的なもつれから、理性では考えられないような行動に出てしまうのです。
金銭貸借のリスクは、単なる貸し倒れだけではありません。あなたの人生や、大切な人の命に関わるような悲劇を避けるためにも、安易な金銭貸借は絶対に避けるべきです。もし、お金を貸すことを検討しているなら、こうした事例を思い出し、一度立ち止まって冷静に考える必要があります。
最後に:いざという時の自己防衛策3選
金銭消費貸借契約書で証拠を残そう
「書面なんてなくても大丈夫」と思わないでください。口約束は、後になって「言った、言わない」の水掛け論になり、法的にも立証が極めて困難になります。
金銭の貸し借りを行う際は、口約束ではなく、必ず金銭消費貸借契約書を作成してください。この書面には、貸した金額、返済の期日、利息(無利子の場合も明記)、返済方法、そして遅延した場合の損害金について、すべて具体的に記載する必要があります。
また、ただ作成するだけでなく、内容を公正証書にすることも有効です。公正証書にすることで、法的な効力が強まり、万が一の際に裁判を経ずに強制執行を行うことができるようになります。これにより、トラブルの解決がスムーズになります。
担保や保証人を設定する重要性
貸したお金が返ってこないリスクを減らすために、担保や保証人を要求することも重要な自己防衛策です。
担保とは、借り手が返済できなくなった場合に、代わりに金銭的価値のあるものを売却して貸付金を回収する仕組みです。これには、不動産や自動車などが含まれます。
また、保証人を立ててもらうことも有効です。保証人は、借り手が返済できない場合に、代わりに返済義務を負う人です。返済能力のある保証人を立ててもらうことで、貸し倒れのリスクを大幅に減らすことができます。
これらの要求に対し、借り手が難色を示す場合、それは相手の返済能力や誠実さを疑う一つの判断材料となります。
個人間のお金は、返ってこないものと思って貸す
最後に、元も子もない話ですが「個人間のお金は、返ってこないものと思って貸す」というのが、最大の自己防衛策だと言えます。
金銭トラブルの多くは、「きっと返してくれるだろう」という貸し手の期待と、「まぁ大丈夫だろう」という借り手の甘えから生まれます。この期待のズレこそが、人間関係を壊し、深い精神的苦痛を生み出すのです。
だからこそ、最も効果的な自己防衛策は、「貸したお金は返ってこないもの」と最初から覚悟することに他なりません。この心構えがあれば、もし返済されなくても、精神的なダメージを最小限に抑えられます。
繰り返しになりますが、お金を貸すプロである銀行や消費者金融は、貸金業法といった法令や業務に精通しています。彼らは、返済確保のためのノウハウや、借り手の返済能力を見抜く高い審査能力を持っています。これにより、貸し倒れを防ぎ、たとえ一部の未収金が出ても、事業全体で収益を上げ続けることができます。
それに対して、個人にはそのような専門的な能力はありません。にもかかわらず、多くの人は「返ってくるだろう」という甘い見通しでお金を貸しています。その結果、トラブルに巻き込まれることが多いのは事実です。
もちろん、お金を返さない相手が悪いというのは当然です。しかし、お金を貸すか貸さないかの最終決定権は、常に貸す側にあります。返ってこないことまで含めて事前に検討していなかった貸し手側は、被害者であると同時に、相手を見抜く能力がなかったという自己責任の側面も否定できません。
金銭を貸すという行為は、相手の人生だけでなく、あなたの人生にも大きな影響を与えます。もし、どうしてもお金を貸す必要がある場合は、そのお金が戻ってこなくても生活に支障のない範囲にとどめてください。そして、貸したお金は「あげた」と割り切るくらいの気持ちでいることが、あなた自身を守る最も重要な考え方なのです。